機械設計では、部品の肉厚(にくあつ)=材料の厚みを
できるだけ均一に保つことが非常に重要です。
見た目ではわかりにくいポイントですが、
加工のしやすさや変形のしにくさ、
さらには製品寿命にも大きく関わってきます。
均一な肉厚にする理由
① 加工ひずみを防ぐ
削る部分と残る部分の厚みがバラバラだと、内部応力のバランスが崩れ、
加工後に反りや歪みが発生しやすくなります。
特にアルミやステンレスなどの熱膨張率が高い材料では注意が必要です。
② 熱処理や溶接時の変形を抑える
肉厚にムラがあると、加熱や冷却の際に熱の伝わり方が不均一になります。
その結果、部品の一部だけが伸びたり縮んだりして、寸法精度が狂う原因になります。
③ 成形や鋳造の品質を安定させる
鋳物や樹脂成形品では、
厚い部分があると冷却が遅くなり、収縮ムラや巣(空洞)が発生します。
均一な肉厚設計をすることで、品質ムラの少ない安定した製品が得られます。
均一な肉厚を実現するための3つの設計ポイント
部品を設計する際、
「肉厚(厚み)をできるだけ均一にする」ことはとても大切です。
肉厚がバラバラだと、加工後に反りや歪みが出たり、
成形不良が起きたりすることがあります。
ここでは、そんなトラブルを防ぐための
「均一な肉厚を実現する設計の工夫」を3つ紹介します。
① 肉抜き(中空化)で厚みを一定にする
厚い部分をそのままにしてしまうと、
材料の冷却速度や内部応力にムラが生じ、
加工後の反りや歪みが発生しやすくなります。
そこで有効なのが「肉抜き」や「中空構造」です。
例えば、樹脂部品の裏側にリブ(補強板)を入れて格子状にすることで、
強度を確保しながらも厚みを均一化できます。
また、金属部品でも、ボス(立ち上がり)部分を中空にしたり、
補強板で補うことで、軽量化と剛性アップを両立できます。
厚い部分を削るよりも、リブをうまく配置するほうが効率的です。
② 段差を緩やかにする
厚みが急に変化すると、その境目で応力が集中しやすくなります。
これを防ぐためには、厚みをなだらかに変化させる設計が重要です。
代表的な方法は次の通りです。
こうした処理を施すことで、
強度を保ちながらも部品の寿命を延ばすことができます。
CADでモデリングする際は、「急な段差を避ける」ことを意識しましょう。
③ 板金なら「曲げ位置」と「板厚」の関係を考慮
板金部品では、板厚と曲げ半径の関係を誤ると、
割れやシワ、精度不良が発生します。
特に、厚みのある板を小さい曲げ半径で加工すると、
内側に強い引張応力がかかり、破損することもあります。
そのため、JIS(日本産業規格)などで定められた
最小曲げ半径を守ることが基本です。
一般的な目安としては、
といった基準が使われます。
板厚が増えれば、曲げ半径も大きく設計するのが鉄則です。
最小曲げ半径は板厚に比例し、薄い板ほど小さく、厚い板ほど大きくなります。
均一な肉厚を実現することで、
といったメリットが得られます。

設計時には、
リブ構造・緩やかな厚み変化・適切な曲げ半径を意識するだけで、
見た目にも精度的にも優れた部品設計が可能になります。
設計変更で見落としがちな「肉厚バランス」と「応力分布」
~FEM解析を活用した安全設計のすすめ~
機械設計では、ちょっとした設計変更が思わぬトラブルを引き起こすことがあります。
その代表的な例が「肉厚バランスの崩れ」です。
モデルの一部を修正しただけのつもりでも、
厚みが不均一になり、応力集中や変形の原因になることがあります。
この記事では、設計変更時に注意すべき肉厚バランスの確認方法と、
有限要素法(FEM)解析を使った応力確認のポイントを解説します。
設計変更のたびに肉厚バランスを確認する
肉厚バランスが崩れると何が起こる?
3D CADで形状を修正するとき、
局所的にモデルを伸ばしたり削ったりすることがあります。
しかし、「見た目が正しい」=「構造的に問題ない」とは限りません。
たとえば以下のようなトラブルが起きやすくなります:
特に、初期設計時は全体のバランスを考えて厚みを決めています。
そのため、部分的な設計変更によって意図せず厚みが変わると、
全体強度に悪影響を及ぼすことがあります。
実務でのチェックポイント
有限要素法(FEM)解析で応力分布を確認する
FEM解析とは?
FEM(Finite Element Method:有限要素法)解析は、
構造物を細かい要素に分割して、
荷重や拘束条件を与えた際の
「応力分布」や「変形量」を数値的に求める手法です。
設計段階で応力集中や過大変形を予測できるため、
“図面では見えない危険箇所”を見つける強力なツールです。
厚み差がある設計では特に有効
肉厚が均一でない構造は、応力が局所的に集中しやすくなります。
例えば、厚肉部から薄肉部へとつながるコーナー付近では、
荷重が集中して破損の起点になることがあります。
このような箇所は、
FEM解析で応力分布を確認することで以下の判断ができます。
実務での使い方
設計変更=構造バランスの再確認のチャンス
設計変更は単なる形状修正ではなく、
構造全体の再点検のタイミングでもあります。
部分修正のつもりで強度や精度を損なってしまうのは、現場でよくあるミスです。
以下の2点を習慣化するだけで、設計品質は大きく向上します。
- 設計変更ごとに肉厚バランスをチェックする
- FEM解析で応力分布を可視化し、弱点を早期発見する
少しの確認作業が、大きな手戻り防止につながります。
特に近年では、CADと解析の連携が進み、手軽に検証できる環境が整っています。
「厚みのムラを残さない」「応力を見える化する」——
これが、信頼性の高い機械設計を実現する第一歩です。
まとめ
均一な肉厚は、
▶ 加工精度を安定させる
▶ 変形・歪みを防ぐ
▶ 成形・鋳造の品質を高める
といった設計品質の土台になる考え方です。
軽量化やコストダウンを進める中でも、
「厚みを一定にする」という基本を守ることで、
結果的にトラブルの少ない信頼性の高い製品をつくることができます。



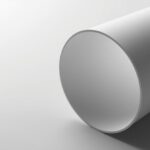
コメント