機械設計や装置の選定において、「防塵・防水性能(IP保護等級)」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
「ちょっとホコリや水がかかるだけなら大丈夫では?」と思ってしまいがちですが、実はその油断が機械の故障や誤作動、さらには事故につながることもあります。
この記事では、なぜ防塵・防水対策が必要なのかを、初心者にもわかりやすく解説していきます。
なぜ防塵・防水対策が必要なの?
工場や現場で使われる機械や装置には、「ホコリや水、油がかかる」という過酷な環境がつきものです。
こうした影響から機械を守るために欠かせないのが「防塵・防水対策」です。
本記事では、なぜその対策が必要なのか?その理由を初心者にもわかりやすく解説します。
理由①:ホコリや異物で機械が壊れるから
製造現場では、以下のような異物が空中に舞っています。
✔ 金属粉(研削・切削くず)
✔ 切粉(フライス加工など)
✔ 木くず
✔ 粉じん(セメントや食品原料)
こうした異物が機械内部に侵入すると、次のような不具合を引き起こします。
🚫 センサーやスイッチが誤動作する
🚫 リレーや基板がショート・絶縁不良になる
🚫 モーターやファンが回転不良を起こす
また、異物がベアリングやギアの隙間に入り込むと、摩耗や焼き付きの原因にもなります。
防塵対策の目的
- 電子機器の短絡や腐食を防止
- 可動部の摩耗や異常発熱を抑える
- 装置全体の信頼性と寿命を向上
理由②:水や油がかかるとショート・腐食の原因になるから
製造ラインでは、以下のような液体が機械にかかることがあります。
✔ 雨・水しぶき(屋外装置、洗浄工程)
✔ 加工油・切削油・クーラント
✔ 高圧洗浄水(食品・医療業界など)
これらが電気部品に侵入すると、深刻なトラブルが発生します。
🚫 配線や基板のショート・誤作動
🚫 コネクタの腐食
🚫 塗装面のはがれやサビ
さらに、食品工場や医療機器では、高圧洗浄や薬品洗浄に耐える防水性が求められるケースもあります。
防水対策の目的
- 電気トラブルの防止
- 機械の清掃性・衛生性の確保
- 屋外や高湿環境でも安定して使用可能
理由③:環境に合わせた「IP等級」の選定が必要
「この装置は防塵・防水対策がされています」と言っても、どのレベルかはIP等級で具体的に決まっています。
IP等級とは?
「IP65」のように、数字2桁で保護性能を表します。
- 1桁目(防塵):0〜6 → 数字が大きいほど粉じんに強い
- 2桁目(防水):0〜8 → 数字が大きいほど水に強い
| IP等級 | 防塵性能 | 防水性能 |
|---|---|---|
| IP20 | 指や異物の侵入を防ぐ | 水への対策なし |
| IP54 | 粉じんが入りにくい | 水の飛まつに耐える |
| IP65 | 粉じんが完全に入らない | あらゆる方向の噴流水に耐える |
| IP67 | 粉じんが完全に入らない | 一時的な水没に耐える |
設計時の注意点
- 使用環境(屋内/屋外/水濡れの有無)を事前に確認
- オーバースペック(IP67など)はコスト高になる
- メンテナンス性とのバランスも重要
防塵・防水対策は“故障を防ぐ第一歩”
防塵・防水対策は単なる「おまけ」ではなく、機械の信頼性・安全性を守るための必須項目です。
とくに屋外・粉じん・水や油が飛ぶ環境では、保護等級(IP等級)の確認と適切な対策設計が不可欠です。
一言アドバイス
「現場の“空気と水”が、機械を壊すか守るかを決める」
装置が長くトラブルなく動くかどうかは、
環境に合った防塵・防水対策がされているかどうかにかかっています。

設計者・選定者は、目に見えない空気や水のリスクにも目を向けましょう!
よくある防塵・防水対策の例
| 対策方法 | 内容 | 適用部位 |
|---|---|---|
| パッキン・ガスケット | 隙間からの粉塵・水侵入を防止 | 制御盤、筐体カバー |
| ケーブルグランド | ケーブルの引き込み部をシール | モーター、センサー |
| 防水コネクタ | 濡れた手や水濡れに強い | 操作スイッチ、接続部 |
| 防塵フィルター | 空気の取り込み口を保護 | ファン、冷却口 |
| エンクロージャ | 密閉型ケースで丸ごと保護 | 制御機器、電子機器 |
設計者が注意すべきポイント
〜防塵・防水対策は“最初の段階”がカギ〜
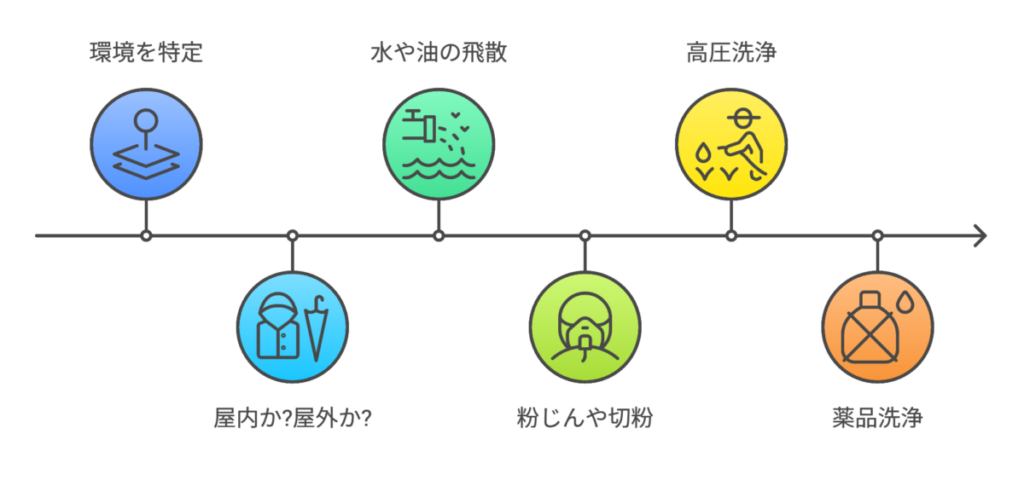
機械や装置を長く、安全に使うためには「防塵・防水対策」が欠かせません。
ただし、対策の仕方を間違えると、コスト増やメンテナンス性の低下につながることも。
ここでは、設計者が防塵・防水を検討する際に注意すべきポイントを、初心者にもわかりやすく整理します。
まずは“使用環境”をしっかり確認!
設計の出発点は、「どんな場所で使われるか?」を知ることです。
以下のチェックリストを確認しましょう:
屋内か?屋外か?
- 屋外なら雨・紫外線対策も必要
- 屋内でも水や粉じんが飛ぶ環境は注意
水や油が飛び散る工程か?
- 洗浄機、食品ライン、加工機などでは飛散が多い
- クーラント・切削油も要注意
粉じんや切粉が舞っているか?
- 木材加工、金属切削、研磨工程などでは粉じんが多い
- 電気部品への侵入で誤作動やショートのリスクあり
高圧洗浄や薬品洗浄はあるか?
- 食品・医療・半導体関連では薬品耐性や水圧耐性が求められる
- 耐薬品グレードの筐体や部品を選定する必要あり
コストとメンテナンス性のバランスを考える
「防塵・防水をしっかりやれば安心!」と思いがちですが、対策すればするほどコストが上がるのも事実です。
IP等級を上げるとコストも上がる
すべての装置をIP67にする必要はありません!
「実際の使用環境にとって必要十分な等級」を選ぶことが重要です。
✅ 密閉すればよいとは限らない!
- IP等級を高くすると、装置のメンテナンス性が下がることも
- 内部が見えにくく、点検がしにくい
- 分解しにくく、保守コストが上がる
完全防水が必要か?清掃性を優先すべきか?
⇒ 用途に合わせたバランス設計が重要です!
環境を“見抜いて”、必要十分な対策を!
防塵・防水対策は、「たくさんやれば正解」ではありません。
- 現場環境の把握
- IP等級の適正選定
- メンテナンス性の配慮
これらを設計段階で押さえておくことが、トラブルの少ない装置設計につながります。
設計者への一言
「防塵・防水は“万全”より“適切”を目指そう」

守りすぎても、使いづらくなる。
最適な設計は、“ちょうどいい保護”のバランスにあります。
まとめ:防塵・防水は“壊れない設計”の基本
「たかがホコリ」「ちょっとの水」でも、積もり積もれば大きなトラブルに発展します。
防塵・防水対策は、装置の寿命・安全性・信頼性を左右する重要な設計要素です。
「現場環境に合わせた保護が、故障を防ぐ最初の一歩」
IP等級の理解と、適切な対策設計を通じて、長く安心して使える機械を作りましょう!




コメント