機械設計で部品を作るとき、
「加工が大変そうだな」と思ったことはありませんか?
その悩みの多くは、工数や段取りの多さに原因があります。
この記事では、切削加工において「加工工数」や
「段取り替え」を減らすための設計の工夫を、
初心者にもわかりやすく10項目に分けて解説します。
1. 片側から加工できる形状にする
加工機に一度セットしたら、裏返さずにすべて加工できる形状が理想です。
裏表がある形状や、横方向にも加工が必要な場合、
段取り替え(治具の付け直し)が必要になります。
✅ 工夫ポイント
2. ワンチャックで加工できる寸法にする
旋盤やマシニングでは、チャッキング(固定)できる寸法範囲が決まっています。
長すぎたり、大きすぎたりすると、固定を変えて何度も段取りしなければなりません。
✅ 工夫ポイント
3. 標準工具だけで加工できるようにする
特殊な形状や深穴、小径すぎる穴などは、
特注工具や細いエンドミルが必要になり、工具交換・プログラム変更が増えます。
✅ 工夫ポイント
4. 加工面の向きをまとめる
部品の各面に加工が分散していると、
加工機を何度も回転・傾ける必要があり、工数が増えます。
✅ 工夫ポイント
5. 穴ピッチや位置は整数にそろえる
複数穴が等間隔で配置される場合、10mm・50mm単位などの整数ピッチが理想です。
CAD/CAMでの作業効率が上がり、プログラムもシンプルになります。
✅ 工夫ポイント
6. 同一工程内で完結する設計にする
工程を分けなければならないような部品は、段取り回数が増加します。
(例:溶接後に仕上げ、後加工が必要な段付き部品)
✅ 工夫ポイント
7. 一体加工ではなく分割構造を活用する
複雑な一体部品を無理に加工しようとすると、
5軸加工機や治具変更が必要になることもあります。
それよりも、複数部品に分けて簡単な形状にして組み立てる方が効率的です。
✅ 工夫ポイント
8. テーパや面取りを標準角度にそろえる
面取りやテーパーを自由な角度にすると、工具変更や特殊工具が必要になります。
✅ 工夫ポイント
- 面取り角度は45°に統一
- テーパーも標準の角度(7°、10°など)に揃える
9. 溶接・焼入れ・表面処理後の追加加工をなくす
表面処理後の穴あけや、焼入れ後の仕上げ加工は、
精度が出にくく、段取りも複雑になります。
✅ 工夫ポイント
10. 同一部品は同じ形状にそろえる
複数個ある部品で、寸法が微妙に異なると、
加工プログラムがすべて別になって手間が増えます。
✅ 工夫ポイント
まとめ:加工者目線で考える設計がカギ!
加工工数や段取りの多さは、コストアップや納期遅延の原因になります。
「加工者だったらどうする?」という視点で図面を見直すだけで、
段取り回数や工程数を大きく減らせることもあります。
図面を描くときは、「これは何回セットし直せば加工できるか?」を自問してみてください。
それが、「加工しやすい設計」への第一歩です!
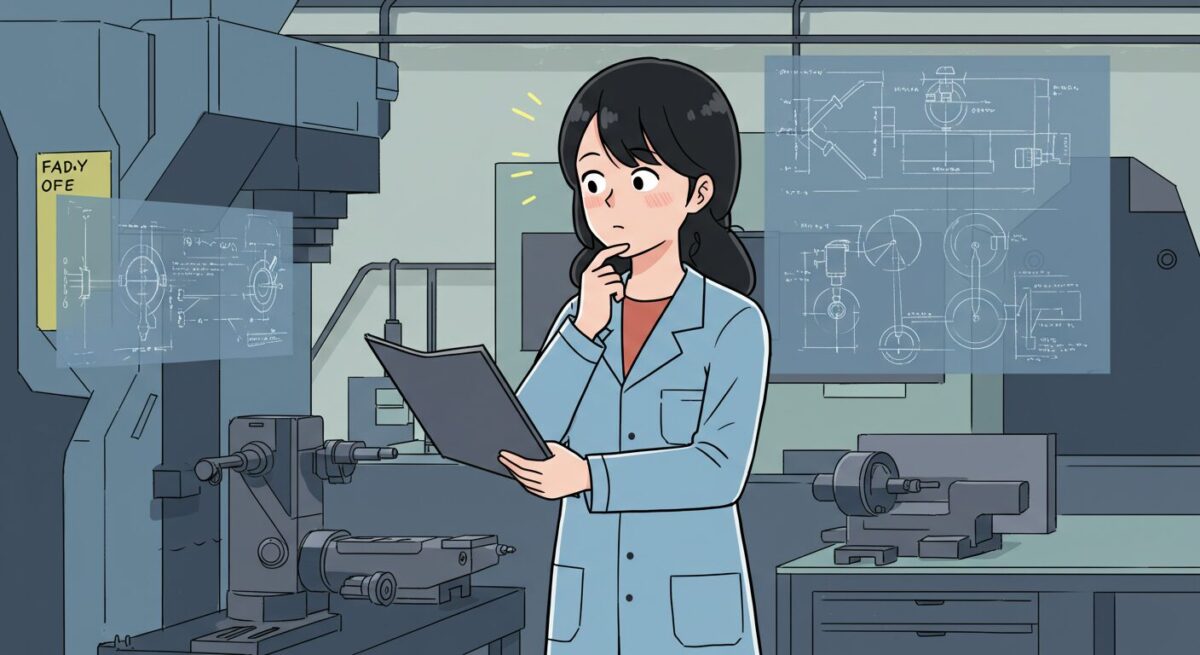



コメント