機械設計の仕事に就く、あるいは転職を検討している人の中には、「今まで使っていたCADソフトと、転職先で使うCADソフトが違うけど大丈夫だろうか?」という不安を持つ人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、CADソフトが変わっても基本的な設計スキルがしっかりしていれば問題ありません。とはいえ、スムーズに業務に入るためには、いくつかの対策や注意点を押さえておくことが大切です。
CADソフトが変わっても「設計スキル」は共通
まず最初に知っておいてほしいのは、CADは「道具」であって、「設計の考え方」や「力学的な知識」「加工への配慮」などの本質的な設計力は共通であるという点です。
たとえば、SolidWorksを使っていた人が、転職後にInventorやCreo、または2DのAutoCADに変わったとしても、設計者としての視点や設計のロジックがしっかりしていれば、CAD操作に多少の慣れが必要なだけで、十分に活躍できます。
CADソフト変更に伴う主な違い
とはいえ、CADソフトごとに以下のような違いがあるため、初めは戸惑うかもしれません。
- 操作画面の構成やアイコンの配置
- ショートカットキーの違い
- モデリングの流れ(履歴の扱い方など)
- ファイルの拡張子や保存形式
- 図面機能の癖(バルーンや寸法の入れ方など)
特に3D CADでは、「履歴ベースのCAD(例:SolidWorks、Inventor)」と「ダイレクトモデリング系(例:Creo、Fusion 360)」などで操作思想そのものが異なることもあります。
転職時の対策①:使い方を事前に予習しておく
転職先が使用しているCADソフトが分かっている場合、事前に操作方法を学んでおくことが有効です。
おすすめの学習方法
- 公式チュートリアルやYouTubeの解説動画を見る
- 無料体験版があれば実際に触ってみる
- Udemyや書籍での学習
- 職業訓練校やCADスクールの利用(転職前の時間がある人向け)
特に「基本的なスケッチ→押し出し→穴あけ→フィレット→図面化」などの一連の流れを体験しておくと、実務でも安心です。

転職時の対策②:自分の経験とスキルを整理しておく
転職の面接や職場では、「使用経験があるCADソフトは何か?」と聞かれることがあります。その際に、ただ「SolidWorks使えます」と言うのではなく、どんな設計に使っていたのか、どういう工夫をしていたのかを具体的に話せると信頼度が増します。
🔍例
「樹脂筐体の設計にSolidWorksを使い、スライド金型を意識した抜き勾配の設計をしていました」
「アセンブリでは干渉チェックを使って、部品間のクリアランスを確認していました」
このような説明ができれば、「CADが変わっても、この人は設計の考え方がしっかりしている」と判断してもらいやすくなります。
転職後の注意点:独自ルールや運用フローに注意
転職後にもうひとつ気をつけたいのが、会社ごとのCAD運用ルールや図面のフォーマットです。たとえば:
- 部品番号の付け方や図面のテンプレート
- アセンブリ構成の整理ルール
- データ管理(PDM)の運用方法
- 図面の寸法公差の書き方や注記のフォーマット
これらはCADの機能というより、組織のルールや設計標準なので、まずは新しい職場のやり方に素直に従いましょう。わからないときは積極的に質問してOKです。
外注や設計補助の人とも連携を
設計業務では、社内外の他の設計者や外注先とCADデータをやり取りする機会も増えます。データ形式(STEP、IGES、Parasolidなど)や、図面への注記・指示の仕方など、他者との連携を意識することも大切です。
日本における2D CADの利用状況
日本では、製造業や建設業などで2D CADの利用が根強く残っています。特に中小企業では、既存の設計資産や業務フローとの互換性を重視し、2D CADを継続して使用するケースが多く見られます。
一方で、3D CADの導入も進んでおり、設計の効率化や製品の可視化、シミュレーションの活用などを目的に、2Dから3Dへの移行を検討する企業も増えています。
2D CADの主なソフトウェア
日本で広く使用されている2D CADソフトウェアには、以下のようなものがあります:
- AutoCAD(Autodesk社)
- 世界的に最も普及している2D CADの一つで、多くの業界で標準的に使用されています。
- Jw_cad
- 日本国内で開発された無料の2D CADソフトウェアで、建築業界を中心に広く利用されています。
- DraftSight(Dassault Systèmes社)
- AutoCADと互換性のある2D CADで、コストパフォーマンスの高さから注目されています。
2D CADの今後の展望
2D CADは、引き続き多くの業界で重要な役割を果たすと考えられます。特に、簡易な図面作成や既存の2Dデータの活用、教育用途などでは、2D CADの需要が続くでしょう。
しかし、製品の複雑化や設計プロセスの高度化に伴い、3D CADの導入が進む中で、2D CADの役割も変化していく可能性があります。今後は、2Dと3Dの連携や、クラウドベースの設計環境への対応など、柔軟な運用が求められるでしょう。
2D CADは、機械設計をはじめとする多くの分野で長年にわたり使用されてきた重要なツールです。現在も多くの企業で活用されており、特に中小企業や特定の業務では欠かせない存在となっています。

今後も、設計の効率化やデジタル化の進展に対応しながら、2D CADの役割は進化していくでしょう。
日本で使われている主な3D CADソフトとその特徴
3D CADソフトは多くありますが、代表的なものとその特長を以下にまとめます。
| ソフト名 | 特長 |
|---|---|
| SOLIDWORKS | 操作性がよく、部品やアセンブリの設計に強い。教育現場でも使用例多数 |
| Creo(PTC) | 複雑なモデリングに対応、CAEとの親和性も高い |
| CATIA | サーフェス形状が得意で、複雑な曲面設計が可能 |
| NX(Siemens) | 高度な統合CAD/CAM/CAE環境 |
| Fusion (Autodesk) | クラウドベースで、設計・解析・CAMまでオールインワン |
3D CADの今後の展望
日本の3D CAD市場は、今後も成長が期待されています。特に、クラウドベースのCADソリューションの普及や、AIを活用した設計支援機能の導入が進むことで、設計業務の効率化がさらに進むと考えられます。
また、教育機関でも3D CADの導入が進んでおり、将来的にはより多くの技術者が3D CADを活用できるようになるでしょう。
3D CADは、製品設計の効率化や品質向上に不可欠なツールです。日本市場では、SOLIDWORKSをはじめとする主要なソフトウェアが広く利用されており、今後も市場の拡大が期待されています。

初心者の方も、まずは基本的な操作を学び、徐々にスキルを高めていくことで、3D CADを活用した設計業務に携わることができるでしょう。
まとめ:CAD変更は怖くない。準備と心構えがカギ
異なるCADソフトに変わるのは、誰にとっても最初は不安ですが、基本操作の習得と「設計力の本質」を押さえておけば心配無用です。
✅ 事前に触ってみて慣れておく
✅ 設計スキルを自信を持ってアピールする
✅ 転職先のCAD運用ルールを学ぶ姿勢を持つ
この3点を意識することで、スムーズに新しい職場でも設計者としての力を発揮できるはずです。











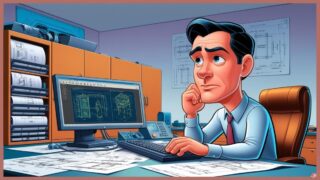





コメント