設備や装置の架台(フレーム)を設計する際、
どの鋼材を選ぶかは、強度や剛性、コスト、製作性に大きく影響します。
特によく使われるのが、
▶ 山形鋼(Lアングル)
▶ 溝形鋼(チャンネル)
▶ 角鋼管(角パイプ)
の3種類。
しかし「どれを使えば最適か?」は、
求める強度・重量・コストによって変わります。
本記事では、設備架台のフレーム設計で押さえておきたい
鋼材ごとの特性・メリット・ベストな使い分け
をわかりやすく解説します。
山形鋼(Lアングル)の特徴とメリット
Lアングルの特徴
L字形のシンプルな鋼材で、重量が軽く、取り扱いやすいのが魅力。
Lアングルのメリット
Lアングルのデメリット
Lアングルに向いている用途
- 装置の補助フレーム
- 補強材・ブラケット
- パネルや板金部品の取付け
→ 主構造ではなく「補助材として使う」のが最適。
溝形鋼(チャンネル)の特徴とメリット
チャンネルの特徴
U字型の断面を持つ鋼材。片側が開いているため、曲げに強い方向と弱い方向がはっきりしている。
チャンネルのメリット
チャンネルのデメリット
チャンネルに向いている用途
- 装置架台の脚材
- 荷重方向が明確な梁
- 据付架台やユニット台
→ 荷重方向が決まっている梁や脚材の“メインフレーム”に最適。
角鋼管(角パイプ)の特徴とメリット
角パイプの特徴
四角い中空構造で、三者の中で最もバランスの良い鋼材。
角パイプのメリット
角パイプのデメリット
角パイプに向いている用途
- 精度が必要な装置フレーム
- ねじりが発生しやすいユニット
- 高剛性 × 軽量フレーム
- 外観を重視する装置
→ 精度・剛性・外観、すべて求められるメイン構造に最適。
3種類の鋼材の使い分け(比較表)
| 鋼材 | 剛性 | ねじり強度 | 軽さ | コスト | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lアングル | 低 | 弱い | ◎ | ◎ | 補強材 取付部 |
| チャンネル | 高(方向依存) | 中 | ○ | ○ | 架台の梁 脚 |
| 角鋼管 | 全方向に高い | 非常に強い | ○ | △ | 主フレーム 高剛性装置 |
鋼材の使い分けの基本ルールを徹底解説
— 角パイプ・チャンネル・Lアングルの最適な選び方 —
設備や装置の架台を設計する際、「どの形状の鋼材を使うべきか?」は、
剛性・重量・コストに大きく影響します。
ここでは、設計者がよく悩む 角パイプ・チャンネル・Lアングルの
使い分けの基本ルール を、現場目線でわかりやすく解説します。
1. 軽量 × 強度バランスを取りたい → 角パイプ(角鋼管)
角パイプが「第一選択」と言われる理由
角パイプは四角い中空構造で、全方向に強い のが最大の特徴です。
つまり、強度と軽さと外観のバランスが最も良い万能材。
装置フレームが角パイプで作られることが多いのは、
「迷ったらコレ」という設計上の定番だからです。
角パイプが向いているケース
→ 一番汎用性が高く、設計自由度も高い。
よほど特別な条件でなければ角パイプが最適。
2. 荷重方向が明確 → チャンネル(溝形鋼)
「縦には強く、横は弱い」という特徴を活かす
チャンネルはU字型の断面を持つため、
という特徴を持っています。
この「強い方向」と「弱い方向」が
はっきりしているのが設計上のメリットです。
チャンネルが効果を発揮する使い方
つまり、
荷重方向が決まっている場所に使うと
“最小コストで最大効果”が出る鋼材です。
チャンネルを使う際の注意点
→ 設置方向を間違えると、本来の強度が出せない点に注意。
3. 補助的な補強や取付部 → Lアングル(山形鋼)
Lアングルは「補助材として最強」
Lアングルは軽量かつ安価で、加工性も優れている鋼材ですが、
主構造としては剛性不足です。
しかし、
などに使うと、コスト・重量・加工性のバランスが非常に良くなります。
Lアングルのメリット
→ 主役ではなく「名脇役」として使う鋼材。
Lアングルを使う際の注意点
→ 強度を期待して使う素材ではなく、補助用途で真価を発揮。
使い分けの基本ルールを押さえるだけで設計品質が向上する
鋼材は、それぞれの特性を理解して正しく使い分けることで
「最小の重量・最小のコストで最大の剛性」が得られます。
- 角パイプ
→ 軽量 × 高剛性 × 見た目の良さ
→ 装置フレームの“第一選択” - チャンネル(溝形鋼)
→ 一方向に強い
→ 荷重方向が決まっている梁・脚材に最適 - Lアングル(山形鋼)
→ 軽くて安価
→ 補助的な補強・取付ステーに最適
鋼材の選択は架台設計の品質や安定性を大きく左右します。
この基本ルールを押さえておけば、より軽く、より強く、より合理的な設計が可能になります。
最近では「アルミフレーム」を使用する架台が増えている
近年、機械装置の架台では アルミフレームを
採用するケースが急増しています。
なぜアルミフレームが増えているのか?
軽量で扱いやすい
鉄鋼材と比べ 約1/3の軽さ。
組立・移動・レイアウト変更が圧倒的に楽。
追加工が簡単
溝にナットを差し込むだけで後付け部品が装着でき、
配線ダクト・センサー・カバーなどを容易に追加可能。
腐食に強い
酸化皮膜による耐食性が高く、
食品装置や医療関係でも採用しやすい。
見た目が良い
スタイリッシュでクリーン。
展示装置・ラボ装置との相性が良い。
アルミフレームが向いている用途
特に、量産ラインのカスタマイズ性が求められる現場では
アルミフレームが急速にシェアを伸ばしています。
まとめ
架台フレーム設計は鋼材の使い分けが品質・コストを左右する。
設備架台や装置フレームの設計では、
鋼材の特性を理解して使い分けることで、
▶ 剛性確保
▶ 軽量化
▶ コスト低減
▶ 安定した据付性
が実現できます。
▶ 角鋼管(角パイプ):全方向に強く、メインフレームに最適
▶ 溝形鋼(チャンネル):一方向に強く、架台の脚や梁に向く
▶ 山形鋼(Lアングル):軽く安く、補助材・取付部に最適
鋼材の性質を理解し、最適な場所に最適な形を使うことで、
強く・軽く・コストの良い架台設計ができます。


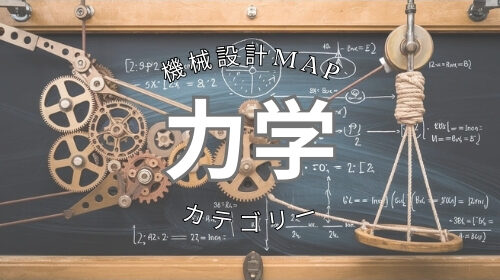


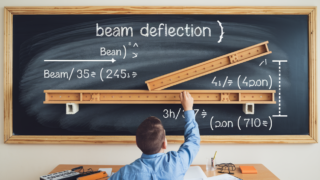

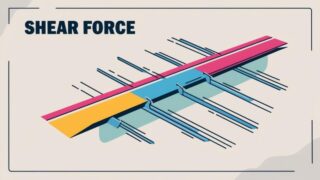




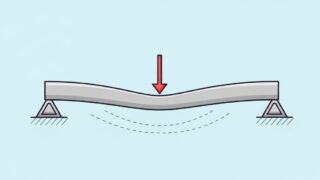

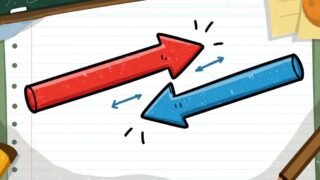

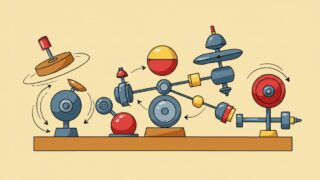

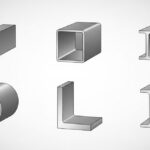
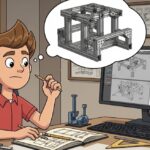
コメント