〜荷重を「見える化」する力センサーの基礎と選定のコツ〜
ロードセル(Load Cell)とは、
物体にかかる荷重(力)を電気信号に変換して検出するセンサーです。
工場の自動計量器や試験機、プレス装置、材料試験装置など、
多くの産業機械で使用されています。
ロードセルは、変位(たわみ)をひずみゲージで検出し、
その変化を電気的に処理することで「力」を計測しています。
ロードセルの主な構造と種類
ロードセルにはいくつかの構造タイプがあり、
使用環境や測定方法に応じて選定されます。
| タイプ | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| ビーム型(曲げ) | 荷重によるたわみを検出 | 計量台、簡易荷重測定 |
| S型 | 引張・圧縮両対応、取付が簡単 | 試験装置、吊り下げ計量 |
| ボタン型 | 圧縮荷重専用、コンパクト | プレス機、スペース制限時 |
| シェアビーム型 | ひずみをせん断方向で測定 | 多軸荷重測定 |
| リング型・円筒型 | 中心穴付きで通し設置可 | ボルト締付力や軸荷重測定 |
主な仕様・特性
ロードセルを選定する際は、以下のような仕様を確認することが重要です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 定格容量(定格荷重) | 測定できる最大荷重。 使用荷重は70〜80%以下が推奨。 |
| 精度 (非直線性・ヒステリシス・繰り返し性) | 測定誤差の要因。 高精度用途では±0.05%FS以下が目安。 |
| 感度(出力信号) | 通常mV/Vで表記。 アンプの選定にも関係。 |
| ゼロバランス | 無負荷時の出力。 アンプでのゼロ補正が必要な場合も。 |
| 許容過負荷 | 定格容量を超えた荷重にどれだけ耐えられるか。 安全率確保が大切。 |
| 温度特性 | 周囲温度の変化による出力誤差 (温度補償範囲・動作温度範囲)。 |
| 材質 | ステンレス製が多く、耐食・耐久性に優れる。 アルミ製は軽量。 |
電気的特性とアンプ回路
ロードセルはブリッジ回路(ホイートストンブリッジ)構成となっており、
外部から励起電圧(一般的に5〜10V)を与えて、
ひずみに応じた微小電圧(mV単位)を出力します。
この微小信号を増幅してA/D変換するアンプ回路(変換器)が必要です。
✅ ポイント:アンプや指示計との組み合わせで、システム全体の精度が決まります!
ロードセルの選定ポイント
測定する力の種類
必要な測定範囲(荷重容量)
設置スペースと取り付け方法
必要な精度
周囲環境(温度・防塵・防水)
アンプとの整合性
よくある用途と設置例
| 用途 | 使用されるロードセル | 補足 |
|---|---|---|
| 計量装置 (ベルトスケールなど) | ビーム型、 シェアビーム型 | 複数台構成で安定計測 |
| 引張試験機 | S型 | 両方向計測可能 |
| プレス圧管理 | ボタン型 | 圧縮力の変化を高速で検出 |
| ネジ締付力の測定 | リング型 | 中空ボルト貫通可 |
| タンクの重量測定 | ビーム型または 圧縮型を複数使用 | 変形を利用して質量検出 |
使用上の注意点
ロードセルの校正方法とは?
〜正確な「力」を測るために欠かせない工程をやさしく解説〜
ロードセルを使った「荷重計測」は、高精度であることが前提です。
しかし、どんなに高性能なロードセルでも使い始める前には校正が必要です。
また、使用中にも定期的な点検・再校正が推奨されます。
この記事では、ロードセルの校正とは何か、なぜ必要なのか、
どのように実施するのかについて、わかりやすく説明していきます。
なぜロードセルの校正が必要なのか?
ロードセルは荷重を電気信号に変換するセンサーですが、
以下の理由で実際の表示値とズレる可能性があります。
そのため、実際にどの荷重が加わったときに、
どれくらいの電気信号が出るかを「校正」によって把握し、
装置側で補正することが大切です。
校正の基本用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ゼロ点校正(ゼロバランス調整) | 無荷重時の出力を0に調整する |
| スパン校正(フルスケール校正) | 所定荷重をかけて出力スケールを合わせる |
| トレーサビリティ校正 | 国家標準に基づく校正機関による精密校正 |
| 簡易校正(現場校正) | 重りなどを使って自社で行う簡易的な校正 |
校正方法の手順(現場向け)
① 準備するもの
② ゼロ点校正
- ロードセルに荷重を加えていない状態にする
- 指示計の「ゼロリセット」機能を使って出力を0に調整
- ゼロ点の値が安定するまで数秒待機(初期ドリフトを防止)
③ スパン校正
- ロードセルの仕様に合った基準重り(例:5kg, 10kgなど)を段階的に載せる
- 指示計の設定画面で「校正荷重値」を入力
- 指示値が一致するように「スパン調整」を行う
- 校正後、異なる重りでも正しく表示されるか確認
校正時の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 偏荷重NG | 重りは中心に均等に載せること。偏荷重は誤差の原因。 |
| 温度安定 | 校正時は周囲温度を一定に保つ(15〜30℃が望ましい) |
| 時間経過 | ロードセルによっては「クリープ(時間変化)」が起こるため、重りを載せた後は数秒待機して安定させる |
| 繰り返し性確認 | 同じ荷重で複数回測定し、再現性(ばらつき)を確認 |
校正の種類と使い分け
| 校正方法 | 内容 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 一次校正(初期校正) | 新品導入時に行う | 精度確認とシステム補正 |
| 定期校正 | 数ヶ月〜1年ごとに実施 | 継続使用の精度維持 |
| トレーサビリティ校正 | 国家標準と紐づく校正証明付き | 検査機器、ISO対応現場 |
| 現場簡易校正 | 自社管理で手動校正 | 生産ラインや検出器調整 |
校正結果の記録(品質管理)
校正後は以下の情報を記録しておくと、トレーサビリティの確保や設備の品質保証につながります。
校正におけるトラブル例と対策
| トラブル | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 出力値が不安定 | 荷重の載せ方が不均一 温度変化 | 水平設置、重りの位置調整、 温調 |
| 校正後も誤差が大きい | アンプや表示器の設定ミス | 入力レンジや分解能を再確認 |
| ゼロ点がずれる | ロードセルの経年劣化・ 断線・ひずみ破損 | 他の正常なロードセルで 比較、交換検討 |
✔️ 設置状態や周囲温度も校正結果に影響するので注意
✔️ ロードセルは使う前に「ゼロ点」と「スパン」の校正が必須
✔️ 校正はトレーサビリティを意識して記録管理するのが理想
✔️ ゼロ点・スパンのずれは精度を大きく狂わせる
✔️ 重りは精度等級が明示された標準器を使用

ロードセルの正確な計測値を得るには、適切な校正が欠かせません。
特に機械設計の現場では「力の見える化」が品質に直結するため、
定期的な校正ルールを設けることが重要です。
まとめ
| 視点 | ポイント |
|---|---|
| 種類 | 測定目的に応じて形状・構造を選ぶ |
| 精度 | 用途によって必要精度を見極める |
| 環境 | 防塵・防水・温度特性に注意 |
| 接続 | アンプ・指示計との整合性が重要 |
| 設置 | 荷重の向き、偏荷重に注意して設置 |
ロードセルは、「力」を「電気信号」に変換することで、
装置の挙動を定量的に「見える化」できる便利なセンサーです。
構想段階からロードセルの種類と設置位置を
明確にしておくことが、設計トラブルを減らすカギです。
不明点があれば、メーカー仕様書や技術資料で
しっかり確認しながら選定を進めましょう!













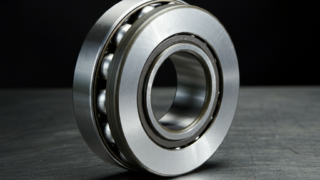
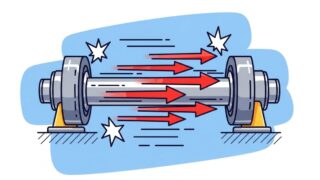










コメント