~小型・高精度の光検知センサーの特性と選定ポイント~
機械設計や装置設計において、「物の有無」や「位置」、
「通過」などを検出するセンサは欠かせない存在です。
中でも、小型で高速応答が可能な光センサとして活躍しているのが
「マイクロフォトセンサ」です。
マイクロフォトセンサは、発光部と受光部が一体化された構造を持ち、
非常にコンパクトで扱いやすいのが特徴です。
そのため、電子部品の検出や小型装置の原点検出、
カウンタ用途など、限られたスペースでの使用に最適です。
本記事では、このマイクロフォトセンサの基本的な仕組みや特性から、
実際の用途例や選定時のポイントまで、
初心者の方にも理解しやすいように解説していきます。
「他の光センサとの違いは?」「どんなときに使えばいいの?」
といった疑問を解消し、最適なセンサ選定に役立てていただければと思います。
マイクロフォトセンサとは?
マイクロフォトセンサとは、
光を使って物体の有無や位置を検出する小型センサーです。
一般的には、送信部と受信部を一体にした反射型や、
分離型の透過型(スロットタイプ)などがあります。
その名のとおり、「マイクロ(小型)」で
「フォト(光)」を使ったセンサというのが特徴で、
電子機器や小型メカ機構の組み込み用途で非常によく使われます。
マイクロフォトセンサの主な構造と種類
| 種類 | 概要 |
|---|---|
| 透過型(スロット型) | スリット内に物体が入ると、光が遮られON/OFFを検出 |
| 反射型 | 物体の表面からの反射光を受光し検知 |
| 回帰反射型(一部対応) | センサと反射板をセットで使用し、物体による遮光で検知 |
マイクロフォトセンサの特性
小型・軽量
コンパクト設計のため、
狭いスペースや小型装置への実装に最適
表面実装タイプ(SMD)なども存在し、基板直付け可能
高速応答性
応答速度はμs(マイクロ秒)~ms(ミリ秒)単位と非常に速く、
回転体や高速搬送にも対応
非接触で摩耗がない
光検知なので、物理的な接触がなく耐久性が高い
リミットスイッチのような接点摩耗がない
検出距離は短め
一般的に数mm~数十mm程度の検出範囲
遠距離の検出には不向き(レーザーセンサや光電センサが適)
ノイズ・周囲光にやや弱い
マイクロフォトセンサの選定ポイント
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 検出方式 | 透過型・反射型・回帰反射型から用途に合わせて選定 |
| 検出距離 | 数mm単位で確認。対象物の大きさや設置条件に注意 |
| 検出物体 | 光の反射率や色に影響される。反射型では黒色や透明体は要注意 |
| 応答速度 | 高速回転体・高速搬送にはμs対応のタイプが必要 |
| 出力形式 | NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力など制御方式と合わせる |
| 耐環境性 | 使用温度範囲、防塵・防水(IPランク)、耐振動性も確認 |
| 実装形状 | パネル取り付け、基板直付け、コネクタタイプなど装置に合わせて選定 |
マイクロフォトセンサの活用例
エンコーダーの回転検出
スリットディスクと組み合わせて、
高分解能の角度検出に活用
小型アクチュエーターの原点検出
ミニリニアガイドや電動スライドの
原点出し用センサに最適
カウント装置(コインや部品の通過)
透過型を使って、
物体の通過回数を正確にカウント
マイクロフォトセンサの注意点とトラブル対策
| 問題 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 誤検出 | 周囲光(蛍光灯や直射日光) | 遮光ケース使用 ノイズ対策品の選定 |
| 検出できない | 物体が黒・透明など反射率が低い | 感度調整可能なタイプや 反射シール使用 |
| 検出ずれ | センサ取り付け位置がズレている | マウント位置の微調整 or フィクスチャの工夫 |
| ノイズ混入 | 外部からの電磁ノイズ | シールド線 ツイストペア フィルタ回路の活用 |
マイクロフォトセンサとファイバーセンサの違いと使い分け
~用途に応じた光センサ選定のポイント~
機械設計において、物体の位置・通過・有無を検出するために
光センサは非常に重要な要素です。
その中でも特に「マイクロフォトセンサ」と「ファイバーセンサ」は、
よく似た機能を持ちますが、構造や性能には大きな違いがあり、
適材適所で使い分けることが必要です。
マイクロフォトセンサとは?
特徴
主な用途
ファイバーセンサとは?
特徴
主な用途
【比較表】 マイクロフォトセンサ vs ファイバーセンサ
| 項目 | マイクロフォトセンサ | ファイバーセンサ |
|---|---|---|
| センサ構造 | 一体型 (本体に光源と受光器が内蔵) | 分離型 (検出部とアンプが別) |
| 検出距離 | 短距離 (~30mm程度) | 中距離~長距離 (数cm~1m以上) |
| 感度調整 | 不可 (機種による) | 可 (アンプ側で詳細設定可能) |
| 設置の自由度 | 本体サイズに依存 | ファイバー部が小さいため柔軟 |
| 環境耐性 | 一般的な工場レベル | 高温・油・粉塵に 強いタイプあり |
| 応答速度 | 非常に速い (μs~ms) | 速い(μs~ms)+応答調整可 |
| メリット | 安価・省スペース 組込しやすい | 柔軟・高性能 微小物対応 |
| デメリット | 感度固定・距離短い | 本体がやや高価 設置や設定に注意 |
使い分けのポイント
| 使用シーン | 推奨センサ | 理由 |
|---|---|---|
| 小型装置の組み込み、原点検出 | マイクロフォト | 小型・一体型で簡単に組み込める |
| 狭くてセンサ本体が入らない場所 | ファイバー | ファイバー部が細く、 先端のみ挿入可能 |
| 高温環境・溶接や炉の近く | ファイバー | ファイバー部が耐熱仕様可 (200℃以上も) |
| 検出距離を伸ばしたい | ファイバー | 反射型で最大1m以上も可能 (高反射材併用) |
| 微小部品の検出 | ファイバー | スポット径が小さく、 微小対象に対応しやすい |
| 高速回転・搬送体の検出 | 両者可 | 応答性の観点ではどちらも◎。 コストやスペース次第で選定 |
注意点
| 内容 | マイクロフォトセンサ | ファイバーセンサ |
|---|---|---|
| 特徴 | 小型・高速・省配線 | 柔軟・高機能・広い用途 |
| 向いている用途 | 組込用、短距離検出 | 高温・微小・長距離・複雑な検出 |
| 使い分けのコツ | コスト・スペース重視 | 性能重視 |

「まずマイクロフォトセンサで試す → 条件が厳しければファイバーに変更」
という流れで設計を進めると、無駄なくセンサ選定ができます。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 特徴 | 小型・高速応答・非接触・短距離 |
| 用途 | 原点検出、カウント、小型装置向けの位置検出 |
| 選定のポイント | 検出方式、距離、対象物、環境性、応答性、取り付け形式など |
マイクロフォトセンサは、「狭い・速い・繊細」な検出に強い光センサです。
正しい選定と取り付けによって、機械装置の精度や信頼性を大きく高めることができます。
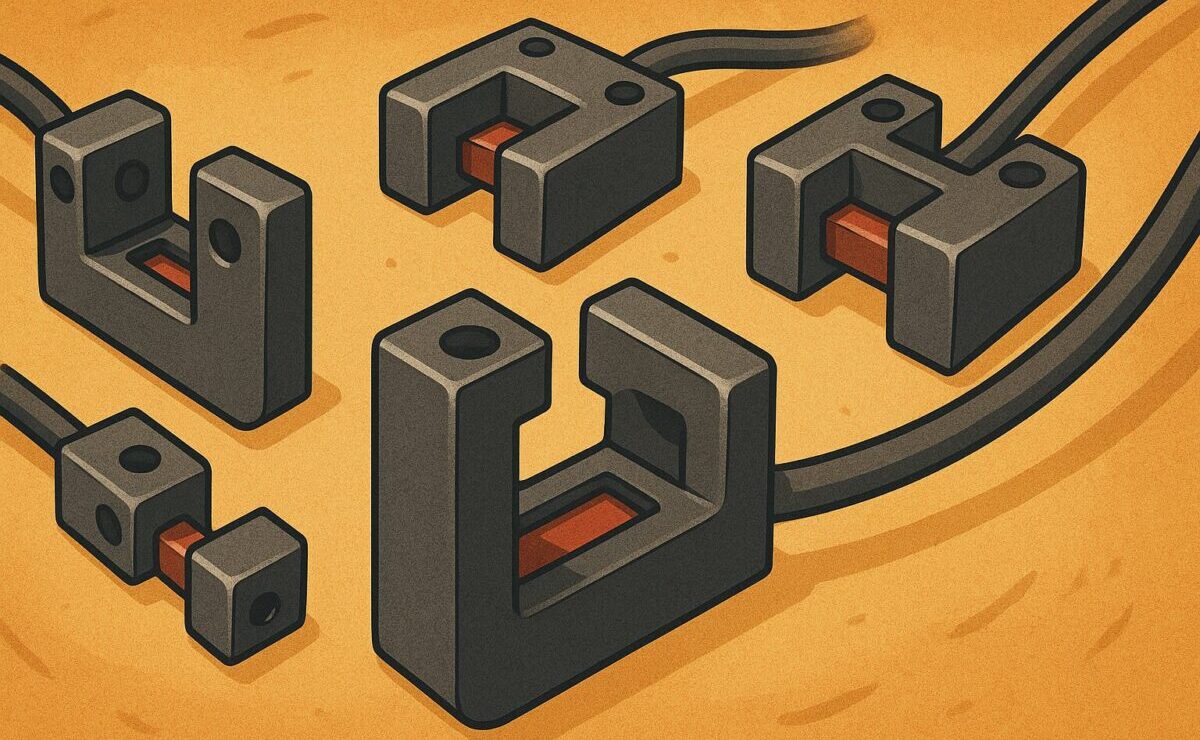






















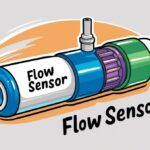

コメント