ネジ(おねじ・めねじ)は、機械設計において
非常によく使われる要素ですが、
「めねじ側(タップ加工)の設計をどうするか?」によって、
加工の難しさが大きく変わってきます。
初心者のうちは、何気なく止まり穴(底付き穴)を
設計してしまいがちですが、
実はこれ、加工現場では非常に困るパターンです。
今回は、「ねじ穴はできるだけ貫通にしよう!」というテーマで、
その理由と設計の工夫をわかりやすく解説します。
止まり穴のネジ加工はなぜ難しい?
タップが折れやすい!
止まり穴(底がある穴)にタップ加工を行うと、
切りくずが逃げる場所がありません。
そのため、タップが詰まりやすくなり、
無理な力がかかってタップがポキっと折れてしまうことがあります。

特に、細いタップ(M3やM4)は非常に繊細で、
再加工がほぼ不可能になることも…。
ネジの有効ねじ長さが足りない!
止まり穴では、穴の深さいっぱいにネジを切ることが難しく、
底付近はネジ山が浅くなります。
すると、ねじ込み長さが不十分で、強度不足になるリスクもあります。
工具選定・段取りが複雑になる
止まり穴にタップを切る場合、以下のような特殊な段取りが必要になります。

初心者設計者が気軽に描く止まり穴のネジは、
加工現場にかなりの負担をかけている可能性があるのです。
工夫ポイント:「ネジ穴(下穴)は貫通で設計する」
できるだけ、ねじ穴は貫通形状で設計しましょう。
【貫通穴のメリット】
| 項目 | コンテンツ |
|---|---|
| 切りくずの逃げがある | タップがスムーズに加工できる |
| タップの折損リスクが低い | 加工トラブルが激減 |
| 深い有効ねじが確保できる | ネジの保持力・締結力が上がる |
| サンプル | 加工コスト・段取りが簡単になる |
ねじ穴が貫通不可な場合、下穴は深く設計しよう!
~タップ加工トラブルを防ぐ工夫~
機械設計において「ねじ穴」は頻繁に登場する要素ですが、
その形状には大きく2種類あります。
一般的には、加工性の良さから「貫通穴」が推奨されます。
しかし、どうしても製品の構造や機能上
「ねじ穴を貫通にできない」というケースもあるでしょう。
そのような場合、タップ加工時のトラブルを回避するために
重要な設計ポイントがあります。
それは、
下穴(タップ下穴)を少し深めに設計すること!
本項では、止まり穴の下穴を深く設計する理由と、
その設計時の注意点についてわかりやすく解説します。
なぜ下穴を深くする必要があるのか?
タップ加工は「食いつき長さ」が必要
タップ(ねじを切る工具)は、刃の先端部分で材料を削りながら、ネジ山を形成します。
この先端部分(食いつき部分)は、1~3山程度は完全なネジ山にはなりません。
つまり、指定したねじ深さをしっかり確保するには、加工長さに余裕が必要になるのです。
切りくずの逃げ場所がないと、タップが詰まる
止まり穴では、ネジを切る際に出る
切りくずが穴の底にたまって逃げ場がありません。
その結果…
これを避けるには、
下穴に少し余分な深さ(逃げ)を持たせるのが有効です。
設計の目安:どれくらい深くすればよい?
下穴の深さは、以下のように設計するのが一般的です。
加工現場が助かる「最低余裕」
| 項目 | 推奨量 | 理由 |
|---|---|---|
| 食いつき長さ | 2山(2ピッチ) | 不完全ねじ部を考慮 |
| 切りくず逃げ | 2山(2ピッチ) | 切りくずが溜まっても加工しやすい |

最低でも4山分(4ピッチ)の逃げを持たせるのが目安です。
下穴深さの設計例(目安)
タップの種類により異なるためあくまで目安です。
最低でも下表以上の余裕を確保することがトラブル回避につながります。
| ねじサイズ | ピッチ | 下穴余裕 |
|---|---|---|
| M3 | 0.5mm | 2.0mm |
| M4 | 0.7mm | 2.8mm |
| M5 | 0.8mm | 3.2mm |
| M6 | 1.0mm | 4.0mm |
| M8 | 1.25mm | 5.0mm |
| M10 | 1.5mm | 6.0mm |
図面にどう指示する?
以下のように記載すると、加工者にも優しく、ミスも減ります。
【例】M6ねじ、ねじ深さ10mmの場合
M6深さ10mm
下穴深さ15mm
このように記載することで、必要なネジ山の長さを満たしながら、
タップの破損リスクを減らす設計が実現できます。
下穴が深すぎても問題ないの?
実は、下穴は多少深くても大きな問題はありません。
ネジの有効長さだけ守っていれば、
それ以深の部分はネジが切られずに「タップ逃げ」として機能するだけです。
ただし、以下の点には注意してください。
▶ 図面には、下穴深さとねじ深さを明確に記載しよう
▶ 止まり穴は、タップ加工の難易度が高く、トラブルも多い
▶ どうしても止まり穴設計になる場合は、下穴を4山(4ピッチ程度)深く設計することが重要
▶ 食いつき長さ+切りくず逃げを考慮して、タップ破損を防止
まとめ:ネジ穴はできるだけ「貫通」で設計しよう!
ネジ穴は設計上「止まり穴」にせざるを得ない場合もありますが、
基本は加工性・品質・コストの観点から「貫通形状」が推奨されます。
止まり穴は、
✔ タップが折れやすい
✔ 切りくずが詰まりやすい
✔ 加工コストが上がる
などのリスクを抱えており、
特に深穴や小径ネジではトラブルの原因になりやすいです。
やむを得ず止まり穴とする場合は、
▶ 下穴を深めに設計する
▶ 逃げスペースを確保する
▶ 有効ねじ深さを明記する
などの対策をとりましょう。
まずは、「貫通できないか?」を
常に設計段階で検討する習慣を身につけましょう。
現場に優しい設計は、
結果的に「コストダウン」「納期短縮」「品質向上」につながります。
次にネジ穴を設計する時は、
貫通穴にできないか? ぜひ一度、見直してみてください。














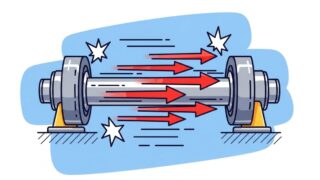
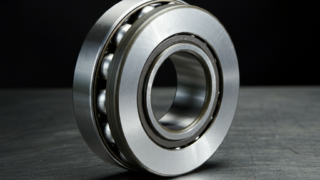










コメント