機械設計でアルミ材料を選ぶとき、
「A5052」「A6061」などの5000番や6000番系がよく使われますが、
より高強度を求める場合には
「2000番代(A2011・A2017・A2024など)」という選択肢もあります。
この記事では、アルミニウム合金2000番代の特徴・代表的な材質
使い分け・設計での注意点について、初心者にもわかりやすくまとめました。
アルミニウム合金2000番代とは?
2000番代のアルミ合金は、銅(Cu)を主添加元素としたアルミ合金で、
「ジュラルミン系」と呼ばれることもあります。
最大の特長は「高強度」で、強度重視の設計で採用されることが多い材料群です。
主な特徴
| 特性項目 | 内容 |
|---|---|
| 強度 | アルミ合金中でも最高レベルの強度を誇る |
| 切削性 | A2011などは非常に良好(機械加工向け) |
| 耐食性 | やや低く、表面処理が必須 |
| 溶接性 | あまり良くない(ひび割れのリスクあり) |
よく使われる2000番代の代表合金と特徴
A2011【切削性特化型】
🔍 用途例
精密ネジ、電子機器部品、コネクタ部品など
A2017【機械構造用の万能ジュラルミン】
🔍 用途例
航空機部品、自転車部品、構造部材、スポーツ用品など

A2017は、軽量で強度もそこそこ欲しい場面に重宝されます。
A2024の廉価版として扱われることもあります。
A2024【高強度・高剛性の代表格】
🔍 用途例
航空機構造材、自動車部品、機械構造部など
設計上の注意点と選定ポイント
強度重視:A2024
SS400に匹敵するような引張強さが必要な場合に有効。
バランス型:A2017
強度・加工性のバランスがよく、機械構造材として扱いやすい。
切削重視:A2011
👉 精密加工部品で大量生産が求められるならこれ一択。
表面処理・溶接に注意
耐食性が低いため、アルマイト処理や塗装が必須です。
溶接性は低く、ひずみや割れが発生しやすいため、
機械的接合(ボルト固定など)が推奨されます。
他のアルミ合金との比較
| 系列 | 主成分 | 強度 | 耐食性 | 溶接性 | 用途の傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000番 | 純アルミ | × | ◎ | ◎ | 装飾・導電用途 |
| 2000番 | 銅 | ◎ | △ | × | 航空・構造・精密部品 |
| 5000番 | Mg | ○ | ◎ | ◎ | 板金・筐体・海洋 |
| 6000番 | Mg+Si | ○ | ○ | ○ | 汎用機械部品・構造材 |
| 7000番 | Zn | ◎(最強) | △ | × | 超高強度部品 |
ジェラルミンの誕生とその歴史 〜軽くて強い夢の金属ができるまで〜
第1章:ドイツの工場から始まった物語(1900年代初頭)
1900年代のドイツ。
産業が大きく発展し、蒸気機関車や飛行船が空を舞っていた時代。
ドイツの金属工場では、
若き技術者アルフレッド・ウィルムが、ある“夢”を追いかけていました。
「鉄のように強く、でもアルミのように軽い金属ができないだろうか…」
当時のアルミニウムは「軽いけど弱い」金属という扱い。
鉄のように構造材として使うには、強度が足りなかったのです。
第2章:偶然が導いた発見(1906年)
1906年、ある日ウィルムは試験の合間に、
銅を加えたアルミニウムのサンプルを数日間放置してしまいます。
すると驚くべきことに…
「ん?数日前よりも、金属が硬くなっている…?」
これは後に「時効硬化(じこうこうか)」と呼ばれる現象。
加熱と自然放置によって、
金属の中で微細な変化が起き、強度が上がるのです。
これこそが、アルミニウム合金の歴史を変える一歩でした。
第3章:ジェラルミンの誕生(1909年)
その後の研究で、ウィルムは
アルミに銅(Cu)・マグネシウム(Mg)・マンガン(Mn)などを加えることで、
理想的な強度を得られる配合を発見します。
そして1909年、ついに世界初の高強度アルミ合金が誕生。
その名も「ジュラルミン」
名前の由来は、
工場のある地名「ジューレン(Düren)」にちなんで付けられたとされています。
第4章:空を飛ぶ材料へと進化(第一次世界大戦〜)
当時の飛行機はまだ木製や布製の機体が主流。
でも重くて遅くて壊れやすい…。
そこで登場したのがこの新素材、ジュラルミンです。
第一次世界大戦の頃には、
ジュラルミン製の飛行機構造材が登場し、
航空技術の発展を大きく支えることになりました。
「強くて軽い」
航空機に最適!ということで世界中で注目されていきます。
第5章:日本にもやってきたジュラルミン
日本では、昭和初期に航空機産業の発展とともに、
ジュラルミンの使用が広がっていきました。
戦後も、自転車部品や精密機械部品など、
軽さと強さが求められる分野で活用され続けます。
現代では、A2017という記号で呼ばれ、
2000番台アルミ合金の代表格となっています。
第6章:ジェラルミンのその後と今
ジュラルミンはその後も改良が進み、
といったさらに高強度なアルミ合金へと進化していきました。
しかし、元祖ジュラルミン(A2017)は、
今でも“ちょうど良い”バランス材として多くのエンジニアに愛されています。
エピローグ:軽くて強い金属の物語は、今も続いている
最初は偶然から始まった発見。
夢を諦めなかった若き技術者ウィルムの情熱が、
現代の機械設計や航空産業、スポーツ機器など、
さまざまな分野の進化を支えています。
ジュラルミンの物語は、
今も私たちの生活の中で続いているのです。
補足:ジュラルミン=A2017
| 名前 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|
| ジュラルミン | A2017相当 | 機械構造材、加工性と強度のバランスが良い |
| 超ジュラルミン | A2024 | 航空機用など、高強度が必要な用途 |
| 超々ジュラルミン | A7075 | アルミ合金中で最強レベルの強度 |
まとめ|2000番代は「強度・加工性」で選ばれるプロ向きアルミ合金
| 材質 | 特長 | 適した使い方 |
|---|---|---|
| A2011 | 切削性最強 | 精密部品・ネジ・コネクタ |
| A2017 | バランス型 | 汎用機械部品・構造材 |
| A2024 | 高強度 | 航空・車両・高応力部品 |
アルミ合金2000番代は、
「軽量かつ強度が欲しい」「精密加工に向いた材質が欲しい」
といった要求に応える材料群です。
選定時は、強度・加工方法・使用環境(防錆対策)を
バランスよく考慮しましょう。
必要に応じて、表面処理の前提や溶接の有無についても
事前に検討しておくと安心です。






















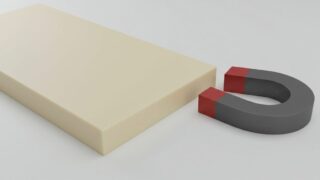

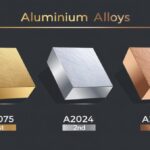
コメント