空圧機器を設計するとき、つい「供給圧力」ばかりを気にしていませんか?
実は、空気の通り道であるエア配管の圧力損失を見落とすと、
シリンダやバルブが想定通りに動作しない原因になります。
この記事では、エア配管の圧力損失の仕組み・原因・対策方法を
初心者にもわかりやすく解説します。
圧力損失を正しく理解すれば、
より安定した空圧システムを設計できるようになります。
エア配管における「圧力損失」とは?
圧力損失とは、空気が配管を流れる途中で生じる圧力の低下のことです。
空気は流れる際に、配管内壁の摩擦や、
エルボ(曲がり)・分岐などでエネルギーを消費します。
その結果、末端の機器(シリンダやノズルなど)に
届く圧力が低下してしまうのです。
簡単に言えば、
「コンプレッサで0.5MPaに設定しても、末端では0.45MPaしか届かない」
というのが圧力損失です。
圧力損失が発生する主な原因
| 原因 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 配管径が細い | 流速が上がり 摩擦が増加 | 配管径を太くする |
| 配管が長い | 摩擦抵抗が蓄積 | 配管ルートを短くする |
| 曲がり・分岐が多い | エルボ・T字継手で 乱流が発生 | 継手を減らし、スムーズな流路に |
| 継手・バルブの抵抗 | 内径が狭い 段差がある | 抵抗の少ない継手を選ぶ |
| フィルタ・レギュレータの目詰まり | 流路が塞がれ 圧力低下 | 定期的な清掃・交換を実施 |
特に、細い配管や長いルートは要注意。
「圧力が足りない」と感じたら、
まず配管径とルートを見直しましょう。
Q&Aで理解する「圧力損失」
Q1. 圧力損失が大きいと何が問題なの?
シリンダの推力やモーターのトルクが低下し、
動作が遅くなったり不安定になります。
特に高速動作や高精度制御が必要な装置では致命的です。
Q2. 配管を太くすれば解決しますか?
ある程度は改善しますが、
太くしすぎるとコストやスペースが増加します。
設計段階で、流量に見合った
適正配管径を選定することが重要です。
Q3. 配管の長さはどのくらいまで大丈夫?
一概には言えませんが、
5mを超える場合は圧力低下を意識したほうがよいです。
途中にバルブや継手が多い場合は、
より短くすることが望ましいです。
Q4. 圧力損失を簡単に確認する方法は?
実際の装置でエア入力側と出力側の圧力を比較すればOKです。
差が大きい場合、配管径やルートに問題がある可能性があります。
圧力損失を簡単に確認する方法とは?
エア配管のトラブルを見抜く現場チェックのコツ
エアシリンダやエアモーターが「遅い」「力が弱い」と感じたとき、
まず疑いたいのが配管内の圧力損失です。
圧力損失は、配管内の摩擦や継手抵抗によって、
コンプレッサーから送られる空気圧が途中で下がってしまう現象。
これを放置すると、装置の動作不良やエネルギーロスの原因になります。
そこでおすすめなのが、
「入力側と出力側の圧力を比較して確認する」
という簡単なチェック方法です。
この記事では、その確認方法と得られるメリットについて、
現場目線でわかりやすく解説します。
圧力損失を簡単に確認する方法
圧力損失の確認は、2か所の圧力を比べるだけでOKです。
【確認手順】
- コンプレッサーから出た直後(入力側)に圧力計を取り付ける
- エアシリンダやエア機器の直前(出力側)にも圧力計を取り付ける
- 装置を通常動作させた状態で、両方の圧力を比較する
もし、
入力側:0.6MPa
出力側:0.5MPa
というように0.1MPa以上の差があれば、
圧力損失が発生していると判断できます。
この差が大きいほど、配管径の不足やルートの悪さ、
フィルタ詰まりなどの問題がある可能性が高いです。
圧力損失を確認するメリット
① トラブル原因をすぐ特定できる
エア装置が正常に動かないとき、
原因が「シリンダ」なのか「配管」なのかを判断するのは意外と難しいもの。
圧力を比較するだけで、
問題がどこにあるかを簡単に切り分けできます。
② 無駄な調整や交換を防げる
圧力損失を把握せずに部品交換を行うと、
「結局直らなかった」という無駄なコストや時間が発生します。
圧力比較を行えば、
根本原因を特定して正しい対策ができるため、
メンテナンス効率が向上します。
③ エア消費と電力コストを削減できる
圧力損失が大きいと、装置に必要な圧力を
得るためにコンプレッサーが余分に稼働します。
つまり、電気代とエア漏れリスクが増えるということです。
圧力差を小さく保つことで、
といった効果が期待できます。
④ 装置の安定動作につながる
圧力損失が安定していない配管では、
シリンダの動作が遅れたり停止したりといった
不具合が発生しやすくなります。
定期的に圧力差を確認することで、
装置の動作安定性を維持できます。
現場で使えるワンポイント
圧力損失の確認は、
「入力側と出力側の圧力を比較する」だけの簡単なチェックで行えます。
この小さな確認を習慣化することで、
といった大きなメリットが得られます。
「圧力計を2つ取り付けるだけ」でトラブルを未然に防げるのです。
空圧設備の保守・設計では、ぜひこの確認を
ルーチン点検の1つとして取り入れてみましょう。
設計者が押さえるべきポイント
- 配管径は「流量」に合わせて決める
- 曲がりは最小限にする
- 継手・バルブの内径を確認する
- フィルタやレギュレータのメンテナンスを怠らない
圧力損失は、エア機器の性能を左右する非常に重要な要素です。
いくら高性能なシリンダを使っても、
配管設計が悪ければ本来の性能を発揮できません。
「圧力が足りない=コンプレッサーのせい」ではなく、
「配管設計の見直し」から。
これが空圧設計における基本の考え方です。
圧力損失が大きいとどうなる?
圧力損失を放置すると、次のようなトラブルが起こります。
空圧設計では、末端機器で必要な圧力(例:0.5MPa)が確保できるよう、
逆算して配管径やコンプレッサ圧力を設定することが重要です。
圧力損失を抑える設計のコツ
- 配管径は「余裕を持って」選ぶ
- 小さすぎる配管はトラブルのもと。
- 少し太めを選定するのが安心です。
- エルボやT字継手を減らす
- 曲がりが増えるほど乱流が発生します。
- ルートをできるだけ直線的に。
- エアフィルタ・レギュレータの定期点検
- 目詰まりや劣化は圧力損失の原因。
- 清掃・交換を忘れずに。
- 末端圧力を実測する
- 計算値だけでなく、実際の圧力を
確認しておくと信頼性が高まります。
- 計算値だけでなく、実際の圧力を
まとめ:圧力損失を意識すれば、空圧はもっと安定する!
エア配管の圧力損失は、
シリンダの動作安定性やエネルギー効率に大きく影響します。
流量や圧力だけでなく、
「空気の通り道の抵抗」も考慮して設計することで、
トラブルのない快適な空圧システムを実現できます。

モーターやアクチュエーターなど、
機械の駆動源に関する基礎知識と
選定基準をまとめています。

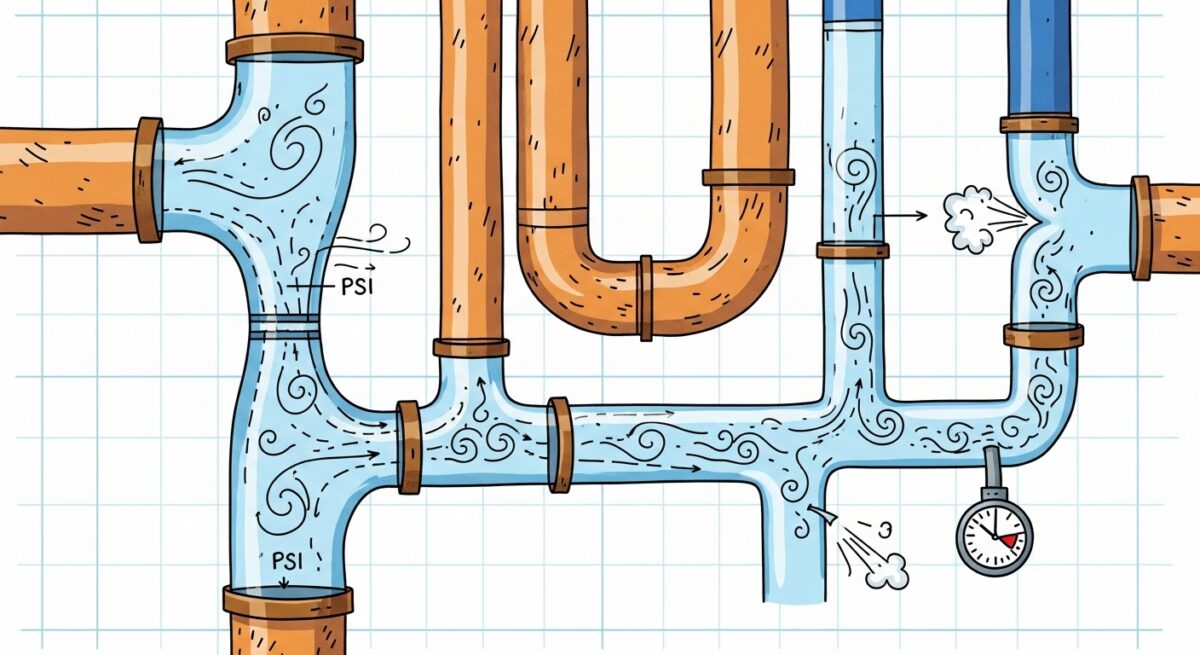
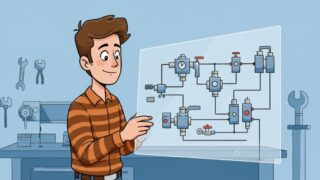



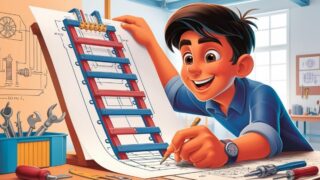
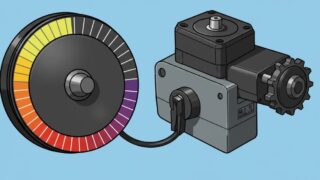

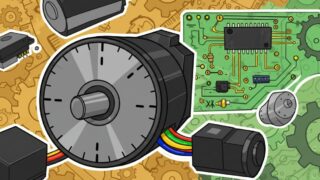

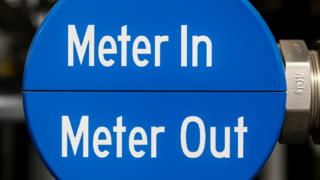



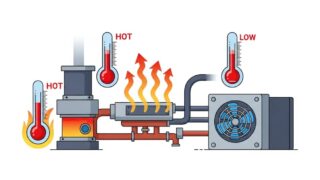



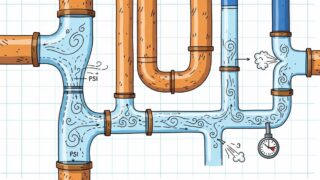
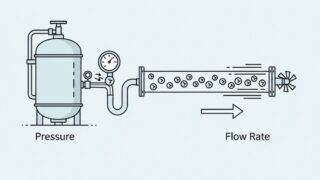

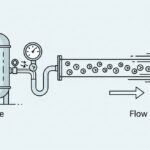

コメント