ローラーチェーンを使った機械で、
「チェーンが外れやすい」「異音がする」「寿命が短い」
といったトラブルに悩んでいませんか?
その原因の多くは、
チェーンのたるみ量(テンション)が適切でないことにあります。
たるみが大きすぎても、小さすぎてもトラブルの原因になります。
この記事では、ローラーチェーンの適正たるみ量の考え方と調整のコツを、
初心者にもわかりやすく解説します。
そもそも「たるみ量」とは?
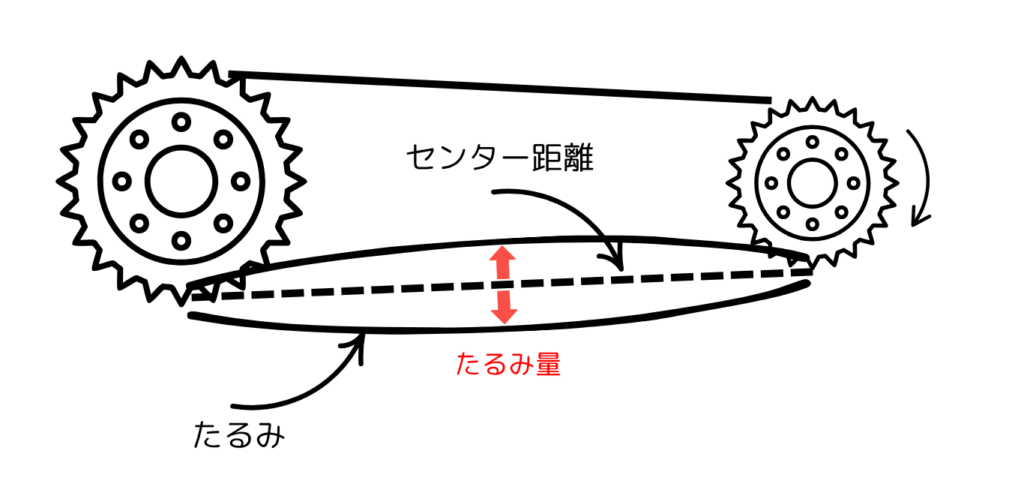
たるみ量とは、チェーンの下側(弛み側)が
どれだけ垂れ下がっているかを表す値です。
一般的には、チェーンの上下のスプロケット間(センタ距離)に対して、
どれくらいの変位があるかで評価します。
たるみ量は、チェーンの動力伝達効率や寿命に直結する重要な要素です。
適正たるみ量の目安
ローラーチェーンのたるみ量は、センタ距離(スプロケット間距離)Lを基準にして決めます。
| 使用条件 | 推奨たるみ量 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般的な水平配置 | センタ距離の 4%程度 | 例:センタ距離 500mm → たるみ 20mm |
| 垂直配置(下向き駆動) | センタ距離の 2%程度 | チェーンが自重で 垂れるため少なめに |
| 高速回転・衝撃負荷が大きい場合 | センタ距離の 2%程度 | 過大なたるみは 振動・脱落の原因になる |
つまり、センタ距離が500mmの装置なら、20mm程度のたるみが適正です。
※実際の値は、使用環境・チェーンサイズ・メーカー推奨値に従ってください。
つばき産業の技術資料「ローラチェーンの配置と据付」では、
ローラーチェーンには “適当なたるみ” を持たせて使用することが
重要であると記されています。
引用:つばき産業:技術資料 ドライブチェーン ローラチェーンの取扱
チェーンのたるみは重要!張りすぎ・緩すぎによるトラブルを防ごう
ローラーチェーンを使う際、
「たるみ量(チェーンのゆるみ)」の管理はとても重要です。
適正なたるみを保つことで、スムーズな動力伝達と長寿命化が実現できます。
しかし、たるみが「多すぎる」または「少なすぎる」と、
思わぬトラブルを引き起こす原因になります。
たるみが不適切な場合に起きるトラブル例
| 状況 | 主なトラブル | 原因 |
|---|---|---|
| たるみすぎ(緩い) | チェーン外れ スプロケットの歯飛び、異音 | テンション不足 チェーン摩耗の促進 |
| 張りすぎ(きつい) | ベアリング破損、 軸の曲がり、チェーン伸び | 初期張力が過大 熱膨張の影響を無視 |
特に注意したいのは「張りすぎ」
一見、「緩むよりは少し張っておいた方が安心」と思いがちですが、
実は“張りすぎ”の方が深刻なダメージを与えることが多いです。
適正なたるみ管理が長寿命のカギ
チェーンのたるみは「緩すぎず、張りすぎず」が鉄則です。
一般的には、チェーンスパンの約 4% 程度が目安とされています。
(例:スパン500mmなら約20mm)
もし運転中に異音や振動を感じたら、
たるみ量が適正かどうかをまず確認しましょう。
定期的にチェーンのたるみを点検し、メーカー推奨値を守ることが大切
「チェーンが緩まないように」と思って強く張ると、
軸受やモーターに過大な負荷がかかり、機械全体の寿命を縮めることになります。

たるみ量が不適切だと、外れや摩耗、軸破損などのトラブルを招く
張りすぎは特に危険!軸受やモーターに負担をかける
定期的にチェーンのたるみを点検し、メーカー推奨値を守ることが大切
ローラーチェーンのたるみ量の測り方|初心者でもできる簡単チェック方法
ローラーチェーンを長く安定して使うためには、
「たるみ量(たわみ量)」の確認が欠かせません。
たるみ量が適正でないと、
チェーン外れやスプロケットの摩耗、ベアリング破損といった
トラブルにつながるからです。
ここでは、初心者でも簡単にできる
たるみ量のチェック方法をわかりやすく紹介します。
測定前の準備
まず、安全のために次の手順を守りましょう。
- 必ず機械を停止する
- 稼働中のチェーンは非常に危険です。
- 必ず電源を切り、安全を確保してから作業を行いましょう。
- たるみ側を確認する
- ローラーチェーンには「張り側」と「たるみ側」があります。
- 駆動中、張力がかかっていない側(ゆるんでいる側)が「たるみ側」です。
測定はたるみ側中央で行うのが基本です。
たるみ量の測り方(手順)
測定はとてもシンプルです。
- チェーンの弛み側中央を軽く指で押す
- 指やスケールなどで軽く押して、上下にどの程度動くかを確認します。
- 上下方向の変位量を測定する
- 押したときの「上方向」と「下方向」それぞれの変位量を足し算します。
この合計の変位量が“たるみ量”です。
測定例
たとえば以下のような場合
- 上方向に押して 5mm 動く
- 下方向に押して 5mm 動く
このときのたるみ量は「10mm」 になります。
つまり、たるみ量は「片側だけの変位」ではなく、
上下両側の合計値で評価するということです。
ひとことアドバイス
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 測定箇所 | たるみ側の中央 |
| 測定方法 | 軽く押して上下変位の合計を測る |
| たるみ量の目安 | 中心距離の2~4%程度 ※条件による |
| 注意点 | 機械停止・安全確認を必ず行う |
たるみ量の測定は、定期点検のたびに実施するのがおすすめです。
たるみが増えてきた場合は、チェーンの伸びや摩耗が進行しているサイン。

早めの張り調整や交換を行うことで、
スプロケットや軸受の寿命を大きく延ばすことができます。
正しい張り方・調整のコツ
① 初期伸びを考慮する
チェーンは使用初期に“なじみ”による初期伸びが発生します。
設計時に調整余裕(スライド機構やテンショナー)を持たせておくと安心です。
② 調整後は軽く回して確認する
張りすぎや偏りを防ぐために、調整後はチェーンを数回転させ、
全体のテンションが均一になっているかを確認しましょう。
③ テンショナーを活用する
振動が多い機械や長時間運転する装置では、
スプリング式テンショナーや自動調整式を導入することで、
常に適正たるみを維持できます。
たるみ・張り調整を考慮した設計のコツ
ローラーチェーンを使った伝達機構は、シンプルで高効率ですが、
「設計段階でのちょっとした工夫」が、
寿命やメンテナンス性を大きく左右します。
特に、チェーンのたるみ量や張力の調整を考慮せずに設計すると、
組立後に「張りすぎて動かない」「緩くて外れる」
といったトラブルが起こることもあります。
ここでは、設計段階で押さえておくべき3つのポイントをわかりやすく解説します。
① センタ距離の調整余裕を確保する
チェーンの中心距離(スプロケット間の距離)は、
実際の組立時や使用中に微妙に変化します。
原因は以下のようなものです。
そのため、固定寸法でガチガチに設計してしまうのはNG。
少しの誤差でも張りが強くなり、ベアリングや軸に大きな負担がかかります。
👉 対策ポイント
これらを設けておくことで、後からたるみ量を微調整できる設計になります。
② チェーン配置はなるべく水平が理想
ローラーチェーンは、重力の影響を受ける部品です。
そのため、垂直や傾斜配置にすると、下側にチェーンがたるみやすくなり、
均一な張力を保ちにくくなります。
👉 対策ポイント
こうした配慮で、チェーンの外れや異音を防止できます。
③ 使用環境(振動・粉塵・温度変化)を考慮する
チェーン伝達部は、周囲の環境の影響を受けやすい部分でもあります。
特に、振動・粉塵・温度変化はたるみ量やテンションに直結します。
👉 対策ポイント
これらの対策によって、長期間安定した駆動と寿命延長が期待できます。
設計者へのアドバイス
| 設計項目 | 対策ポイント |
|---|---|
| センタ距離調整 | 長穴やスライド機構で調整余裕を確保 |
| チェーン配置 | 水平配置が理想。垂直や傾斜の場合はテンションを強めに |
| 使用環境 | 振動・粉塵・温度変化を考慮したテンション設計 |
ローラーチェーンの寿命を延ばす最大のコツは、
「組立後に調整できる設計にしておくこと」です。
設計時に余裕を持たせるだけで、
メンテナンス時の作業性も大きく向上します。
最初から完璧な張りを狙うよりも、調整できる設計を前提に考えるのが、
現場で信頼される機械設計者の鉄則です。
まとめ:適正たるみ量で長寿命・安定運転!
ローラーチェーンの性能を最大限に発揮するには、たるみ量の管理がカギです。
この記事のポイントまとめ
▶ 適正たわみ量はセンタ距離の2〜4%が目安
▶ 張りすぎても緩すぎてもNG
▶ 初期伸びを考慮して調整機構を設ける
▶ テンショナーの活用が効果的
たるみを正しく管理することで、
チェーンの寿命はもちろん、機械全体の信頼性も向上します。

























コメント