製品を設計するとき、
「部品の寸法はすべてピッタリ」だと思っていませんか?
実は、現実の部品は必ず少しずつ“ばらつき”があります。
このばらつきが原因で、思ったように動かない・組み立てできない、
といったトラブルが起きることも。
そこで重要なのが――公差解析(こうさかいせき)です。
公差解析とは?
公差解析とは、部品ごとの寸法誤差(公差)が組み立て時に
どう影響するかを事前にチェックする手法です。
たとえば、複数の部品を組み合わせたときに、
✅ すき間が大きすぎないか?
✅ 動きが渋くならないか?
✅ 組み立てできる範囲に収まるか?
といったことを数値で予測できます。
なぜ必要?現実のモノづくりには誤差がつきもの
~公差解析が必要な理由を事例で学ぼう~
設計した通りに作ったのに、
「組み立てできない」
「動かない」
「すぐ壊れる」──。
そんな経験はありませんか?
実はその原因、部品同士の“寸法誤差”の積み重なりにあるかもしれません。
モノづくりは“理想通り”にはいかない
図面には「直径10.0mm」「長さ50.0mm」など、きれいな数字が並びます。
でも実際に作ってみると、どんなに高精度でも少しだけズレます。
このズレ(ばらつき)を「寸法公差(こうさ)」と呼びます。
よくあるトラブル例とその原因
| 🔧 問題の例 | ⚠️ なぜ起きる? |
|---|---|
| 組み立てが固くて入らない | 各部品の誤差が“悪い方向”に重なった |
| ガタが出てしまう | 想定よりすき間が大きくなった |
| モーターが焼き付いた | 軸と穴のクリアランスが足りず、摩擦が増加 |
図面上ではOKでも、現実ではNGになる理由
部品は1つ1つ少しずつ違います。
それらが連鎖的に影響し合うと、全体の組み合わせ寸法にズレが出るのです。
寸法誤差を事前にチェックする「公差解析」が必要!
公差解析とは、それぞれの部品の寸法公差を組み合わせて、最終的にどの程度ズレが出るかを数値で予測することです。
これにより
といった重要なチェックが事前にできるのです。
設計でやるべきこと
公差解析は“想定外”をなくすための設計技術
「図面どおりに作ったのにうまくいかない」
――それはばらつきを無視した設計かもしれません。
公差解析を行えば、その“ズレ”を見える化でき、
不良や再設計のリスクを大幅に減らすことができます。
初心者こそ、「ズレがある前提」で考えることが、
信頼される設計者への第一歩です。
公差解析でできること
~不良ゼロとムダゼロを両立する設計手法~
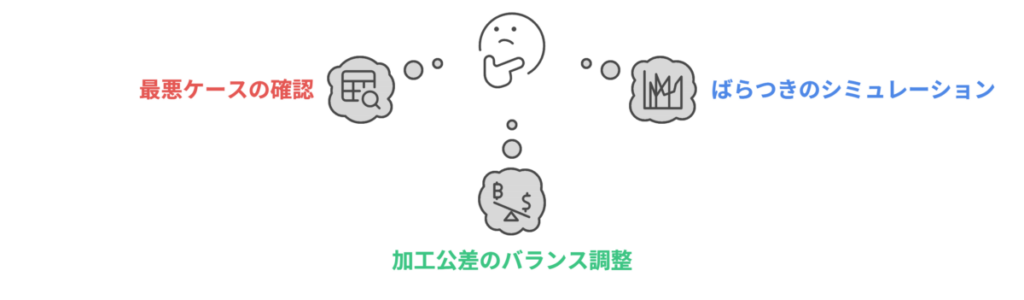
「部品がうまく組み合わない…」
「全部作り直し?コストがかさむ…」
そんなトラブルを未然に防ぐのが公差解析(こうさかいせき)です。
今回は、公差解析で具体的に“何ができるのか”を、
初心者にもわかりやすく紹介します。
最悪ケースの確認(ワーストケース解析)
たとえば、シャフトと穴の組み合わせ。
それぞれが公差の“ギリギリ悪い方向”にズレてしまったら?
入らない・ガタガタになるといった最悪の事態も想定できます。
公差解析では、「最もズレたとき」でも
問題が起きないかを事前にチェックできます。
📌 ポイント
ばらつきの確率をシミュレーション(統計解析)
現実には、すべての部品が最悪方向にズレることはめったにありません。
そこで役立つのが統計的な公差解析です。
例えば…
この設計なら、95%の製品がOK
今の公差だと、不良率が5%出るかも
といったことが、シミュレーションで見えてきます。
📌 ポイント
加工公差のバランス調整(コスト最適化)
精密な加工ほど高コスト。
でも、必要以上に高精度にする必要はありません。
公差解析を使えば…
この部分は ±0.1mm でもOK!
この箇所だけは ±0.01mm が必要!
といった公差のメリハリがつけられます。
📌 ポイント
公差解析は“見えないズレ”を数字で管理する技術
| ✔ できること | 効果 |
|---|---|
| 最悪ケースの検討 | 不良ゼロに近づける |
| 統計シミュレーション | 現実的な合格率を予測 |
| 加工公差の最適化 | コストダウンにつながる |

モノづくりの精度とコストを両立させるために、
公差解析は設計段階でぜひ取り入れたい考え方です。
設計の現場ではどう使う?
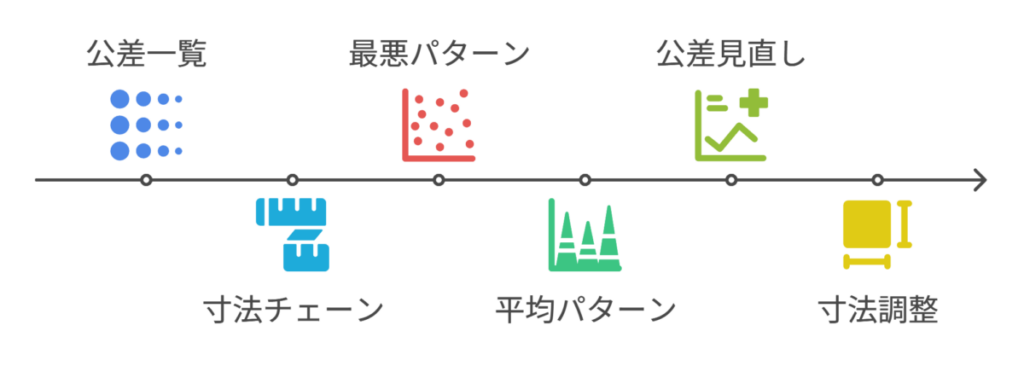
- 組み立てる構成部品の寸法公差を一覧にする
- 寸法チェーンを作って、全体の長さやすき間を計算
- 最悪パターン・平均パターンで解析
- 結果をもとに、公差を見直したり部品寸法を調整する
公差解析は「作ってからの失敗」を防ぐ設計力
~図面だけでは見えない“ばらつき”を事前に読む~
設計者にとって、図面は「理想の世界」を描くものです。
でも、現実のモノづくりでは、
どんなに高精度な加工でも“わずかな誤差(公差)”がつきものです。
その「ばらつき」が原因で…
といった失敗が起きる可能性があります。
そこで役立つのが「公差解析(こうさかいせき)」。
公差解析は、その誤差を事前に読み取って、
問題を未然に防ぐ設計手法です。
公差解析のメリットとは?
不良率の低下
公差解析を行うことで、最悪のケース(ワーストケース)を想定できます。
「一番ズレたときでも組み立てられるか?」を確認できるので、
組立NG、手直し、部品廃棄といったムダな不良品を減らせます。
品質の安定
部品同士の組合せやクリアランスを統計的に検討することで、
「90%以上の製品が問題なく組める」というような品質の“見える化”が可能になります。
結果として、
👉 ユーザーに届ける製品の性能・耐久性が安定し、信頼にもつながります。
加工コストの最適化
「高精度=良い」ではありません。
過剰に厳しい公差は、加工費をムダに上げてしまうことも。
公差解析を使えば、
「この寸法は少しラフでOK」
「ここだけは精密に」など、
公差のバランスを最適化できます。
結果的に、コストを抑えつつ、性能はしっかり確保できます。
設計段階で“失敗を減らす”のがプロの設計力
| 公差解析を使うと | 得られる効果 |
|---|---|
| 組立トラブルが減る | 不良率の低下 |
| 寸法のズレを見積もれる | 品質の安定 |
| 公差を見直せる | 加工コスト削減 |

公差解析は、「作ってからのやり直し」を防ぐ、
まさに“先手を打つ設計”のための武器です。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 公差解析とは? | 寸法のばらつきが製品にどう影響するかを調べる手法 |
| なぜ必要? | 実際の部品には寸法誤差があり、トラブルの原因になるから |
| メリット | 不具合の予防・コストダウン・設計の信頼性向上 |
「図面どおりなのに動かない!」を防ぐために、公差解析は設計に欠かせないステップです。





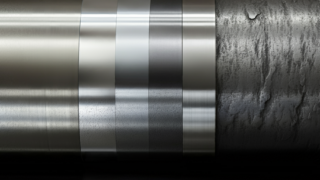


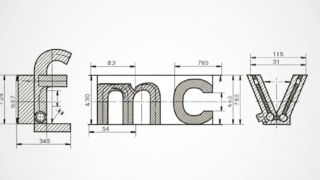







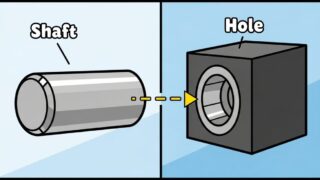






コメント