ねじは最も基本的な締結部品ですが、
「ねじまわりのトラブル」は現場でも設計でも非常に多いです。
この記事では、機械設計や組立現場でよく起こる
以下の5つのトラブルと、その原因・対策を初心者でもわかりやすく解説します。
▶ ねじ山がつぶれてしまった
▶ ねじの頭をなめてしまった
▶ ねじ軸が破断してしまった
▶ ねじが錆びついてしまった
▶ ねじを斜めに締付けてタップが破損してしまった
ねじ・ボルトのトラブルの解明
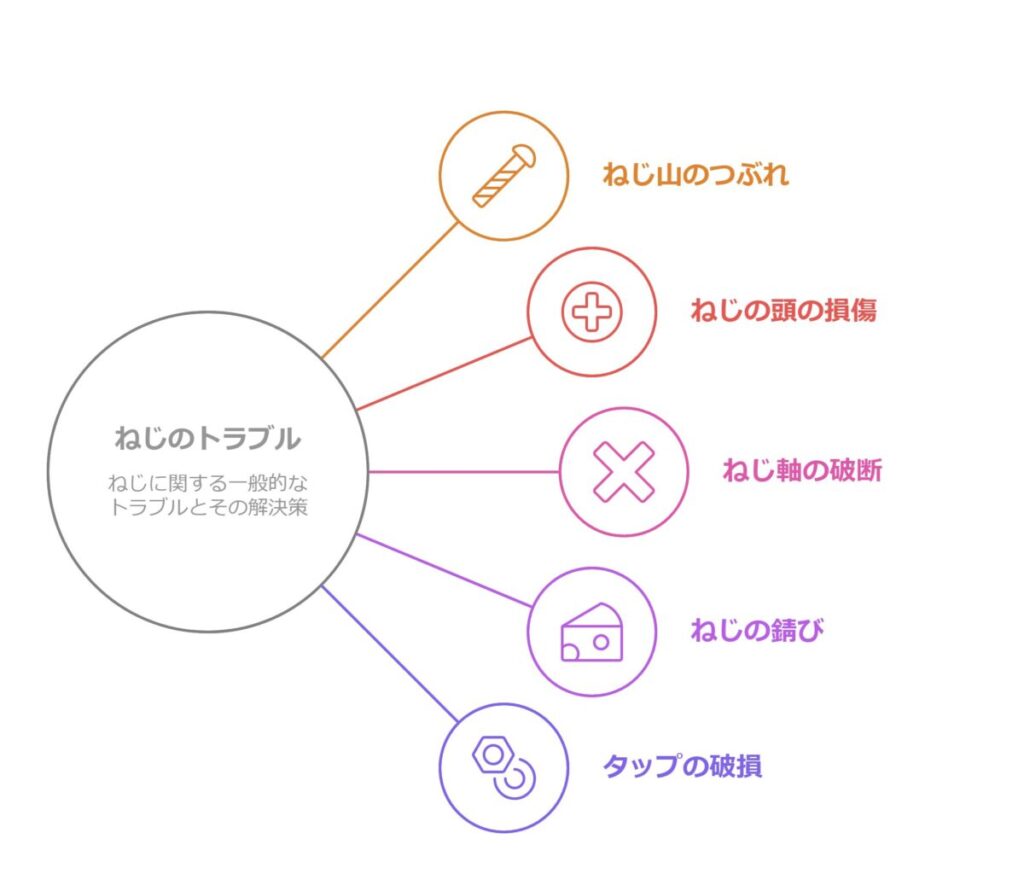
ねじ山がつぶれてしまった
原因
対策
ねじの頭をなめてしまった
原因
対策
ねじの頭をなめてしまった!取り外せないときの対処法まとめ
ねじを外そうとしたら、ドライバーが空回りして
「頭がつるつるになってしまった…」という経験はありませんか?
この状態を「ねじの頭がなめる(潰れる)」といいます。
なめてしまうと通常の方法では外せなくなり、
作業が進まない厄介なトラブルです。

なめてしまったねじの取り外し方を、わかりやすく手順ごとに解説します。
あわせて、再発防止のポイントも紹介します!
ねじの頭がなめたときの基本対処フロー
状況に応じて、次のような方法を順番に試していくのがポイントです。
方法1:ゴムや輪ゴムを噛ませる
【難易度:★☆☆(初心者向け)】
ドライバーとねじの間に輪ゴムや滑り止めシートを挟んで回します。
摩擦が増えることで空回りを防ぎ、意外とこれで外れることもあります。
押し付ける力をしっかりかけながら、垂直にドライバーを当てる。
方法2:プライヤーやモンキーレンチで直接つかんで回す
【難易度:★☆☆】
ねじの頭が出っ張っていれば、プライヤーやモンキーでガッチリつかんで回すのも有効です。
特に六角ボルトや皿ねじ以外のなめたねじに使いやすい方法です。
つかむ位置はねじの根本に近いほど力がかかりやすい。
方法3:ねじすべり止め液(グリップ剤)を使う
【難易度:★☆☆】
市販の「ねじすべり止め液(ねじグリップ)」を使うと、
摩擦が増えてドライバーが食いつきやすくなります。
ドラッグストアやホームセンターで数百円で手に入ります。
方法4:貫通ドライバー+ハンマーでショックを与える
【難易度:★★☆(中級者向け)】
「貫通ドライバー」を使い、
ハンマーで軽く叩きながら回すことで食いつきやサビの固着を緩めます。
注意:強く叩きすぎるとねじが完全に変形する恐れがあるので要注意!
方法5:専用工具「ネジザウルス」を使う
【難易度:★☆☆(初心者OK)】
なめたねじに特化した工具「ネジザウルス(エンジニア製)」は非常に優秀です。
ねじの頭をガッチリつかむ特殊な形状をしており、家庭用でも人気があります。
方法6:エキストラクター(ねじ外し工具)を使う
【難易度:★★☆】
完全になめてしまって頭がつるつるのねじには「エキストラクター(逆タップ)」が有効。
ドリルで下穴を開け、逆ネジの工具で食い込ませながら回して外します。
📌 ポイント:電動ドリルが必要なので、DIYや現場作業に慣れている方向け。
最終手段:ねじ頭を削って外す
【難易度:★★★(上級者向け)】
どうしても外れない場合は、以下のような最終手段もあります。
- サンダーやリューターでねじ頭にマイナス溝を削る
- ドリルでねじ頭を完全に飛ばして、部品を外してから軸を取り除く
この方法は部品を傷つける可能性があるため、破壊覚悟で行う必要があります。
再発防止のポイント
| 原因 | 防止策 |
|---|---|
| 工具が合っていない | ドライバーサイズ・形状を正しく選ぶ(例:プラス2番など) |
| 工具の角度がずれている | まっすぐ押し込みながら垂直に回す |
| サビ・固着 | 潤滑剤(ラスペネ・グリース)を事前に塗布 |
| 安物のねじ | 強度等級付きの信頼性あるねじを選定(10.9ボルトなど) |
| 頭が小さすぎる | トルクが必要な箇所では六角穴付きボルトや六角ボルトを使う |
なめたねじは段階的に対処法を試すことで多くの場合は外せます。
まずは輪ゴムやつかみ工具などの簡単な方法から始めましょう。
専用工具(ネジザウルス、エキストラクター)も頼れる存在です。
トラブルを防ぐには工具・トルク・材質の正しい選定がカギ!
ねじ軸が破断してしまった
原因
対策
ねじが錆びついてしまった
原因
対策
※SUSボルト同士の焼き付き(かじり)には注意
👉 モリブデングリスや専用のかじり防止剤を併用
5. ねじを斜めに締付けてタップが破損してしまった
原因
対策
ねじトラブルは「原因を知って予防」がカギ!
| トラブル | 主な原因 | 主な対策 |
|---|---|---|
| ねじ山つぶれ | 過トルク・異物・材料不足 | トルク管理・ヘリサート・清掃 |
| 頭なめり | 工具不一致・固着 | 正しい工具・潤滑剤・材質選定 |
| 軸破断 | オーバートルク・疲労 | 強度等級選定・振動対策 |
| 錆び | 環境要因・防錆不足 | 防錆ねじ・潤滑剤 |
| タップ破損 | 斜め挿入・下穴ミス | 直角保持・下穴サイズ・油使用 |
ねじのトラブルは小さく見えて、機械全体の信頼性に直結する問題です。

設計段階から対策を意識し、
現場でもしっかりした作業手順を守ることで、
トラブルは大きく減らせます。
まとめ
ねじは機械設計や組立において欠かせない要素ですが、
「ねじ山が潰れた」「頭がなめた」「軸が折れた」
「錆びついた」「タップが破損した」など、
トラブルは意外と身近に潜んでいます。
これらの多くは、使用工具の選定ミス・締付けトルクの管理不足・
潤滑不足・材料の選定ミス・作業姿勢の不備
といった基本的な点から起こるものです。
トラブルの発生を防ぐためには、次のポイントを意識しましょう。
▶ 適切なサイズと種類の工具を使用する
▶ 推奨トルクに従って、必要以上に締めすぎない
▶ ねじの材質や強度等級を確認して選定する
▶ 防錆処理や潤滑処理をあらかじめ行う
▶ ねじ穴は垂直・正確に加工し、締付け時も真っすぐに回す
また、トラブルが起きた場合でも、
段階的な対応方法を知っておくことで冷静に対処できます。
現場や設計の中で「なんとなく」ねじを使わず、
「きちんとした理屈と対策」で扱うことで、
信頼性の高い製品づくりにつながります。

























コメント