機械設計において「部材のたわみ」を抑えることは、
精度・寿命・安全性を確保するうえで非常に重要です。
しかし、板厚を増やすだけの対策では
コストや重量が増え、効率的な設計とは言えません。
実は、たわみ対策で最も効果が高いのは“断面形状の最適化”です。
同じ材料・同じ重量でも、断面を工夫するだけで剛性は数倍に向上します。
本記事では、機械設計者が必ず押さえておきたい
断面形状によるたわみ対策の考え方・効果・実践ポイント
を分かりやすく解説します。
なぜ断面形状が重要なのか(たわみは断面二次モーメントで決まる)
部材のたわみ量は、
材料の硬さ(ヤング率 E) と 断面形状の強さ(断面二次モーメント I) で決まります。
特に重要なのは I(断面二次モーメント) で、これは
“どれだけ曲がりにくい形をしているか” を表す値です。
一言で言うと、、、
断面形状を工夫して I を大きくすると、たわみは一気に小さくなる。
(材料を変えるより効果が大きいことも多い)
さらに簡単に例えると…
- 板を縦向きに持つと強く、横向きに持つと曲がりやすい
→ これは I の差が大きいから
こうした理屈から、たわみ対策では
材料よりも断面形状を最優先で見直す
ことが非常に効果的になります。
板厚を少し増やすより、断面形状を変えるほうが効果が大きい
(例)T字・L字・箱形など
同じ重量でも「形状」によって剛性は大幅に変わる
板を増やすだけでは効率が悪いことも多い。

断面形状の工夫こそが、
軽量 × 高剛性を両立する最強の手法です。
よく使われる断面形状と特徴をわかりやすく解説
たわみ対策の中で最も効果が大きいのが、
断面形状の最適化です。
材料や板厚を変えるよりも、
断面形状を工夫するだけで剛性は数倍に
アップすることも珍しくありません。
ここでは、機械設計でよく使われる代表的な断面形状を、
メリット・デメリット・使いどころを踏まえてわかりやすく紹介します。
① 箱形(角パイプ)―もっとも効率の良い断面形状
🔍 代表例
角パイプ、ハット形状、Cチャンネル など
✅ メリット
💡 ポイント
片持ち梁や長いスパンのフレームなど、
“強度が欲しい構造ではまず箱形を検討すべき” というほど万能。
重量と剛性のバランスが非常に良く、設計で最初に選ばれる断面形状です。
② I形(H形鋼)―縦方向のたわみに圧倒的に強い
🔍 代表例
H形鋼、リブ付き部材の断面など
✅ メリット
💡 ポイント
I形の性能は、“高さ方向に立てたとき” に最大になります。
横倒しにして使ってしまうと性能を発揮できないため、
方向性を意識した設計が必須です。
③ L形(アングル)―軽量だが単体剛性は低い
🔍 代表例
鉄アングル、アルミアングル
✅ メリット
⚠️ デメリット
◆ 用途
- 補助材
- 曲げ方向を意図的に避けたい場面
- “取り付けブラケット”のように他部材と組み合わせて剛性を出す用途
単体で主構造に使うより、
補助的な補強材として使用するのがベターです。
④ リブ追加―薄板構造の剛性を劇的に底上げする
薄板構造の設計で頻繁に用いられる強化方法。
✅ メリット
💡 ポイント
設計では、
「板厚を2mm増やす」より「リブ1本追加する」ほうが圧倒的に効果的。
リブの高さ・向き・位置を工夫することで、
軽量化と高剛性を同時に実現できます。
断面形状を変えるだけで、たわみは劇的に減らせる
断面形状は、たわみ対策において最も効果的な要素です。
| 断面形状 | 特徴 | 推奨用途 |
|---|---|---|
| 箱形(角パイプ) | 高剛性・ねじれに強い・万能 | フレーム、長スパン |
| I形(H形鋼) | 縦方向の曲げに最強 | 梁、架台、大型構造 |
| L形(アングル) | 軽量・安価・補助向け | 補強材、ブラケット |
| リブ追加 | 薄板の剛性アップ、軽量化に最適 | カバー、薄板筐体 |
断面形状を工夫するだけで、
重さを増やさずにたわみを大きく減らすことが可能です。
たわみで悩んでいる箇所があれば、まずは
断面形状の見直し → 材料 → 板厚
の順で検討するのが最も効果的なアプローチです。
断面形状を工夫すると「軽量 × 高剛性」が実現できる理由とは?
最も効率的なたわみ対策を解説
機械設計の現場では、
「もっと強くしたいが、重くしたくない」
という要求が常につきまといます。
実は、この難題を解決する最も効果的な方法が…
断面形状の工夫(断面二次モーメントの改善)です。
板厚を増やすよりも、
断面形状を変えるほうが圧倒的に剛性が上がり、
重量増加も最小限に抑えられます。
以下でその理由と具体例をわかりやすく説明します。
板厚を増やす vs 箱形断面にする(具体例で比較)
例えば、片持ちアームの板厚を 10mm → 12mm にしたとします。
このとき剛性(=断面二次モーメント I)の増加は 約20%程度 に留まります。
一方、同じ重量増加で 箱形断面(角パイプ形状) に変更すると…
剛性が2~3倍になることも珍しくない
これは、板を分厚くするよりも、
材料を外周に離して配置するほうが曲げに強い ためです。
板厚アップは「最終手段」
板厚を増やすと、
といったデメリットが多いのに対し、
剛性アップの効果はそれほど大きくありません。
だからこそ、たわみ対策として板厚アップを選ぶのは…
最終手段にすべきです。
断面形状の改良こそ最も効率的なたわみ対策
断面形状を改善すると、
というメリットがあります。
そのため、「軽くて強い構造」を作りたいなら、
- 板厚より断面形状を優先する
- まず箱形・リブ化を検討する
これが機械設計における定石です。
迷ったら断面形状から見直すのが正解
たわみ対策で最も費用対効果が高いのは、
板厚アップではなく断面形状の改善 です。
「軽くて強い設計をしたい」
「たわみに悩んでいる部材がある」
そんな場合は、まず断面形状の見直しが最も効果的なアプローチです。
たわみを最小にするための断面設計のポイント
- 高さ方向に断面を大きくする
- 断面二次モーメントは高さの3乗に比例。
→高さを増やすのが最も効果が大きい
- 断面二次モーメントは高さの3乗に比例。
- 中空構造を積極的に使う
- 同重量なら中空のほうが圧倒的に剛性が高い。
- リブ追加は“板厚アップ”より効率が良い
- 最小の材料で最大の効果が得られる。
- 曲げの方向を意識して断面を配置する
- I形鋼は向きによって剛性が大きく変わる。
→曲げが大きい方向に強い向きを合わせる
- I形鋼は向きによって剛性が大きく変わる。
- 製造性・コストとのバランスも重要
- 理想形状(箱形・リブ大量)でも、
- 加工が複雑すぎると逆にコストがアップするため注意。
断面形状の最適化は“最も費用対効果が高いたわみ対策”
たわみ対策は「材料選定」「板厚アップ」「補強」など多くありますが、
その中で最も効率的なのが断面形状の見直しです。
設計の初期段階で断面形状を最適化することで、
後から余計な補強をする手間も大幅に減ります。
まとめ:断面形状の工夫で“強い設計”がつくれる
たわみ対策を効率的に行うには、材料や板厚に頼るのではなく、
断面形状を賢く最適化することが最も重要です。
箱形断面・I形断面・リブ追加などを適切に組み合わせれば、
軽量化と高剛性を同時に達成できます。
▶ 断面二次モーメントを増やすのが最優先
板厚アップより断面形状の変更が効く。
▶ 箱形・I型・リブ追加は非常に有効
同じ重量でも剛性は大きく変わる。
▶ 軽量 × 高剛性設計が可能
材料を無駄に増やさず対策できる。
▶ 製造性・コストとのバランスも考える
断面形状の最適化は、機械設計の中でも特に
費用対効果の高い強度・剛性対策です。
たわみで悩んでいる構造がある場合は、
まず断面形状から見直すことで、
より強く・軽く・無駄のない設計を実現できます。
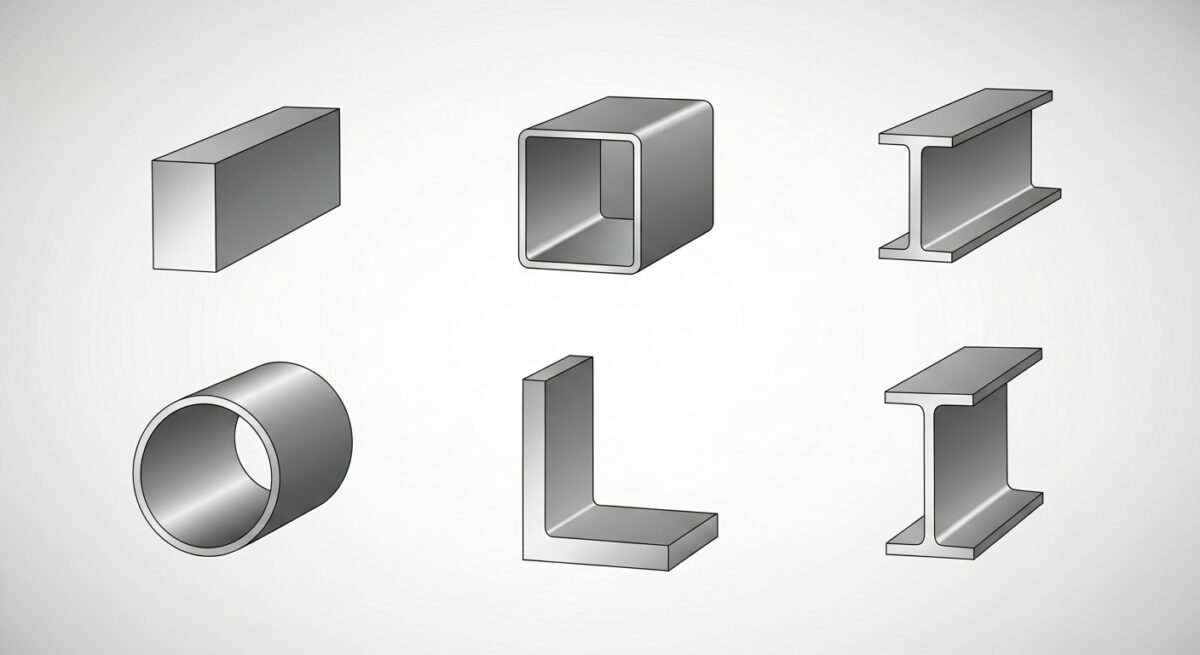
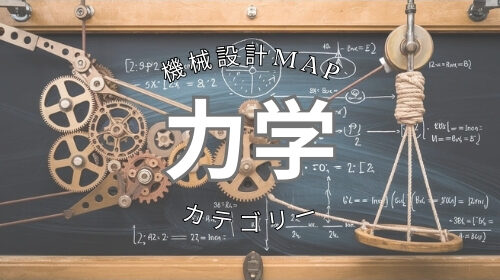


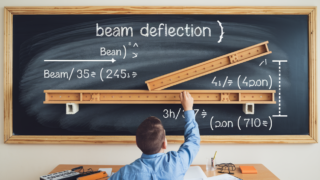

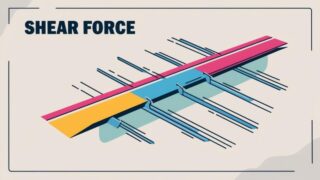





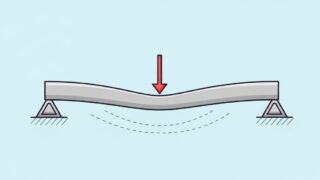

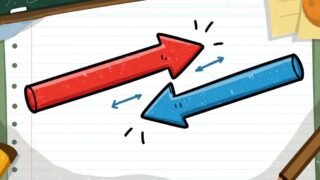

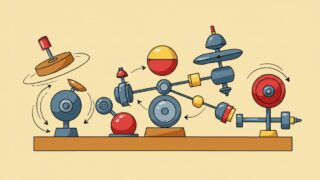
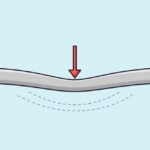

コメント