機械設計では「動力の伝達」や「回転の制御」は
とても重要なテーマです。
中でも、回転方向を直角に変えながら、
大きな減速比を得られる歯車が
「ウォームギヤ(ウォームとウォームホイール)」です。
この記事では、ウォームギヤの基本的な仕組み・
特徴・設計時の注意点・選定ポイントを、
初心者にもわかりやすく解説します。
ウォームギヤとは?
ウォームギヤとは、ネジのような形状の「ウォーム」と、
それにかみ合う「ウォームホイール(歯車)」で構成される、
直角伝達用の歯車機構です。
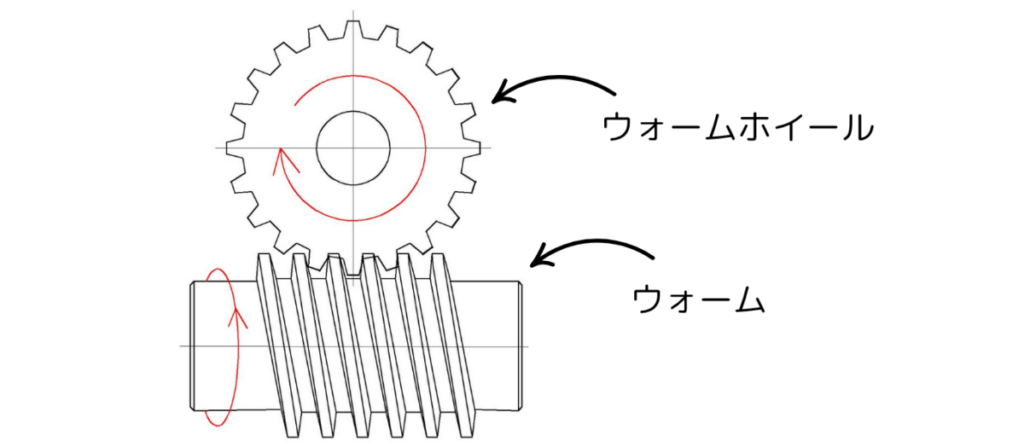
ウォームが回転すると、その力が直角方向にある
ウォームホイールに伝わり、90度方向に回転を伝える仕組みです。
ウォームギヤの主な特徴
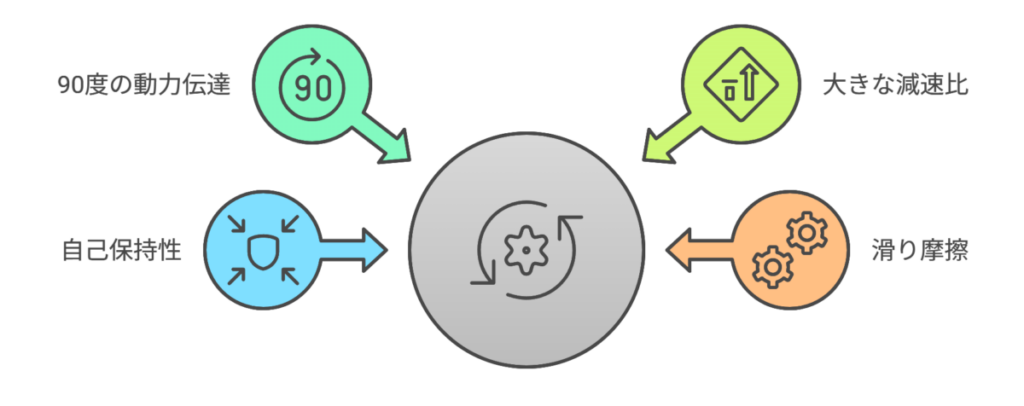
ウォームギヤが持つ4つの主要な特徴について、
具体例とともにわかりやすく見ていきましょう。
特徴1:90度の動力伝達が可能
ウォームギヤ最大の特徴は、
軸の向きを直角(90度)に変えて動力を伝えられることです。
ウォームとウォームホイールは、
軸が直交して組み合わされているため、
モーターなどの回転力を別方向に伝えたいときに非常に便利です。
具体例
このように、省スペース設計が可能であり、
限られたスペースでも効率的に力を伝えられます。
特徴2:大きな減速比が得られる
ウォームギヤは、1段で非常に大きな減速比(20:1や50:1など)を
得られることが大きな強みです。
減速比とは?
「入力に対して出力がどれくらいゆっくり動くか」を示す比率のことです。
たとえば30:1の減速比であれば、ウォームが30回転して、
ウォームホイールがようやく1回転するという意味です。
メリット
活用例
特徴3:自己保持性がある
ウォームギヤには、減速比が高い場合、
自己保持性という特性があります。
自己保持性とは?
出力側(ウォームホイール)に力がかかっても、
逆方向に力が伝わらずウォームが回らないという性質です。
どんなときに便利?
活用例
ただし、すべてのウォームギヤが自己保持するわけではありません。
減速比や摩擦係数によって変わるため、選定時には注意が必要です。
特徴4:滑り摩擦が大きく効率はやや低め
ウォームギヤは「すべり摩擦」によって
動力を伝える仕組みになっているため、
他の歯車(かみ合い摩擦)に比べて摩擦損失が大きいです。
効率の目安
なぜ効率が下がる?
ウォームの回転がホイールに対して「滑る」ように
力を伝えるため、摩擦熱が発生します。
これがエネルギー損失となり、回転効率を低下させます。
設計上のポイント
ウォームギヤは「ゆっくり・強く・確実に動かす」場面に最適
ウォームギヤは、以下のような特徴を持つ、
非常にユニークで便利な歯車機構です。
| 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 90度の動力伝達 | 配置自由度が高く省スペース | 軸配置が固定される |
| 高減速比 | 精密で力強い動き | 効率が落ちやすい |
| 自己保持性 | 安全性が高くブレーキ不要 | 条件によって発揮されない |
| 滑り摩擦 | 静音性あり | 摩耗・発熱への対策が必須 |
ウォームギヤは一見シンプルですが、
設計にあたっては摩擦や材料、潤滑などの配慮が必要です。
減速比や自己保持の有無など、
カタログやメーカー資料をしっかり確認することがポイントです。

ウォームギヤは構造的に「静かでコンパクト」に減速できるため、
住宅設備や静音重視の装置にも向いています。
用途が広く、設計者の工夫次第でさまざまな使い方が可能です。
ウォームギヤの選定ポイント
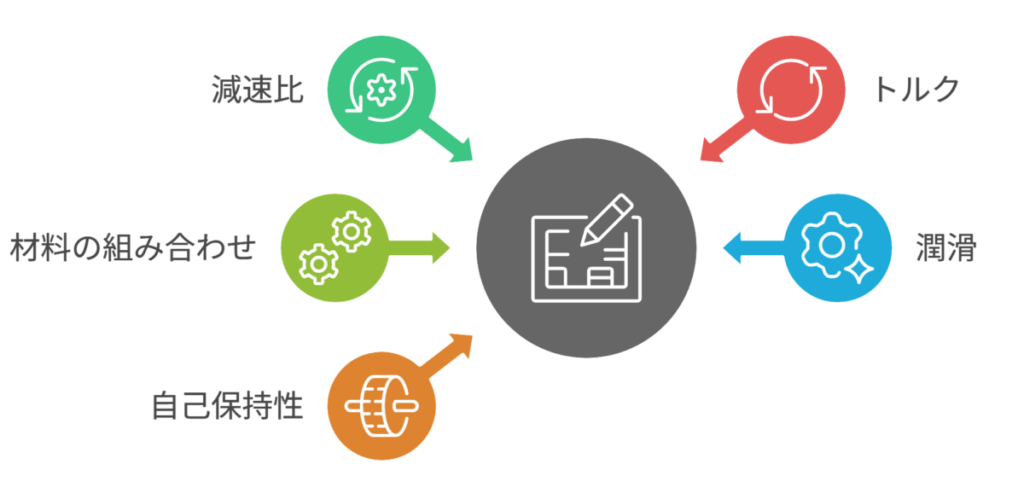
ウォームギヤを選定するときに重要なポイントを以下にまとめます。
減速比(i)
ウォームギヤの減速比は「ウォームホイールの歯数 ÷ ウォームの条数」で決まります。
たとえば…
- ウォーム:1条(1つのねじ山)
- ウォームホイール:30歯
→ 減速比 i = 30 ÷ 1 = 30:1

条数が増えると、1回転で多くの歯が進む
→ 減速比が下がり、回転スピードは速くなる
トルク(伝達できる力)
ウォームギヤは高トルク(力)を得るための装置でもあるため、
出力軸に必要なトルクを事前に計算し、それに合う仕様を選定しましょう。
摩擦損失が大きいため、実効トルクは余裕を持って設計
材料の組み合わせ
ウォームギヤは「すべり接触」のため、異なる材料で組み合わせるのが一般的です。
| ウォーム | ウォームホイール | 理由 |
|---|---|---|
| 鋼 | 青銅 or 真鍮 | 焼付き防止、摩耗軽減 |
同じ金属同士(鉄×鉄など)はNG。
必ず異種金属で。
潤滑・冷却
摩擦熱が発生しやすいため、潤滑は必須です。
連続運転や高負荷の場合は、
冷却ファンやオイル冷却システムが必要な場合もあります。
自己保持性の有無
すべてのウォームギヤが自己保持するわけではありません。
減速比が20:1を超えると、自己保持性が発現しやすいですが、
によって変わるため、カタログやメーカーの技術資料で確認しましょう。
設計時の注意点
効率を過信しない
構造上どうしても滑り摩擦があるため、
エネルギー損失(=発熱)が起きやすく、効率が落ちます。
余裕をもったモーター選定や冷却対策が必要です。
逆転不可の確認
自己保持性がある場合、
外力を加えても回転しないことがあるため、
手動で逆転操作したい場面には不向きな場合もあります。
メンテナンスしやすい構造に
ウォームギヤは潤滑が命。
オイルの交換やグリスアップがしやすい構造を
設計段階で検討しましょう。
まとめ:ウォームギヤの「使いどころ」を理解しよう
ウォームギヤは、
▶ 90度の方向変換
▶ 高減速・高トルク伝達
▶ 自己保持性による安全性
という特徴を活かし、
「遅く、力強く、止める」といった
動作が求められる場面で非常に有効です。
ただし、
➤ 効率が低い
➤ 発熱しやすい
➤ 高速回転には不向き
という短所もあるため、適材適所での活用が重要です。

























コメント