機械設計において「回転軸(シャフト)」は、
モーターやエンジンなどから伝達される動力を、
ギヤ・プーリ・スプロケットなどを介して別の部品へ伝える重要な要素です。
軸は常に回転しながらトルクや荷重を受け続けるため、
適切な軸径を選定しなければ、
ねじれ破壊や曲げによる疲労破壊が起こり、重大な故障に繋がります。
本記事では、初心者でも理解しやすいように、
▶ 動力から軸径を選ぶ方法
▶ 負荷(曲げやせん断力)から軸径を選ぶ方法
を解説します。
さらに、設計上の注意点や実務でよく用いられる考え方も紹介します。
軸径を決めるときの基本的な考え方
軸径を決める際には、主に次の2つの観点があります。

一般的に、
となるため、過不足のない
妥当な径を選定することが重要です。
動力から軸径を求める方法
(1) トルクの計算式
まずは動力と回転数からトルクを求めます。
\( \displaystyle T=\frac{9550×P} {n}\)
- T:トルク [N·m]
- P:動力 [kW]
- n:回転数 [rpm]
例)1.5 kW のモーター、回転数 1500 rpm の場合
\( \displaystyle T=\frac{9550×1.5} {1500}≈9.55N・m\)
補足
実務では「T = 9550 × P / n」のような簡略式がよく使われますが、
より理論的にトルクを求めたい場合は、
\( \displaystyle T=\frac{60P} {2πn}\)
という式もあります。
- T:トルク(N·m)
- P:動力(W)
- N:回転数(rpm)
この式は、出力(P)をワットで、回転数(n)を毎分回転数(rpm)で扱い、
トルク(T)をニュートンメートルで求める物理式です。

単位変換が必要なため少し手間はかかりますが、
仕組みを理解するにはとても役立ちます。
(2) 軸径の算出式(ねじり強度から)
トルクを受ける軸がねじり破壊しないように、次の式で直径を求めます。
\( \displaystyle d=\left(\frac{16T} {πτ}\right)^{1/3}\)
- d:軸径 [mm]
- T:トルク [N·mm](N·mを1000倍)
- τ:許容せん断応力 [N/mm²]
※許容せん断応力は、材料の引張強さの 0.3~0.4 倍程度を使うのが一般的です。
実務ではさらに 安全率を大きめにとって値を落とす ケースが多く、
「疲労」「応力集中」「寸法効果」などを考慮して、
40 N/mm² くらいの 経験的な許容値 を採用することがよくあります。
例えば、S45C で引張強さ 570 N/mm² の場合、
安全率も考慮してτ≈40 N/mm²を採用。
安全率について
機械設計における安全率は
「材料の強さをそのまま使わないで余裕を見込む」ための大事な考え方です。
しかし、その掛け方は 業種・機械の目的・サイズや重量 によって大きく異なります。

安全率は“設計者が決める”
「安全率はケースバイケース」という考え方をまず身につけましょう。
実際の計算例
先ほどのモーターで計算
\( \displaystyle T=9.55N・m=9550N・mm\)
\( \displaystyle d=\left(\frac{16×9550} {π×40}\right)^{1/3}\)
\( \displaystyle d=1215.85^{1/3}≈10.7mm\)
👉 よって、軸径の計算値は10.7m
実務的にはここから安全率2.5を考慮してφ25程度を選定
※「壊れないこと」を優先する場合
(3) 実務上の補正
負荷から軸径を求める方法
(1) 軸には「ねじり」だけでなく「曲げ」もかかる
回転軸には「回す力(トルク)」だけでなく、
プーリやギヤを取り付けることで 横方向の力 もかかります。
例えば…
こうした力によって軸には
曲げモーメント(たわませようとする力のモーメント) が生じます。
つまり軸径を決めるときは、
の両方を見ておく必要があります。
(2) 基本式(曲げ応力の式)
円断面の軸に曲げモーメント M が作用したときの曲げ応力σは次の式で表されます。
\( \displaystyle σ=\frac{32M} {πd^3}\)
- σ:曲げ応力 [N/mm²]
- M:曲げモーメント [N·mm](= 力 [N] × 力の作用点までの距離 [mm])
- d:軸径 [mm]
設計ではこの σ が許容曲げ応力以下になるように d を決めます。
(3) 軸径 d を解く(逆算式)
上式を許容応力 σ を用いて d について解きます。
\( \displaystyle σ=\frac{32M} {πd^3}\)
両辺を入れ替えて整理すると、
\( \displaystyle d^3=\frac{32M} {πσ}\)
したがって、
\( \displaystyle d=\left(\frac{32M} {πσ}\right)^{1/3}\)
これが曲げのみを評価したときの必要最小軸径(理論値)です。
単位に注意してください。
M : N·mm
σ: N/mm²
d : mm
実際の計算例
具体的な数値例で手順を示します。
プーリにかかるベルト張力 F=100N 、
プーリ中心から支持点(軸受)までの距離 L=50 mmの場合
曲げモーメントは…
\( \displaystyle M=F×L=100×50=5000N・mm\)
許容応力は…
\( \displaystyle σ=40N/mm^2\)を採用。
では式に代入していきます。
\( \displaystyle d≈\left(\frac{32×5000} {π×40}\right)^{1/3}\)
\( \displaystyle d≈\left(\frac{160000} {125.66}\right)^{1/3}\)
\( \displaystyle d≈1273.28^{1/3}≈10.84mm\)
よって理論上の必要最小軸径は d≈10.84 mm となります。
(4) 計算結果の扱い方(実務的な注意点)
理論値は「最低」値:上の d は曲げだけを見た理論値です。
実務ではねじり(トルク)や疲労、応力集中、
製造誤差、取付け部(キー溝など)の影響も加味します。
- 標準の丸め
- 計算結果が 10.84 mm なら、標準径に合わせてφ12・φ15など
- 実際には用途に合わせて安全率を考慮して選定する。
- ねじりとの組合せ確認
- ねじりトルクが存在する場合は、
ねじりによるせん断応力と曲げ応力を合成して
評価する必要があります(トレスカの法則など)。
- ねじりトルクが存在する場合は、
- 疲労設計
- 繰返し荷重がある場合、
疲労限度を考慮し許容応力はさらに低くする
(安全率を上げる)ことが必要です。
- 繰返し荷重がある場合、
- 応力集中
- キー溝や段付きなどで応力集中係数が発生します。
- これを掛け合わせて安全側の設計にする必要があります。
(5) 早見的な使い方(設計フロー)
- ベルトやギヤの力(N)と作用点距離(mm)から M を算出。
- 上の式で d を計算。
- 得られた d を規格径に切り上げ(例:10.84 → φ11、実務的には φ12 を選択)。
- ねじり・疲労・応力集中をチェックし、必要ならさらに増径。
ねじりと曲げが同時にかかる場合
実際の軸は「ねじり(トルク)」と「曲げ(横方向の力)」の両方を受けます。
そのため、これらを組み合わせて 相当応力 を計算し、安全かどうかを確認します。
初心者の方は「ねじりだけ見ると細く設計できてしまうが、
曲げを考慮するともっと太くしないといけない」という点を意識すると理解しやすいです。
たわみと振動にも注意
強度的にはOKでも、軸が細すぎると「しなり」や「振動(共振)」が起きます。
特に高速回転軸では
「危険速度(軸の固有振動数と回転数が一致して大きく振動する現象)」を避けるため、
径を太めに設計することが推奨されます。
ポイントまとめ
設計上の注意点
初心者への推奨ステップ
- まずは動力からトルクを計算
→ 軸径の「目安」を得る - 負荷条件(プーリ径、ベルト張力、ギヤの歯面力)を考慮
→ 曲げ応力を評価 - ねじり+曲げの組み合わせで再チェック
→ 相当応力が許容値以下か確認 - 標準部品や安全率を考慮して最終決定
→ 実際の設計に適した径に落とし込む
まとめ
回転軸(シャフト)の軸径選定は、
単に「強そうだから太くする」ではなく、
▶ 動力からトルクを計算して目安を出す
▶ 負荷から曲げモーメントを計算して強度を確認する
▶ ねじりと曲げの組み合わせを考慮する
▶ 安全率・標準規格・疲労強度を踏まえて最終決定する
という流れで行うのが基本です。
初心者のうちは、まず「動力からの目安計算」を行い、
その後「負荷条件を考慮する」ステップを踏むだけでも、
軸径設計の全体像が理解しやすくなります。
実務では安全率を多めに取ることが推奨されますが、
徐々に経験を積んで「どの程度余裕を見ればよいか」を
体感的に掴むことが大切です。
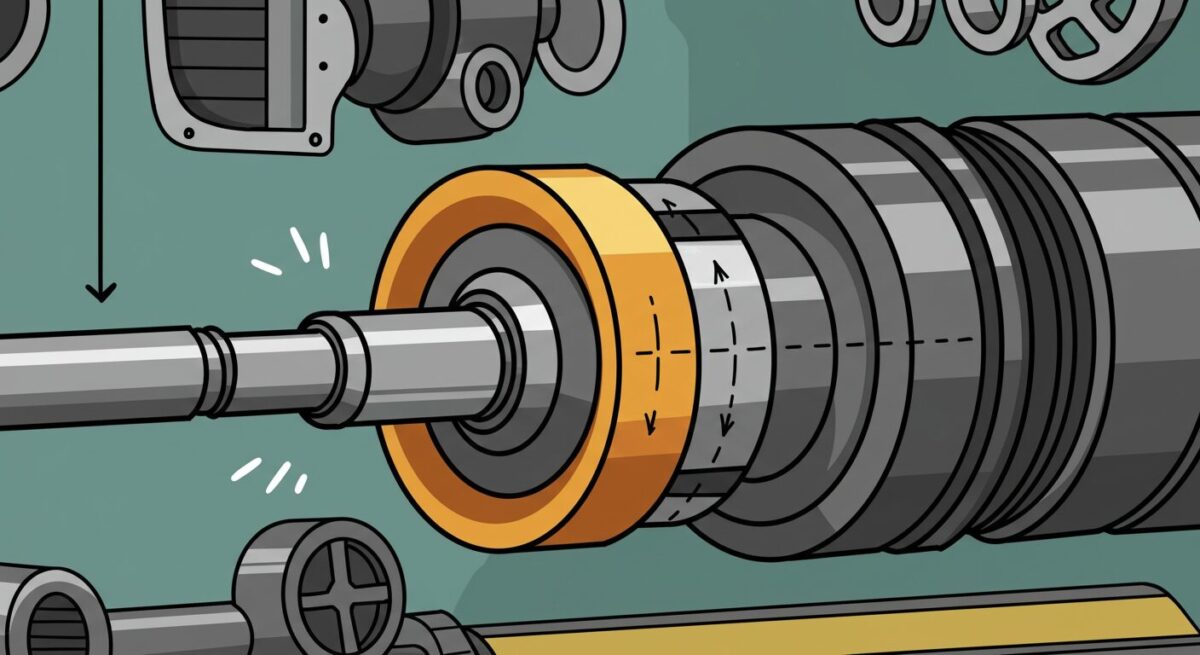

























コメント