金属部品を使っていると、
「熱くなると膨らむ」「冷えると縮む」
という話を耳にすることがありますよね。
でも、なぜ金属は温度によって大きさが変わるのでしょうか?
本記事では、金属が冷えると縮む理由(熱収縮の原理)と、
それが機械設計にどう関わるのかについて、初心者にもわかりやすく解説します。
なぜ金属は冷えると縮むの?
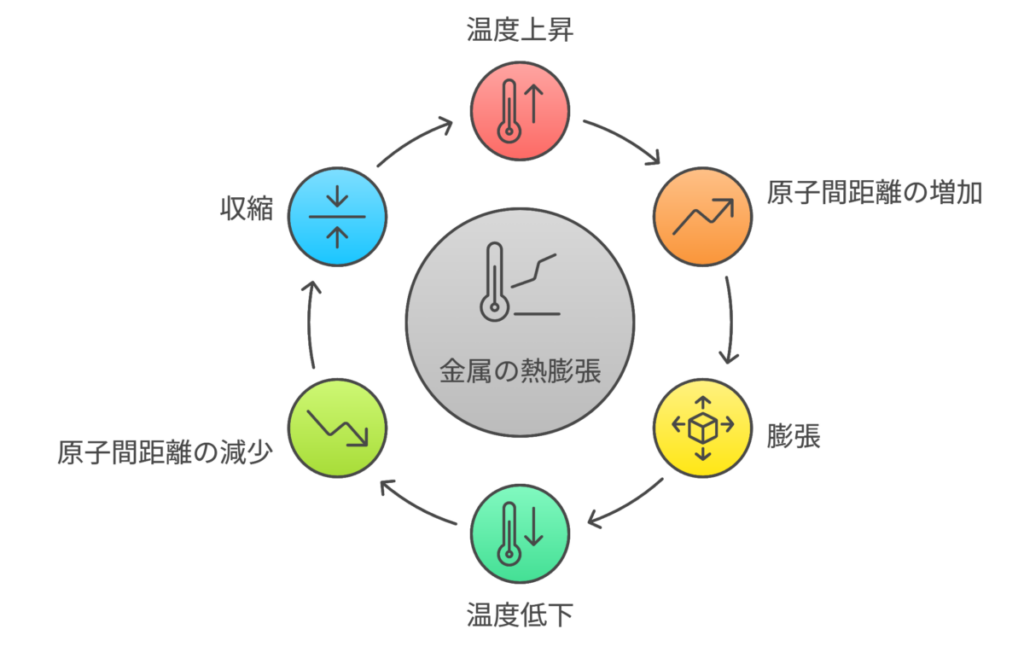
原子の振動が原因!
金属は、原子がたくさん集まってできている材料です。
この原子たちは、温度が上がると激しく振動し、
下がると穏やかに振動するという特徴があります。
つまり、金属が冷える=原子の振動が収まり、
詰まってくる=縮むということです。
この現象を「熱膨張・熱収縮」と呼びます。
原子の振動と膨張の関係とは?
金属はたくさんの原子が整然と並んでできています。
この原子たちは温度が上がると小刻みに振動し始め、
お互いの距離が少しずつ広がる=膨張します。
このとき、
鉄やステンレスなどの線膨張係数が小さい材料は、
アルミなどの線膨張係数が大きい材料は、
どれくらい縮むの?(線膨張係数)
金属ごとに、温度変化による「縮みやすさ」が異なります。
その指標が「線膨張係数(せんぼうちょうけいすう)」です。
そもそも「線膨張係数」ってなに?
線膨張係数とは、
「温度が1℃変わったときに、1mの長さが何ミリ伸びたり縮んだりするか」
を表す数字です。
たとえば、長さ1mの部品が10℃冷えたときにどれくらい縮むか、
以下に一例を示します。
| 材料 | 線膨張係数(×10⁻⁶/℃) | 10℃冷却時の収縮量(1mあたり) |
|---|---|---|
| アルミニウム | 約23 | 約0.23mm |
| 鉄(SS400など) | 約12 | 約0.12mm |
| ステンレス(SUS304) | 約17 | 約0.17mm |
この数字が大きい=温度でたくさん伸び縮みする材料
小さい=あまり伸び縮みしない材料、ということです。

たった10℃の変化でも、
ミリ単位の誤差が出ることに注意が必要です!
設計上、どんなことに気をつけるべき?
金属の熱収縮は、設計や組立に大きな影響を与えることがあります。
ここでは代表的な設計上の注意点を紹介します。
異なる材料を組み合わせるときは注意!
異なる膨張係数を持つ金属を組み合わせると、
温度変化によって“ズレ”や“応力”が発生します。
🔍 例)
アルミフレームに鉄製のブラケットを固定すると、
冷却時に締め付けが緩んだり、逆に歪んだりすることがあります。

設計時に「温度差に強い構造(スライド機構や伸縮逃げ)」を
組み込むのがポイントです。
熱収縮を利用する方法もある!
逆に、「冷やすと縮む」という性質をうまく活用する方法もあります。
🔍 例) 冷却収縮による圧入組立
軸(シャフト)を冷やして縮ませ、穴にスムーズに挿入
常温に戻ると軸が膨張してガッチリ固定される!

工具を使わずに強力な締結ができる「スマートな圧入手法」です。
🔍 例) シャフトとギア(歯車)の圧入組み立てに利用!
たとえば、金属のシャフトにギアを取り付けるとき、こんな方法が使われます。
手順
- ギアを加熱して膨張させる(バーナーや加熱炉などで100〜200℃に)
- 膨張したギアをシャフトにスッと差し込む
- 常温に戻るとギアが収縮して、シャフトをがっちりつかむ!
この方法のメリット
「冷えると縮む」という金属の性質は、
摩擦力を使った強固な接合に活かすことができるんです!
熱で膨らませて入れ、冷えて締まる。
この方法は「焼きばめ」や「熱収縮嵌合」とも呼ばれ、
工作機械など幅広く利用されています。
精密機構では温度管理が超重要!
微細なクリアランスを要求される機構では、
温度による寸法変化がトラブルの原因になることも。
特にベアリングやスライド機構、光学部品などは要注意!

精密機器では「常温設計」だけでなく、
「使用環境の温度条件」も踏まえたクリアランス設定が求められます。
応用:熱収縮はトラブルにもなり得る!
よくあるトラブル例
組立時にはピッタリだったのに、寒い倉庫でガタガタになった
屋外設置の装置が、昼夜の温度差でボルトが緩んだ
高温での運転後、部品が縮んで歪みが発生した
まとめ:冷えると縮む ― 設計者なら押さえておきたい物性の基本!
✔ 金属は原子の振動が小さくなることで縮む=これが熱収縮の正体
✔ 材料ごとに縮み方が違うため、線膨張係数の確認は必須
✔ 異種材料の組合せ・精密部品・圧入などで大きく影響が出る
✔ 設計の中で、「温度と寸法は連動する」ことを常に意識しよう!
温度変化を“敵”にも“味方”にもできるのがプロの設計者。
冷えると縮む――当たり前の現象にこそ、設計の知恵が活きてきます!
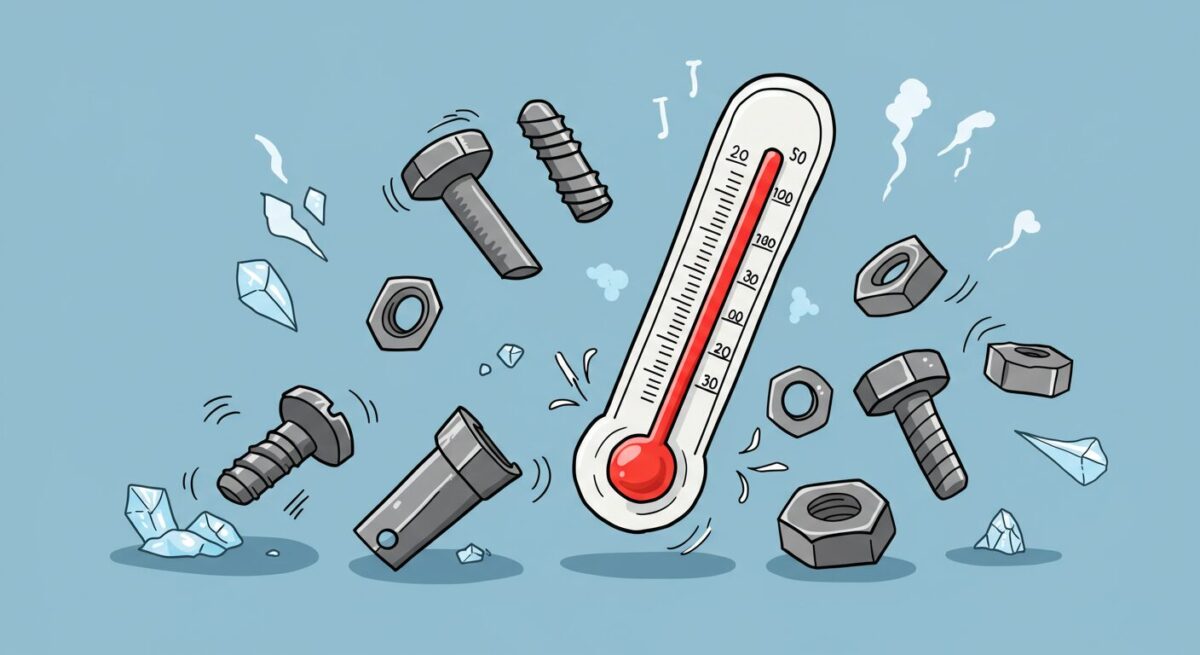
























コメント