機械装置や自動化設備において、
センサーは「今、何が起きているか」を
機械に伝える非常に重要な役割を担っています。
しかし、センサーが発する信号は常に安定しているとは限らず、
「チャタリング」と呼ばれる信号のバタつきが
思わぬトラブルを引き起こすことがあります。
「センサーが反応したのに動かない」
「1つのものを2回カウントしてしまう」など、
現場でよくあるこのような問題は、
チャタリングが原因かもしれません。
この記事では、センサーのチャタリングとは何か?
なぜ起こるのか?どう対策すればよいのか?について、
初心者の方にもわかりやすく解説します。
チャタリングとは?
チャタリングとは、センサーやスイッチが
「オン/オフ」などの状態を切り替える瞬間に、
意図しない微小な信号のバタつき(ノイズ)が発生する現象です。
たとえば、本来は「オン」になるべきタイミングで、
オン→オフ→オン→オフ→オン
というように、ほんの数ミリ秒の間に何度も切り替わることがあります。
この現象がチャタリング(chattering)と呼ばれます。
チャタリングが起こる原因
チャタリングは、センサーやスイッチの
構造的な要因や物理的な衝撃、振動などによって発生します。
以下は主な原因です。
機械的要因
電気的要因
環境要因
どんなセンサーで起こるの?
| センサーの種類 | チャタリングの可能性 |
|---|---|
| 機械式スイッチ(リミットスイッチなど) | 非常に高い |
| 近接センサ | 少ないがあり得る |
| 光電センサ | 対象物の微妙な反射などで起こる場合あり |
| オートスイッチ(有接点タイプ) | 発生する可能性あり |
| オートスイッチ(非接点タイプ) | 基本的に少ない(電子回路処理済み) |
チャタリングが原因で起こるトラブル
チャタリングの対策方法
ハード的対策
ソフト的対策(PLCやマイコン側)
- ON時間のフィルタ処理
- タイマ処理を用いるデバウンス制御
- 一定時間以上変化がないときだけ入力を採用する。
- 複数回の信号一致を確認するロジック
- フリッカ(バタつき)を排除して安定信号に変換。
チャタリング対策の例(実際の現場で)
▶ 現象
ワークがコンベアに流れるたびに、1個が2回カウントされてしまう。
📌 対策
- 使用センサーを高応答・非接点タイプに変更
- PLC側で0.05秒以下の信号は無視するフィルタ処理を実装
👉 誤カウントが解消!
初心者向けワンポイントアドバイス
✅ チャタリング=センサーの“信号のガタつき”と覚えておこう
✅ 初めての設計では、非接点センサー+タイマ処理が安心
✅ トラブル時は「チャタリングかも?」と疑ってみるのが大事!
まとめ
センサーのチャタリングは、信号のバタつきによって設備に
誤作動や誤カウントを引き起こす原因となります。
特に、精度が求められる自動化ラインや、
安全性が重視される装置では、見逃せない問題です。
チャタリングを防ぐには、
▶ センサーの選定(非接点タイプなど)
▶ 取り付け方法の工夫
▶ ソフトウェアでのフィルタ処理
など、ハードとソフトの両面からの対策が重要です。
トラブルが起きたときには、
「もしかしてチャタリングかも?」と視点を変えてみることが、
問題解決の第一歩になります。
正しい理解と対策で、センサーの信頼性を高めましょう。














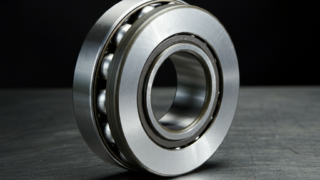
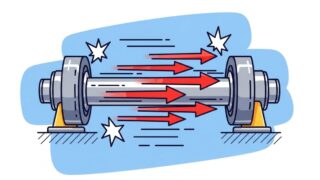










コメント