機械設計において、ねじは部品同士をしっかりと
固定するために欠かせない要素です。
一般的には「右ねじ」が使われていますが、
実は「左ねじ」という特殊なねじも存在します。
ではなぜ、わざわざ“逆向き”のねじを使うのでしょうか?
この記事では、「右ねじ」と「左ねじ」の違いや用途、使い分けの理由、
そして設計上の注意点まで、初心者の方でも理解しやすいように丁寧に解説していきます。
右ねじ・左ねじとは?
ねじには、「右ねじ(右巻き)」と「左ねじ(左巻き)」の2種類があります。
これは、ねじをどちらの方向に回すと締まるかの違いです。
| 種類 | 締まる方向 | 緩む方向 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 🔵 右ねじ | 時計回り(右回し) | 反時計回り(左回し) | 一般的に 最も多く使われている 標準ねじ |
| 🔴 左ねじ | 反時計回り(左回し) | 時計回り(右回し) | 特殊用途向け。 逆回転で緩むのを 防ぐために使用される |
ほとんどの機械やボルトは右ねじですが、
動作によっては左ねじでないと不具合が出る場合もあるため、
正しく理解して使い分けることが大切です。
なぜネジは右回しが基本なの?
人間の「利き手」との関係
まず理由の1つ目は非常にシンプルな生物学的理由があります。
世界の人口の約9割は右利きです。
右手で工具を持ったとき、時計回り(右回し)方向に
力をかける方が自然で力が入りやすいのです。
そのため古くから工具(レンチ・ドライバーなど)は右回し
で締める前提で作られ、ネジそのものも右回しで
締める規格が標準化されていきました。
右ねじの国際標準化
現在、国際的な工業規格(ISO規格)でも
「ネジの標準回転方向は右ねじ」が採用されています。
どちらの規格書でも特別な用途を除き、
ネジの締結方向は右回しが基本と明記されています。
要するに「右ねじが世界共通のデファクトスタンダード」なのです。
機械の回転方向との親和性
もうひとつの理由は、回転運動との相性です。
多くのモーターや回転軸は時計回りが正方向として設計されているため、
右ねじが自然に「締まる」方向になります。
もし逆方向にした場合、
回転によってネジが緩んでしまうリスクがあるため、
右回しが基本になっています。
左ねじが使われる場面とは?
左ねじは特殊な用途ですが、「右回転で緩む」問題を防ぎたいときに活躍します。
よくある使用例
回転体の逆回転による緩みを防ぎたいとき
🔍例)
高速回転でねじが緩みやすい構造
- 回転体に使われるシャフトナットやフライホイールなど
- モーター軸の端部など
ロッドエンド(リンク機構など)の長さ調整
🔍例)
→ 左右のロッドエンドを使う場合、
片側を左ねじにすることで長さ調整を容易にしつつ、
機構の動作中に逆方向のねじ緩みを防止できます。
たとえば、ターンバックル式の調整ロッドでは、両端を「右ねじ・左ねじ」で構成することで、
中央部を回すだけでロッドの長さを微調整でき、ねじを外さずに調整が可能になります。
左ねじは、「回転方向による緩み防止」と「調整機構の効率化」の両方を目的に使われます。
左ねじは逆回転による“ゆるみ”を防ぐために使う!
なぜねじは“緩む”のか?
回転体(モーター、シャフト、ホイールなど)に取り付けたねじやボルトは、
その回転方向によって自ら緩んでしまうことがあります。
🔍たとえば・・・

これは機械が振動や負荷を受けながら回転していると、
少しずつ“戻される力”が働くためです。
左ねじを使うことで緩みを防ぐ!
こうした逆回転による緩みを防ぐために、
「回転方向に逆らう締まり方をするねじ」
つまり 左ねじ(逆ねじ) が使われます。
🔍 例:左回転の部品には左ねじを使う!
これにより、回転によってねじが締まる方向に力がかかる
緩みのリスクが大幅に低減!
設計での注意点
左ねじは非常に便利ですが、使う際には以下の点に注意が必要です。
▶ 図面への明確な記載
▶ 加工工具(タップ、ダイス)は左ねじ用が必要
▶ 組立時の回転方向も注意
逆回転する部品には左ねじで“緩み止め”!
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 緩みの原因 | 回転方向とねじの締め方向が逆だと、ねじが緩む力がかかる |
| 左ねじの利点 | 逆回転でも締まる方向に力がかかり、緩みにくい |
| 注意点 | 工具や図面指示、組立方法を間違えないことが重要 |
左ねじは特殊ではありますが、「緩みを防止する強力な設計手段」のひとつです。

回転方向に応じて正しく使い分けましょう!
回転部品の止めねじは締り勝手で設計するのが基本!
機械設計において、回転軸に取り付けられる
部品の脱落防止や位置決めに「止めねじ」を使うことはよくあります。
このとき重要なのが、「ねじの締り勝手(回す向き)」を考慮した設計です。
📌 「締り勝手って何?」
👉 簡単に言えば、「右ねじか左ねじか」のこと。
通常は右ねじが使われますが、
回転方向によっては左ねじを使うべき場合があります。
なぜ締り勝手が重要なのか?
例えば、回転軸が右回転(時計回り)する場合、止めねじも右ねじだと、
軸と一緒に緩んでしまう可能性があります。
その結果、止めねじが外れて部品が脱落したり、
位置ズレが起きてしまうのです。
このようなトラブルを防ぐために、「締り勝手で設計する」ことが基本です。
回転部品の止めねじの緩み防止には締り勝手を考えよう!
止めねじは、ただ取り付ければいいわけではなく、
回転方向と締付方向が一致すると緩みの原因になります。
そのため、回転方向に対して
逆方向に締まるように設計する(=締り勝手を考慮する)ことが、
機械設計では基本中の基本です。

ちょっとした配慮が、大きなトラブルを防ぐ設計になります!
右ねじ・左ねじの見分け方
現物のねじを見ると、ねじ山の傾きで判別できます。
また、ねじの頭部や軸に「LH(Left Hand)」と
刻印されている場合は、左ねじであることを意味します。
左ねじを使う際の注意点
🔸 部品の誤組付け防止が必要
🔸 左ねじは市販品が少ない
🔸 規格や寸法に注意
左ねじを使うなら、タップ加工も左ねじ用で!
左ねじを使うときの「落とし穴」
左ねじを採用したとしても、「タップ加工」(ねじ穴の加工)が
右ねじのままだと、当然ながらねじが締まりません!
これは初心者が最も見落としやすいポイントの一つです。
タップ加工にも「左ねじ用タップ」がある
通常のタップは右ねじを切るための工具です。
左ねじを切りたい場合には、左ねじ用のタップ(左ねじタップ)が必要になります。
| タップの種類 | 加工できるねじの種類 | 締まる方向 |
|---|---|---|
| 右ねじタップ | 右ねじ(標準) | 時計回りで締まる |
| 左ねじタップ | 左ねじ(特殊) | 反時計回りで締まる |
実務での注意ポイント
加工現場との情報共有が重要!
工具の在庫確認を忘れずに!
タップ加工後の検査も慎重に!
左ねじを使うなら「ねじ穴」も左ねじ!
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 左ねじ使用時の注意 | 右ねじタップでは加工できない |
| 必要な対応 | 左ねじタップを使う / 図面に明記する |
| よくあるミス | タップ加工が右ねじになっていて、組立時に入らない |
左ねじは使いどころが限られる分、間違いが起きやすいポイントでもあります。

図面指示と加工工程の両方で、
「これは左ねじである」ということを
しっかり伝える・確認することが大切です!
まとめ
右ねじと左ねじは、一見するとただの“回す方向の違い”に見えますが、
用途や設計上の目的によって明確に使い分ける必要があります。
特に左ねじは、逆回転による緩みを防ぎたい場面で有効に活用され、
信頼性の高い締結を実現するための重要な選択肢です。
設計時には、「回転方向」や「締結の安全性」、
「加工や組立の可否」などを考慮し、ねじの種類を選定しましょう。
適切なねじの選定が、製品の耐久性と安全性を大きく左右します。
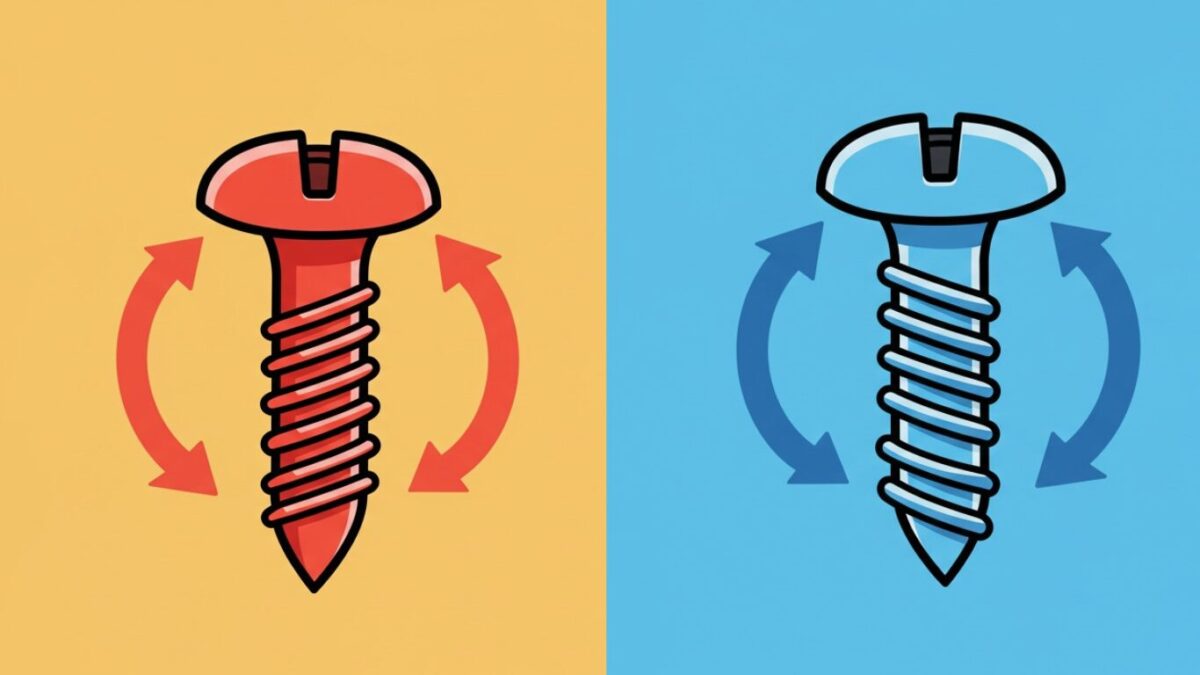












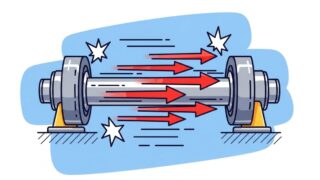
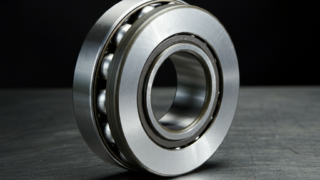










コメント