機械設計では、材料の強度や耐久性だけでなく、
「磁石にくっつくかどうか」も重要な判断基準になることがあります。
特に、センサー機器や電磁波を扱う装置、
あるいは医療機器などでは、
磁力の影響を受けにくい“非磁性材料”の選定が不可欠です。
「ステンレスなら磁石にくっつかないんでしょ?」と
思われがちですが、実はそう単純ではありません。
材料ごとの磁性の違いや、加工による変化、
使用環境に応じた注意点を理解しておくことが、
信頼性の高い設計につながります。
この記事では、非磁性材料の基本的な考え方から、
代表的な材質、設計時の注意点までをやさしく解説していきます。
そもそも「非磁性材料」とは?
非磁性材料とは、磁石にくっつかない材料のことです。
つまり、磁力の影響を受けない(または非常に少ない)材料のことで、
下記のような場面で使われます。
なぜ非磁性材料を選ぶのか?
設計上、「磁力の干渉を避ける」ことが求められる場合があります。
🔍 たとえば…
磁気センサーの精度に悪影響が出る
磁場を乱して誤作動を起こす
強い磁石に引き寄せられて事故につながる
といったリスクがあるためです。
主な非磁性材料の種類と特徴
| 材料名 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| SUS304 | 非磁性、高耐食性 | 食品機械、医療機器、電子機器 |
| アルミニウム | 非磁性、軽量、熱伝導性◎ | 放熱部品、構造部材 |
| チタン | 非磁性、高強度、耐食性 | 航空機部品、医療インプラント |
| 銅・真鍮 | 非磁性、導電性・加工性良好 | 電気部品、接点部品 |
| プラスチック | 非磁性、絶縁、軽量 | カバー類、非接触部品 |
一部のオーステナイト系ステンレスは
加工応力で弱い磁性を帯びる場合があるため注意が必要です。
非磁性が必要な場合は「非金属材料を使う」という手もある!
~金属じゃなくても十分使える設計材料とは?~
機械設計において、「磁石にくっつかない=非磁性」が
求められる場面は意外と多くあります。
たとえば、
磁気センサーの近くで誤動作を防ぎたいとき
MRIなど強い磁場のある装置の周辺で使うとき
微細な金属粉が磁気を帯びてトラブルを起こすのを避けたいとき
こうした場面では金属の磁性がトラブルの原因になることも。
そのため、「金属を使わずに、そもそも磁性のない材料を使う」
という選択肢がとても有効になります。
非磁性なら「非金属」も検討してみよう!
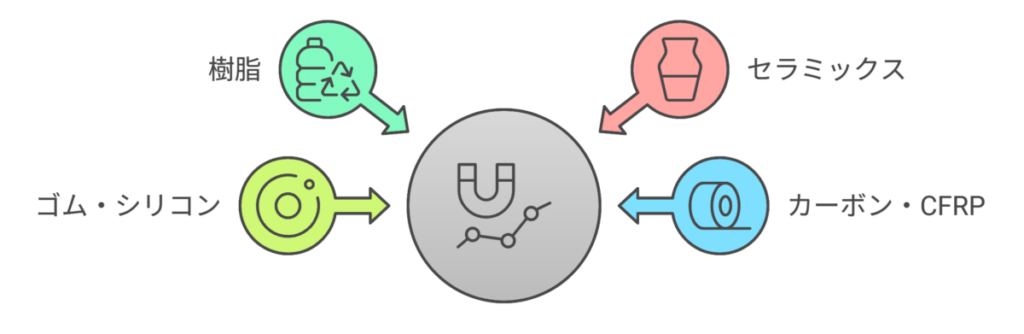
金属は多くが磁石に反応する性質を持っていますが、
非金属材料は基本的に磁石にくっつきません。
非金属材料の代表例
| 材料名 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 樹脂(エンプラなど) | 軽量・加工性良好・絶縁性あり | カバー、ギア、スライド部品 |
| セラミックス | 高硬度・耐摩耗・耐熱性 | 絶縁部品、高温部品 |
| ゴム・シリコン | 柔軟性・密封性 | パッキン、吸振材 |
| カーボン・CFRP | 軽量・高剛性 | ロボットアーム、治具、構造材 |
これらの材料は磁石にまったく反応しない非磁性材料であり、
用途によっては金属以上のメリットを発揮します。
金属より優れる面もある!
非金属は「金属より弱い」というイメージがありますが、
以下のように設計用途によっては金属より有利な点もあります。
軽い!
絶縁性がある!
腐食しない!
磁石に反応しない!
どんなときに非金属材料を選ぶ?
以下のような条件に当てはまる場合は、非金属の活用を検討する価値ありです。
特にエンジニアリングプラスチック(エンプラ)などは、強度も高く、
金属部品の代わりになるほどの性能を持つため、非磁性+実用性の両立が可能です。
設計の選択肢を広げよう!
磁性の有無だけでなく、重量、耐食性、絶縁性など、
非金属材料には多くのメリットがあります。

「金属じゃなきゃだめ」と思い込まずに、
非磁性が必要なときは非金属という選択肢を視野に入れることが、
よりよい設計につながります。
非磁性が必要なら「非金属」が有力な選択肢!
「非磁性=非金属もOK」という視点を持てば、
設計の自由度はぐっと広がります。
設計の初期段階から材料選定を意識することで、
より合理的でトラブルの少ない製品づくりが可能になりますよ。
非金属材料についての記事はこちら
非磁性材料の選定時の注意点
「ステンレスだから非磁性」とは限らない!
磁性が絶対NGの場合は、事前に実物で磁性チェックが必要!
磁性だけに注目しすぎない!
非磁性材料を選ぶときは、他の特性(強度・耐熱性・加工性・コスト)も重要です。
たとえば…

使用環境・負荷条件に応じた総合的な判断が必要です。
材料の組み合わせに注意!
装置内で磁性体と非磁性体を混在させると、
などのトラブルの原因になります。
まとめ
非磁性材料は、安全性や誤作動防止のために重要な要素です。
選定のポイントは…
✔ 磁性の有無だけでなく、強度や耐久性も含めて総合判断
✔ 「非磁性ステンレス」と思い込まず、加工後の磁性も確認
✔ 材料の性質を活かして、用途に応じて正しく使い分ける
非磁性材料は、ただ「磁石にくっつかない」だけではなく、
装置の安全性や性能を左右する重要な要素です。
ステンレスでも磁性を帯びるものがあったり、
非金属材料にも選択肢があるなど、
思っている以上に奥が深い分野です。
材料選定では、磁性の有無に加えて、
強度・耐食性・加工性・コストといった複数の視点から
バランスよく検討することが大切です。
用途に応じて最適な材料を選ぶことで、
誤作動の防止やトラブル回避につながる、
より安心できる機械設計が実現できます。
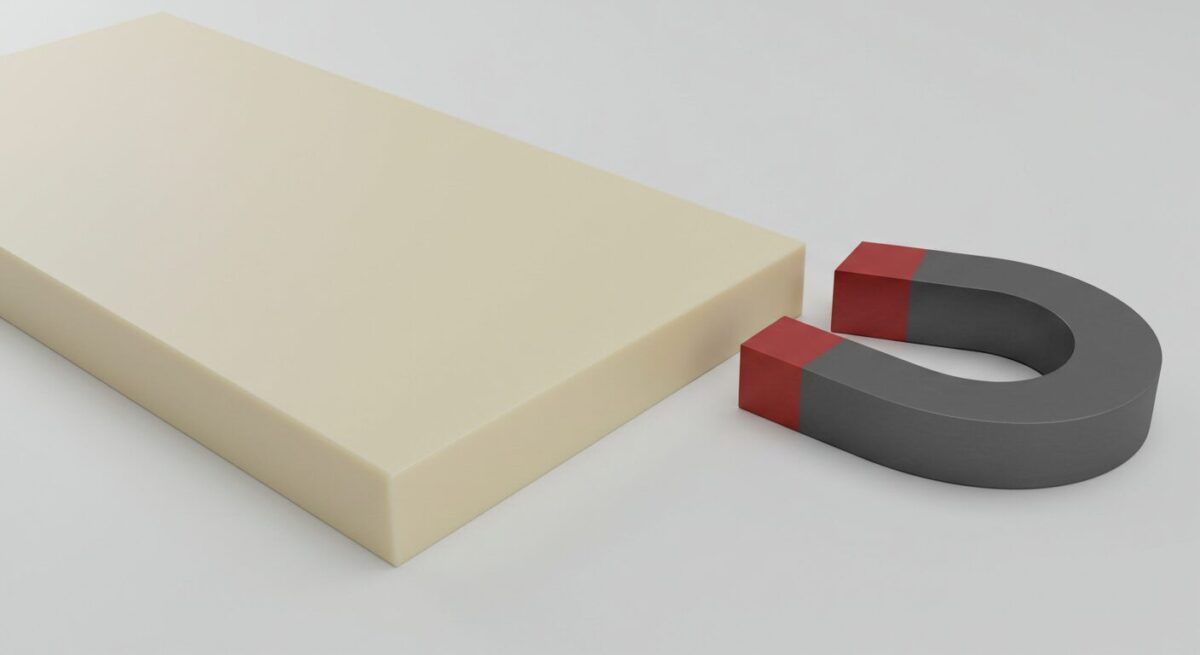























コメント