電動ドライバー、洗濯機、エアコン、電車、EV(電気自動車)――
現代の暮らしや産業のあらゆる場面で使われている「モーター」。
このモーターは、なぜ電気で動くのでしょうか?
なぜ「電気」を流すと「回転」するのか、
不思議に思ったことはありませんか?
この記事では、初心者の方でも理解できるように、
モーターが動く原理=電磁誘導や電流と磁界の関係、
そしてモーターの電力源について、やさしく丁寧に解説します。
モーターとは何をする機械?
まず最初に、モーターの役割を一言でいうと、
「電気エネルギーを回転運動に変える機械」です。
モーターは、内部にある「回転子(ローター)」をグルグル回すことで、
その動力をギアやベルト、シャフトを通して、
さまざまな機械の動力源として使っています。
電気を流すと、なぜ回るの?
モーターが電気で動く秘密は、
「電磁誘導(でんじゆうどう)」と「フレミングの左手の法則」にあります。
ちょっと理科の授業のようですが、わかりやすく説明します!
磁石と電流が作り出す「力」
モーターの中では、次の3つが関係しています。
この「磁界 × 電流 → 力が発生する」という仕組みが、
モーターが回転するメカニズムの核心です。
これを図にすると、以下のようなイメージになります。
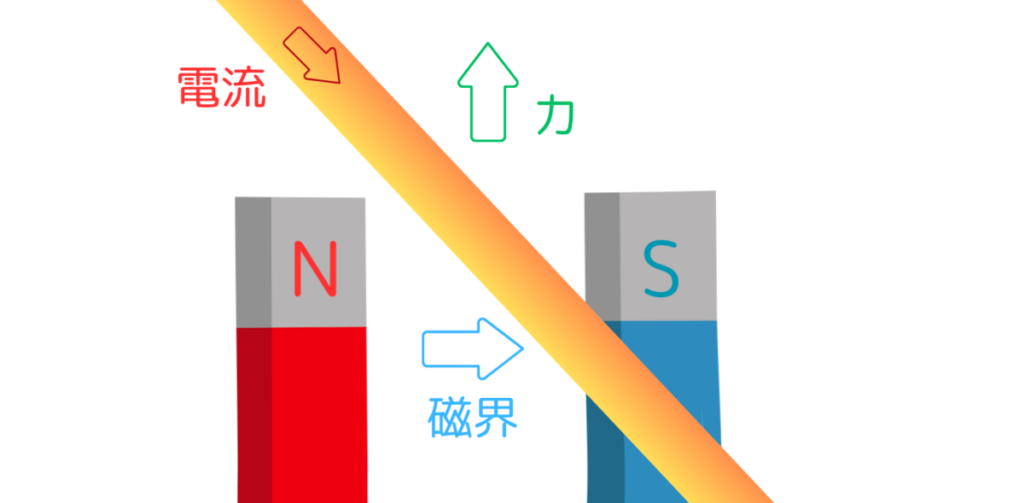
これは「電磁力」と呼ばれる現象で、モーターの基本原理です。
フレミングの左手の法則
「電磁力」がどの方向に働くかは、
「フレミングの左手の法則」で決まります。
左手の指を以下のように使います。
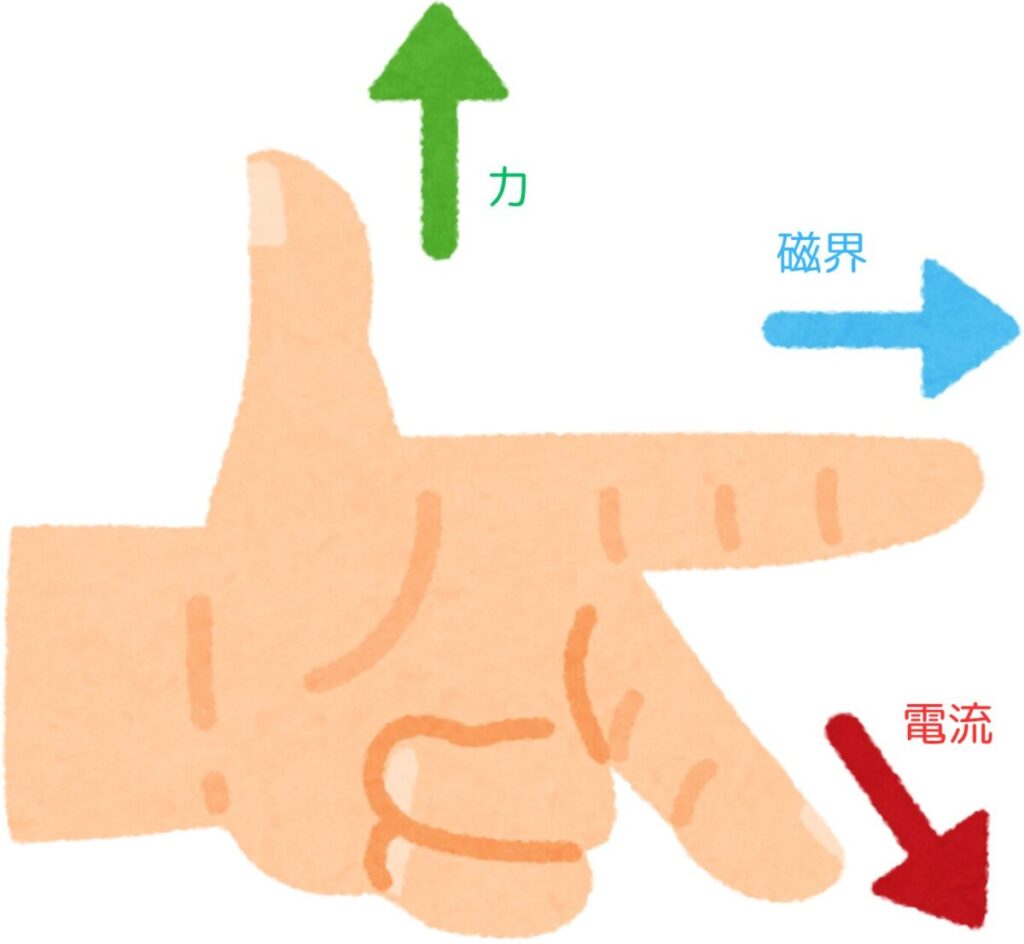
この3本の指を直角に広げると、
磁界と電流の方向が決まれば、動く方向(力の向き)がわかるという仕組みです。
つまり、モーターの中では、
「電流を流したコイルが磁石の磁界の中で力を受けて動く(回転する)」
というわけです。
コイルを回転させる仕組み
モーターの中には、次のような構造があります。
このコイルに電流を流すことで、
上記のように電磁力が発生し、回転子が回り始めるのです。
さらに回転を続けさせるために、
- 電流の向きを交互に切り替える(整流)
- コイルを複数用意して回転の連続性を保つ
といった工夫がされています。
こうした構造によって、
モーターはスムーズに回転を続けられるのです。
モーターの電力源とは?
モーターは電気で動くといっても、
その電気をどこから得るのかも重要なポイントです。
使用環境やモーターの種類によって、
主に以下のような電力源があります。
① 商用電源(家庭用コンセントなど)
- AC100VやAC200V(日本の家庭や工場の電源)
- 主にACモーター(交流モーター)に使われる
- 工場設備、家電、大型機器に広く利用
② バッテリー(直流電源)
- DC12V、DC24Vなどの電池・蓄電池
- 主にDCモーター(直流モーター)に使われる
- ロボット、電動工具、EV、自転車などに多い
③ ソーラーパネル
- 太陽光によって発電し、モーターに給電
- 屋外機器や無人設備などでの応用が進む
このように、モーターはさまざまな電力源と
組み合わせることができるため、幅広い分野で使われているのです。
モーターの種類と特徴
モーターには多くの種類がありますが、
ここでは代表的な2つを紹介します。
DCモーター(直流モーター)
- 電池などの直流電源で動く
- 回転数の制御が簡単、正逆転もしやすい
- 小型ロボットやミニ四駆、ドローンなどに多い
ACモーター(交流モーター)
- 家庭や工場の交流電源で動く
- 高効率・長寿命で大型用途に適している
- 家電や産業機械、ポンプ、コンプレッサなどに多用
モーターの選定では、電源の種類、回転制御のしやすさ、
トルク、寿命、コストなどを比較検討します。
まとめ:モーターは「電気+磁石+導線」の組み合わせで動く!
モーターが電気で動くのは、「電流」と「磁界」が
生み出す「力」によって回転が生まれるからです。
▶ 磁界の中に電流を流すと、導線が動く(電磁力)
▶ その力を使って回転運動を生み出すのがモーター
▶ 回り続けるために工夫された仕組みがモーター内部にある
▶ 電力源はコンセント、バッテリー、太陽光などさまざま
モーターは私たちの生活を支える非常に身近で重要な技術です。
その基本原理を知ることで、家電から産業機械まで、
より深くモノづくりに関わることができるでしょう。


モーターやアクチュエーターなど、
機械の駆動源に関する基礎知識と
選定基準をまとめています。


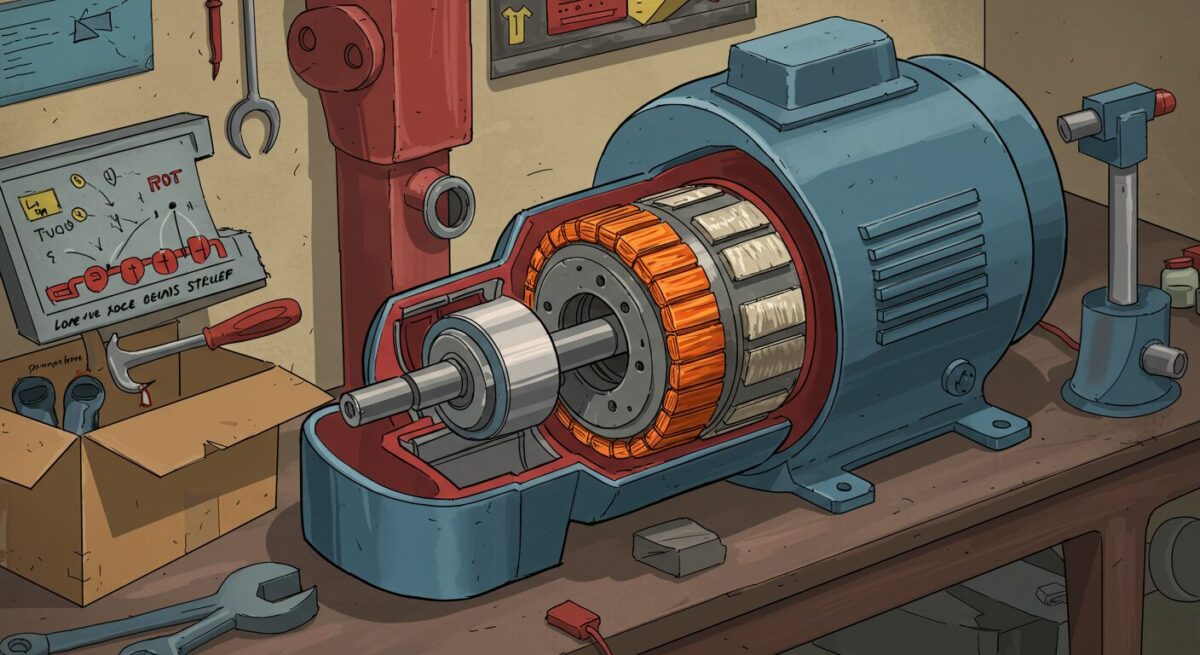

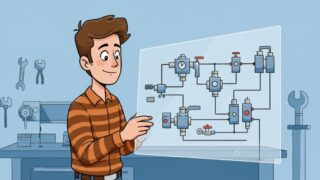



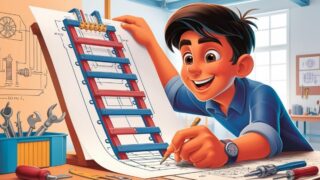
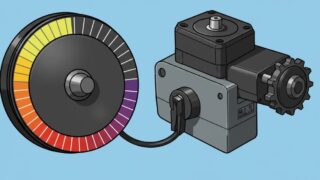

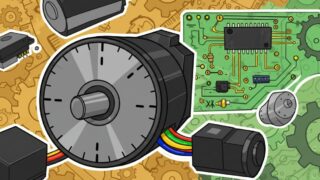

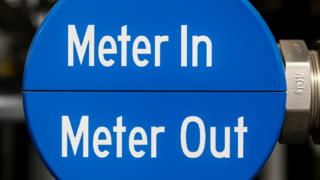



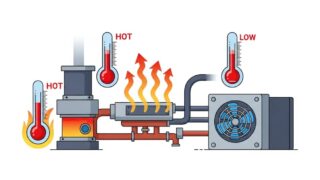



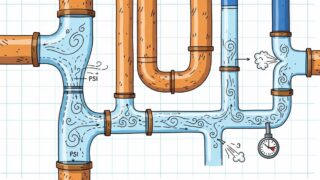
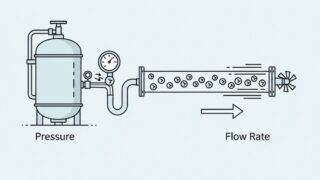



コメント