「S45C相当」
「SUS304相当」
「A5052相当」…
ミスミのカタログや3D CADデータでよく見かけるこの“相当材”という表記。
「同じ材料じゃないの?」と思っていたら、ちょっと注意が必要です。
この記事では、相当材とは何か、どう扱えばいいか、
そして設計にどう影響するのかをやさしく解説します。
「相当材」ってそもそも何?
相当材とは、元の材料(JIS規格など)に性能が近く、
同等の用途に使える材料のことです。
ただし、まったく同じ材料ではないという点が重要です。
よく見かける相当材の例
| 表中の表記 | 解説内容 |
|---|---|
| S45C相当 | JIS規格外の中炭素鋼・引張強さは近い |
| SUS304相当 | JIS G4303 以外のステンレス鋼で類似材 |
| A5052相当 | A5052 に近いアルミ合金、性質差あり |
ミスミにおける相当材の背景と根拠
S45C(相当)
ミスミの公式情報によれば、「S45C(相当)」とは、
「S45C〜S50Cに相当する材質を使用する可能性がある」ことを意味しています。
【相当定義】
S45C(相当)とは、S45C~S50Cの相当品を使用する可能性があることを指します。
つまり、JIS 規格の S45C に厳密に該当するとは限らず、
特性が近い広い範囲の炭素鋼(SC 系)を
相当材として使っている可能性があるということです。
S45C は JIS 規格による「機械構造用炭素鋼(SC 材)」と定義されており、
炭素含有量が約 0.45% で、熱処理可能なことで知られます。
S50C のような近似材を含むことから、
ミスミの「相当材」表記が複数の特性を許容している理由になります。
SUS304(相当) & A5052(相当)
ウェブ上では、SUS304 相当や A5052 相当の具体的仕様について
明記された公式情報は確認できませんでしたが、
同等性能を目指した代替材料として利用されるもので、
全く同じ材料ではない可能性がある点に注意が必要です。
なぜ「相当材」を使っているの?
~品質とコストを両立させる材料選定の工夫~
「ミスミで注文したら“S45C相当”とか“SUS304相当”って書いてあるけど、
これって本物のJIS規格材じゃないの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
実はこの「相当材」には、きちんとした理由とメリットがあります。
本項では、ミスミが相当材を使う理由と、
設計者として知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
相当材を使う理由
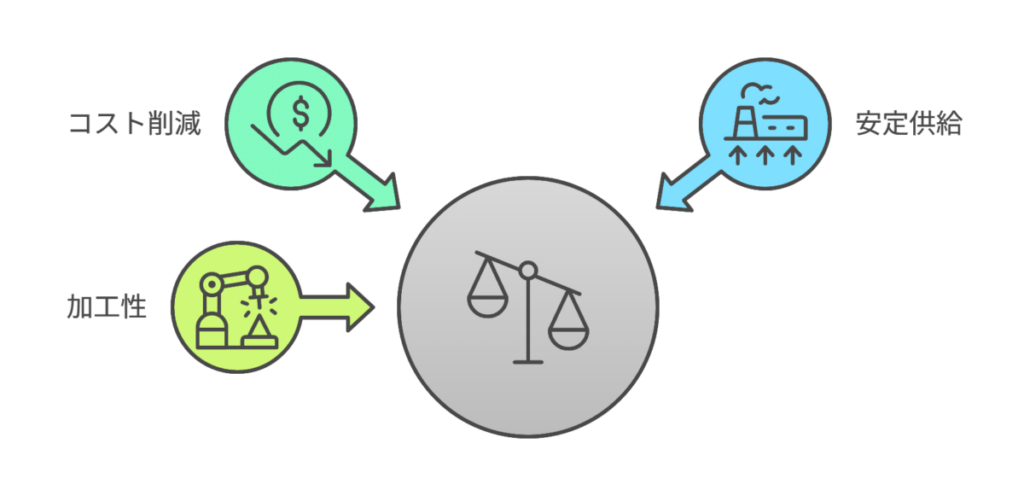
コストを抑えるため
JIS規格の材料は、厳密な成分管理と検査コストがかかります。
一方、相当材は海外規格や社内基準で選定された素材で、
同等性能を保ちつつ安価に調達できるのが特徴です。

材料コストが下がれば、部品全体の価格も下がり、安く早く入手できます。
安定供給のため(グローバル調達)
日本国内だけでなく海外でも手に入る素材を活用し、
需給バランスの変動に強い仕組みを構築できます。

相当材を使えば、特定のJIS材に依存せず、供給の安定化と短納期化が可能になります。
加工性を考慮して選ばれていることも
材料によっては、JIS材よりも切削しやすい・変形しにくいといった
特性を持つ相当材もあります。
設計意図に合う特性を持つ材料を選定することで、
品質と加工効率を両立する狙いもあるのです。
設計者が注意すべきこと
相当材はあくまで「JISと同等の性能を持つ」素材。
ただし、厳密な材質成分やトレーサビリティが求められる用途(医療・航空など)では、
相当材ではなく正式なJIS材を指定するべき場面もあります。
懸念がある場合は、「JIS材を指定」や「材質証明書の要求」で対応しましょう。
相当材は“現場に優しい選択肢”
| 観点 | 相当材のメリット |
|---|---|
| コスト | JIS材より安価に仕入れられる |
| 納期 | 海外調達や複数調達ルートにより短縮できる |
| 加工性 | 切削や曲げに適した特性のものを選べる |
ミスミの「相当材」表記は、単なるコストカットではなく、
品質・価格・納期のバランスをとるための合理的な工夫なのです。

設計者としては、「相当材=品質が劣る」と誤解せず、
どういう用途で使うか・何が求められているかを意識して、
材料指定を判断しましょう。
設計者が知っておくべき注意点
相当材でも多くの場合は問題なく使えますが、
次のようなケースではしっかり確認が必要です。
精密部品や強度部品
疲労強度・硬度・靭性などを確認しましょう。
微妙な差が寿命や安全性に影響する可能性があります。
溶接や熱処理が関わる部品
材料の成分組成によって、焼き割れ・溶接性の悪化が起こることがあります。
医療・食品・輸出用などの厳しい規格要求品
→ 正規のJISやISO番号指定が必要な場合、相当材はNGになることもあります。
相当材とのうまい付き合い方
| 項目 | 対応のヒント |
|---|---|
| 材料指定 | カタログ記載の材質欄を必ずチェック。 「S45C相当」などの表記は“別物”と認識する |
| 強度・性能 | 必要な機械的特性(引張強さ・硬度など)と比較する。 メーカーにデータシートを確認するのも◎ |
| 指定が厳しい場合 | 図面や仕様書に「JIS○○準拠材を使用」と明記することで、 代替を防ぐことが可能 |
| トレーサビリティが必要な場合 | ロット証明書やミルシートの提出可否を確認する |
現場あるある:相当材でこんなすれ違いも…
👷♂️ 現場「ミスミでS45Cって書いてあったけど、削ってみたら硬くて変だよ?」
🧑💻 設計「しまった、実は“相当材”って書いてあった…」
材料の加工性や硬さが違うことで
工具摩耗や公差不良が発生することもあります。
まとめ:相当材は“便利な味方”でも“要注意”でもある!
▶ ミスミの相当材は、コストや納期面で大きなメリットがあります
▶ ただし「本物のJIS材と同じだろう」は禁物!
▶ 強度や精度が求められる場面では、材料仕様の確認が設計者の責任です
相当材は「使える場面」と「使ってはいけない場面」を見極めることが大切です。
➡ 材料選定に迷ったら、現場や仕入先、ミスミの仕様書を活用しよう!
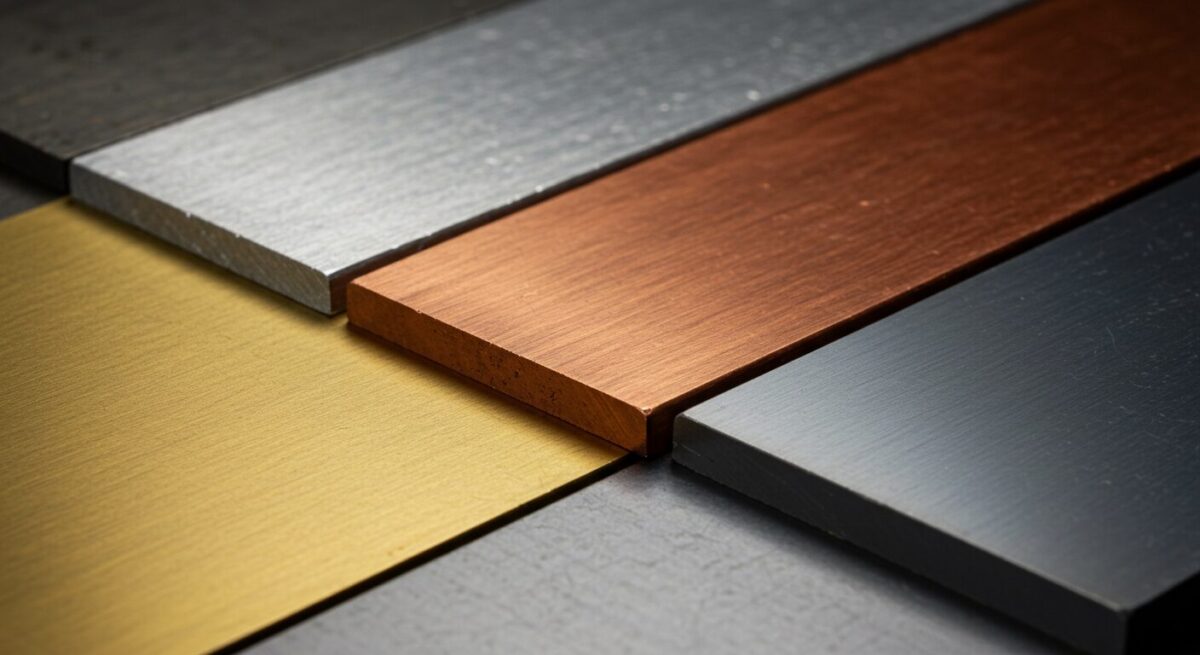
























コメント