金属といえば「磁石にくっつく」というイメージを持つ方が多いと思います。
ところが、ステンレス鋼(SUS304)に磁石を当てても
「全然くっつかない!」ということがあります。
「ステンレスって鉄でできてるんじゃないの?」
「どうして磁石がくっつかないの?」
そんな疑問に、機械設計の視点からわかりやすく答えていきます。
SUS304ってどんな金属?
SUS304は、「オーステナイト系ステンレス鋼」と呼ばれる種類の金属です。
主な成分は「鉄」+「クロム(Cr)」+「ニッケル(Ni)」
錆びにくく、耐食性が高いので、
台所用品・建材・機械部品まで幅広く使われています。
鉄なのになぜ磁石にくっつかない?

実は、「鉄でできている=磁石にくっつく」とは限りません。
磁石につくかどうかは、「結晶構造(結晶の並び方)」によって決まります。
鉄は「フェライト」だと磁性を持つ
普通の鉄(Fe)は「フェライト構造」を持っていて、強い磁性を持ちます。
つまり磁石にしっかりくっつきます。
SUS304は「オーステナイト」だから非磁性
SUS304は、ニッケルを多く含むことで「オーステナイト構造」に変化しています。
このオーステナイトは磁性を持たない結晶構造なので、磁石にくっつかないのです。
なぜオーステナイト構造は磁石にくっつかないの?
結論から言うと、
オーステナイト構造は「原子の並び方(結晶構造)」の違いによって磁性を持たないのです。
まず、金属の磁性はどこからくるの?
金属が磁石にくっつく理由は、
「鉄の原子がもつ磁力(スピン)」が整列するためです。
磁力を持つ原子が
同じ向きにそろう(=磁区ができる)と
磁石に引き寄せられる「磁性」が生まれます。
このような性質を「強磁性(きょうじせい)」と呼びます。
普通の鉄やSUS430(フェライト系ステンレス)はこのタイプです。
オーステナイト構造は「スピンがそろわない」
SUS304に代表されるオーステナイト系ステンレスは、
鉄の結晶構造が「面心立方格子(FCC構造)」という並び方になっています。
この構造になると…
原子間の距離や配置の関係で
電子のスピンがバラバラの方向を向いてしまい
磁力が打ち消し合ってしまう
つまり、「全体として磁性を持たない=磁石にくっつかない」というわけです。
なぜSUS304はオーステナイト構造になるの?
SUS304にはニッケルが多く含まれており、
これが鉄の結晶構造をオーステナイトに安定化させる働きをしています。
通常、鉄は冷えるとフェライト(磁性あり)になる性質がありますが
ニッケルが多いと、冷えてもオーステナイト構造のまま保たれる
結果として、常温でも非磁性のまま

これが、SUS304が磁石にくっつかない最大の理由です。
オーステナイトは「磁石にくっつかない結晶構造」
このように、磁性の有無は成分だけでなく
「結晶構造」でも決まるというのがポイントです。

設計では「ステンレスだから非磁性」と思い込まず、
構造の違い=フェライト系 or オーステナイト系を
しっかり見分けることが重要です。
加工すると磁石につくこともある?
実は、SUS304でも加工の仕方によっては
磁石にくっつくようになることがあります。
強い曲げ加工や冷間加工をすると、
一部が「マルテンサイト化」して磁性を帯びます。
そのため、見た目は同じSUS304でも
「新品の板はつかないけど、曲げた端だけ磁石につく」ということもあります。
これは構造が部分的に変わったためで、
素材の性質が劣化したわけではありません。
他のステンレスは磁石にくっつくの?
はい、ステンレスでも種類によって磁石にくっつくものがあります。
| 種類 | 名称 | 磁石にくっつく? |
|---|---|---|
| SUS304,SUS316,SUS303 | オーステナイト系 | ❌ つかない |
| SUS430 | フェライト系 | ✅ くっつく |
| SUS440C | マルテンサイト系 | ✅ くっつく |
ステンレスすべてが非磁性というわけではありません。
ニッケルの含有量と結晶構造の違いがカギです。
設計における注意点
磁性の有無は、以下のような場面で重要になります。
磁気センサーや磁場に影響を受ける部品では、
非磁性のSUS304が適しています。
一方で、マグネット式の固定具などには
SUS430など磁性のある材質が必要です。
材料選定の際には、「ステンレス」とひとまとめにせず、
磁性の有無もチェックするのが設計のコツです。
非磁性なら「非金属」も検討してみよう!
金属は多くが磁石に反応する性質を持っていますが、
非金属材料は基本的に磁石にくっつきません。
非金属材料の代表例
| 材料名 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 樹脂(エンプラなど) | 軽量・加工性良好・絶縁性あり | カバー、ギア、スライド部品 |
| セラミックス | 高硬度・耐摩耗・耐熱性 | 絶縁部品、高温部品 |
| ゴム・シリコン | 柔軟性・密封性 | パッキン、吸振材 |
| カーボン・CFRP | 軽量・高剛性 | ロボットアーム、治具、構造材 |
これらの材料は磁石にまったく反応しない非磁性材料であり、
用途によっては金属以上のメリットを発揮します。
まとめ:SUS304が磁石にくっつかない理由
✔ SUS304はオーステナイト構造であり、磁性を持たない
✔ 同じ「鉄ベースの金属」でも、結晶構造の違いで磁石への反応が変わる
✔ 加工により部分的に磁性を帯びることもある
ステンレスの種類によって磁石にくっつくかどうかが変わるため、
用途に応じた選定が重要
見た目は同じでも、ステンレス鋼の中身は奥が深い!
「磁石につく・つかない」も、
材料選定の重要な判断基準のひとつです。
現場でのトラブルやミスを防ぐためにも、
材料の性質を知って使い分ける力を身につけましょう!
























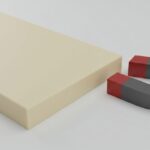
コメント