~液体や気体の流れを見える化するセンサー~
製造装置や機械設備の中で、
液体や気体が「どれだけ流れているか」を
正確に把握することは非常に重要です。
その流れの量を検出・監視するのが
「流量センサー(フローメーター)」です。
機械設計者にとって、適切な流量センサーを選ぶことは、
「工程の安定」「異常検知」「エネルギー管理」のために欠かせません。
この記事では、流量センサーの基礎から
種類別の特性、選定時の注意点までを詳しく解説します。
流量センサーとは?
流量センサー(flow sensor)は、液体または気体が
「どれだけの量」「どれだけの速度」で流れているかを
検出・出力するセンサーです。
測定方式の種類
| 測定方式 | 測定対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 質量流量計 | 液体・気体 | 実際の質量を検出、温度や圧力の影響が少ない |
| 容積流量計 | 主に液体 | 体積ベースで検出、配管条件に依存 |
| 流速型 | 気体・液体 | センサー内部の流速から演算して流量を算出 |
主な流量センサーの種類と特性
熱式流量センサー(サーマル式)
電磁式流量センサー
コリオリ式流量センサー
タービン式流量センサー
超音波式流量センサー
流量センサー選定時のチェックポイント
測定対象の種類
使用環境
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 温度範囲 | 高温流体や冷却水ラインでは耐熱性が必要 |
| 圧力条件 | 高圧ガスや負圧下で使用する場合は耐圧確認 |
| 接液材質 | 腐食性液体にはSUSやフッ素樹脂など耐食性を考慮 |
流量レンジと精度
出力仕様と接続方式
流量センサー選定時の注意点
応用例・導入メリット
| 導入先 | 効果 |
|---|---|
| 自動充填機 | 定量制御による精度向上、歩留まり改善 |
| コンプレッサ管理 | エア消費量の可視化による省エネ |
| 化学プロセス | 有害・腐食性薬液の定量供給で安全性向上 |
| 工場ユーティリティ | 水・冷却水・エア・スチームの配管管理 |
「流体の流れを見えるようにすることで、
装置の“内部の健康状態”がよくわかるようになります。

異常の予兆を検知したり、省エネにもつながるので、
うまく使えば“守り”にも“攻め”にもなる優秀なセンサーです。」
流量と流速の違いとは?
~流量センサーの基礎知識~
機械設計や設備設計の中で、「流量」と「流速」という言葉はよく登場します。
どちらも「液体や気体の流れ」に関係する用語ですが、それぞれ意味が異なります。
本項では、流量センサーを理解する上で必須となる
について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
流速(りゅうそく)とは?
流量(りゅうりょう)とは?
| 種類 | 内容 | 単位(例) |
|---|---|---|
| 容積流量 | 体積の流れ | L/min(リットル/分)、m³/h(立方メートル/時) |
| 質量流量 | 重さの流れ | g/s(グラム/秒)、kg/h(キログラム/時) |
流速と流量の関係
実は「流量」と「流速」は、管の太さ(断面積)を介して、密接に関係しています。
数式で表すと
【容積流量 Q(m³/s)】=【断面積 A(m²)】×【流速 v(m/s)】
💡つまり…
具体例で比較
| 項目 | 太い配管 | 細い配管 |
|---|---|---|
| 配管径 | 50mm | 10mm |
| 流速 | 1m/s | 1m/s |
| 流量 | 約117L/min | 約5L/min |
※どちらも同じ「1m/s」の流速ですが、配管が太ければ流量が圧倒的に多くなります。
なぜ流量センサーは「流速」だけでは足りないの?
一部の流量センサー(熱式・超音波式など)は、
流速を測定し、そこから流量を計算しています。
ですが、
「流速が分かっても、配管の断面積が分からないと流量は分かりません」。
そのため、実際の設計では以下のような情報を組み合わせて使います。
| 測定値 | どう使う? |
|---|---|
| 流速(m/s) | 配管内の流れの勢い・摩耗や騒音の指標にも |
| 流量(L/min) | ポンプ能力や供給量、定量制御に直結 |
間違いやすいポイント
違いをおさらい
| 用語 | 意味 | 単位 | 関係性 |
|---|---|---|---|
| 流速 | 流れる「速さ」 | m/s | 流速 × 面積 = 流量 |
| 流量 | 流れる「量」 | L/min, m³/h | 流速に面積をかけて求める |
配管のサイズや流体の性質に応じて、
流量センサーの出力をどう使うかが設計のポイントです。

“流速”と“流量”を正しく理解していないと、
誤った選定や制御ミスにつながるので注意!
まとめ
流量センサーは、液体・気体の流れを「見える化」する重要なセンサーで、
機械設計や制御に欠かせない存在です。
測定対象の性質や条件に合わせて、
方式(熱式・電磁式・超音波式など)を選定することが重要。
精度や出力方式、設置環境、コストバランスも考慮しながら
最適なセンサーを選びましょう。
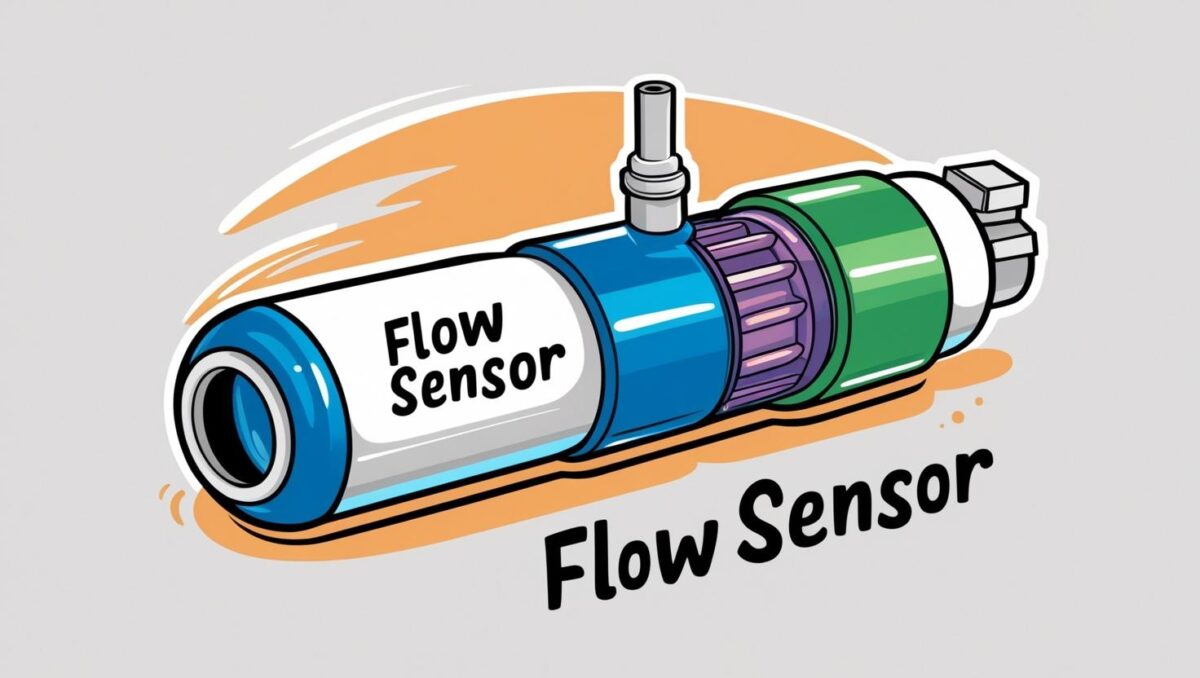

















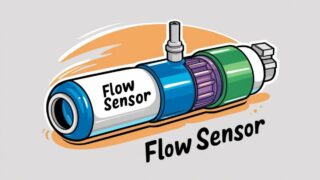






コメント