「昨日まで問題なく使えていたのに、突然ポッキリ折れた!」
そんな金属部品の破損は、疲労破壊(ひろうはかい)が原因かもしれません。
疲労破壊は前兆が少なく、突然壊れるため、非常に危険です。
この記事では、なぜ金属疲労は起こるのか?
そして どのように防げるのか? を、初心者にもわかりやすく解説します。
疲労破壊とは何か?
金属に繰り返し力(荷重)が加わると、
やがて表面に微小なキズ(き裂)ができ、
それが成長していきます。
そしてある日、突然「バキッ」と破断します。
これが「疲労破壊」です。
ポイントは以下の3つ
小さな力でも 繰り返されることで破壊につながる
見た目には 変化が分かりにくい
一度破壊が始まると 急速に進行する
疲労破壊のメカニズム
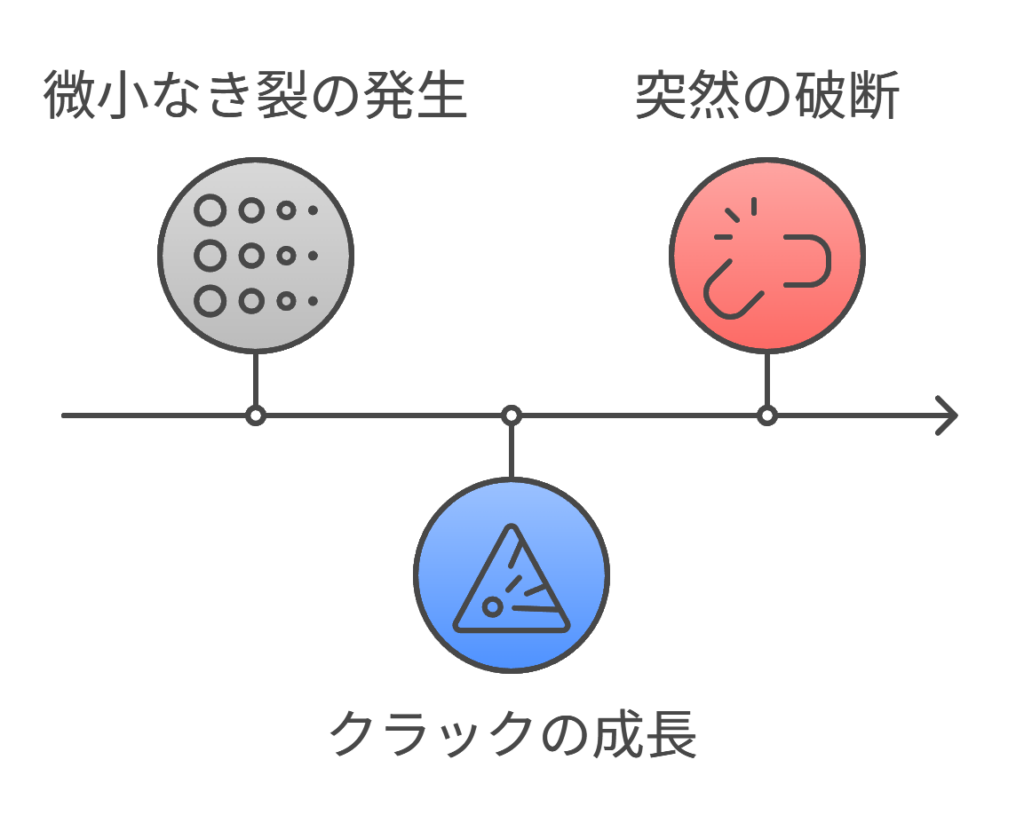
Step1:微小なき裂(クラック)の発生
金属表面の凹み、傷、応力集中(角や穴)などから小さなクラックが発生します。
Step2:クラックの成長
繰り返し荷重によって、そのクラックが徐々に成長していきます。
この段階では、目視ではほとんど確認できません。
Step3:突然の破断
ある日、クラックがある長さを超えると、急に破断します。
このときの破壊は、あっという間で一瞬です。
疲労破壊の例:どんな場面で起こる?
「どれも高い負荷がかかっていないように見えるのに、なぜ?」
実は、「繰り返し」使っていることがポイントです。
疲労破壊の対策は?
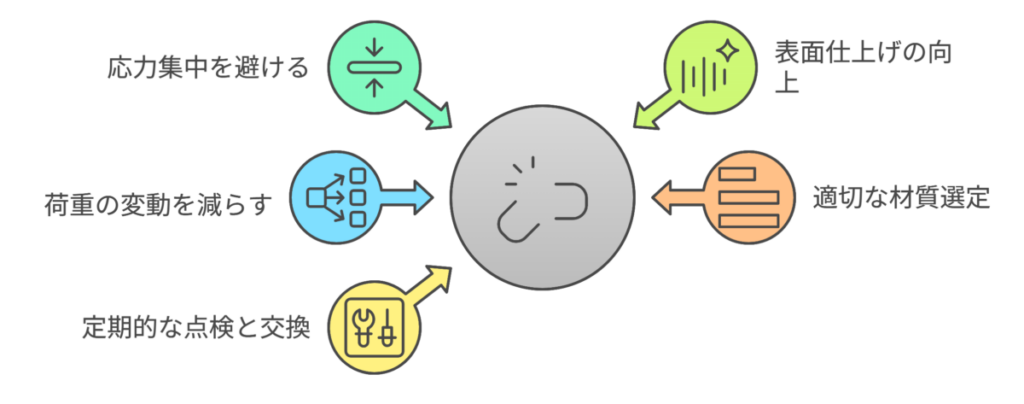
疲労破壊は防げます。
以下に代表的な対策を紹介します。
① 応力集中を避ける
角、穴、溝などは応力が集中するポイント。
対策
② 表面仕上げの向上
粗い表面は小さな傷が入りやすく、クラックの起点になります。
対策
③ 荷重の変動を減らす
荷重の大きさや向きが頻繁に変わると、疲労が進みやすくなります。
対策
④ 適切な材質選定
疲労に強い材質を選ぶことも有効です。
例
また、異種金属の接合部は特に応力集中しやすいため、慎重な材質と接合方法の選定が必要です。
⑤ 定期的な点検と交換
どれだけ対策しても、疲労の進行を完全に止めるのは困難です。
対策
疲労破壊の兆候を見逃すな!
微細なひび・異音・たわみが危険信号!
金属部品が突然折れる「疲労破壊(ひろうはかい)」は、
繰り返しの使用によるダメージの蓄積が原因です。
しかし、実は壊れる前に“サイン”が出ていることが多いのです。
本記事では、疲労破壊の兆候とその見抜き方を、
初心者の方にもわかりやすく解説します。
疲労破壊の兆候はココを見よう!
疲労破壊は、完全に壊れる前に小さな異変を出しています。
これを見逃さなければ、重大なトラブルを防ぐことが可能です。
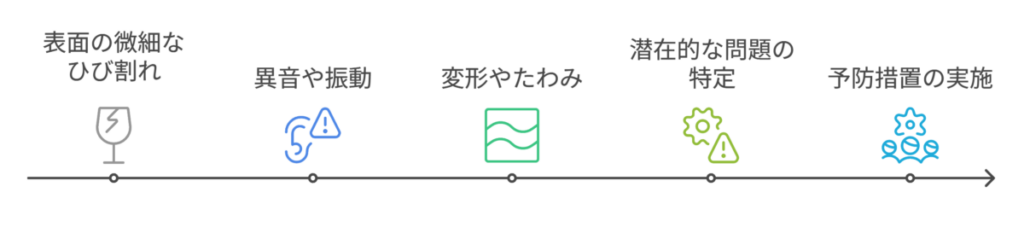
① 表面の微細なひび(クラック)
金属表面に髪の毛のように細いひび割れが現れたら要注意!
特に下記のような場所は、疲労クラックが発生しやすいです。
🔍 見つけ方のポイント
② 異音や振動の発生
装置を使っていて、「ガタガタ」「カチャカチャ」といった異音が出始めたら、
それは部品が劣化しているサインかもしれません。
🛠 対策
③ 使用年数に対しての変形やたわみ
明らかに無理な力が加わったわけでもないのに、
部品が少し曲がっていたり、たわんでいることはありませんか?
🔧 チェックポイント
疲労破壊を防ぐには「予防保全」がカギ!
兆候を見つけたとき、
最も重要なのは「まだ壊れていないから大丈夫」と思わないことです。
以下のような対策を定期的に行いましょう。
定期点検をスケジュール化
非破壊検査(NDT)を導入
⇒ 見えない内部の異常も検出可能!
トラブル事例を設計に活かす
過去に破損した部位を重点的にチェック
同じ構造や材料を使用している箇所を優先確認
小さな違和感が、大きなトラブルを防ぐ
疲労破壊は「突然壊れる」イメージがありますが、
実はその前に微細な異常やサインが出ていることが多いです。
これらの違和感に早く気づき、行動することで、
安全性・稼働率・信頼性を大きく高めることができます。

「見逃さない目」と「対処する判断」が、
機械設計・保全のプロとしての一歩です。
日々の点検・気づきが、大きな安心と安全につながります。
まとめ:疲労破壊は「静かに近づく爆弾」
✔ 疲労破壊は、目に見えないダメージが蓄積して起きる破壊
✔ 「突然壊れた!」の裏には、長期間の繰り返し荷重がある
✔ 応力集中を避ける設計・材質の選定・表面処理・定期点検がカギ
設計者が疲労破壊のリスクを知っているかどうかで、
製品の安全性は大きく変わります。
「壊れてから対処」ではなく、
「壊れる前に防ぐ」知識を、ぜひ設計に活かしてください!
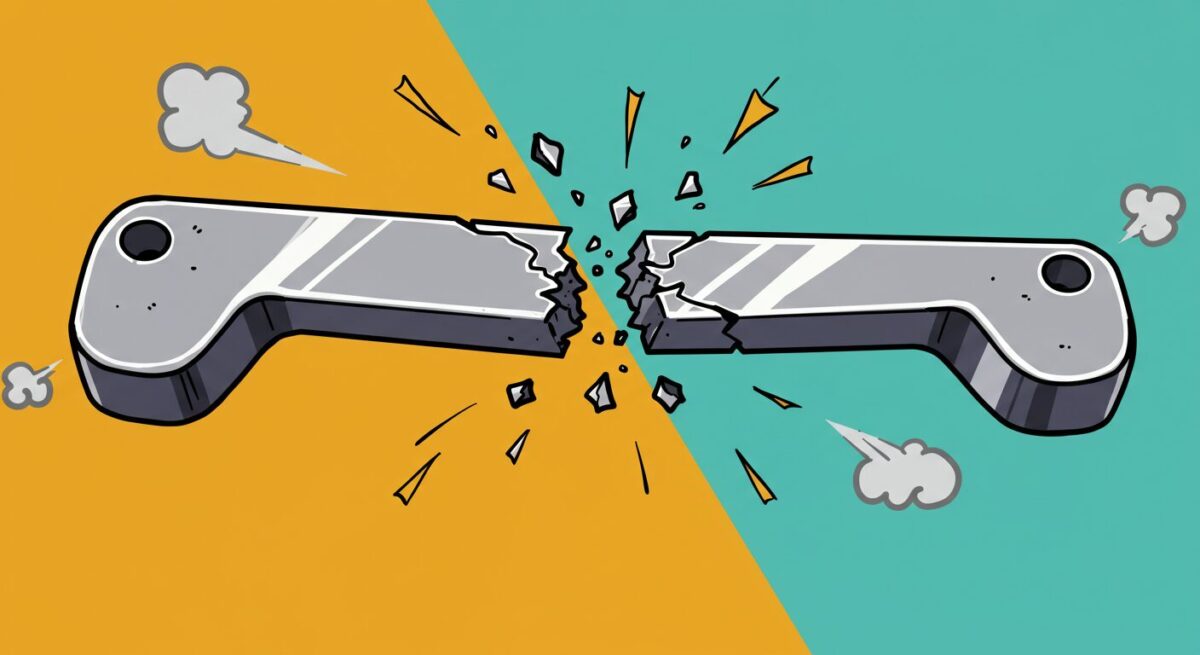
























コメント