「熱膨張」は機械設計で見逃せないポイント
機械や装置を設計するうえで、
「温度変化」による部品の伸び縮み=熱膨張は非常に重要な現象です。
金属は熱くなると膨らみ、冷えると縮むという性質があり、
この性質を無視すると、寸法不良、部品干渉、精度低下などの
トラブルが起こる可能性があります。
この記事では、初心者にもわかりやすく、
熱膨張の基本と設計での考慮ポイントを解説します。
そもそも「熱膨張」とは?
金属などの材料は、温度が上がると内部の原子が激しく振動し、
原子間の距離が広がるために体積が膨張します。
逆に温度が下がれば振動が収まり、元に戻ろうとします。
この現象はどの材料にも起こりますが、
材料ごとにどれだけ膨張するかは異なります。
その膨張のしやすさを表す値が、線膨張係数(熱膨張係数)です。
例)線膨張係数(目安)
| 材料 | 線膨張係数(×10^-6 /℃) |
|---|---|
| アルミニウム(A5052) | 約23 |
| 炭素鋼(S45C) | 約12 |
| ステンレス鋼(SUS304) | 約17 |
| 樹脂(POM) | 約100 |

アルミは鋼の約2倍、POM(樹脂)はそのさらに数倍も膨張します。
設計でよくある熱膨張の影響
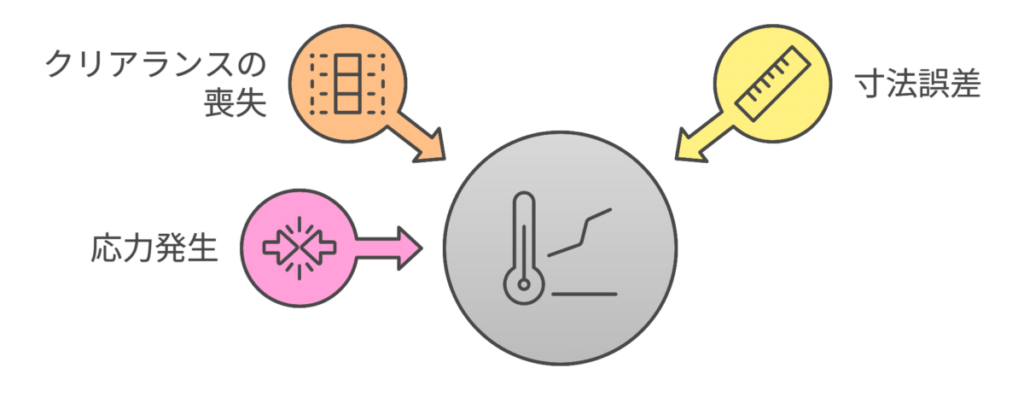
クリアランスがなくなる・動かなくなる
熱で膨張して隙間(クリアランス)がゼロになり、
部品が動かなくなることがあります。
🔍 例)
スライド機構、シャフトとブッシュなど
精密寸法がズレる
精密加工部品で、
常温での公差設計だけに頼ると温度変化でズレが発生します。
🔍 例)
測定器具、カメラ機構、金型部品など
応力が発生し、割れや歪みの原因に
異なる材料を組み合わせていると、
膨張率の違いで応力が発生し、ひび割れや反りの原因になります。
🔍 例)
アルミフレームに鋼部品を固定した場合など
設計での熱膨張対策
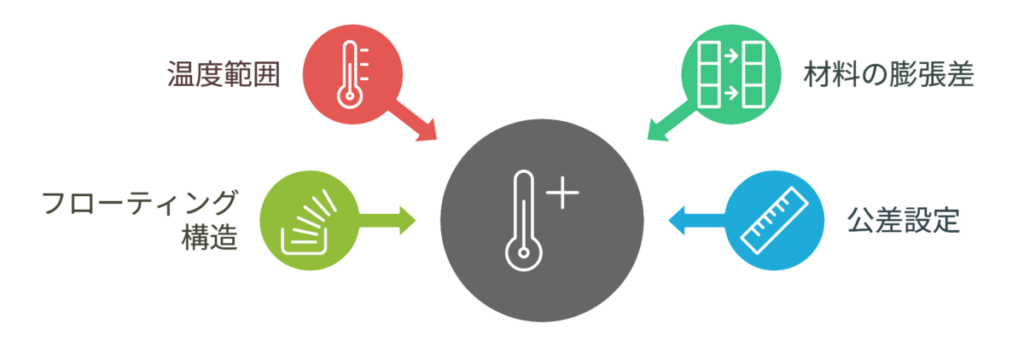
使用温度範囲を考慮して寸法設計する
使用環境の温度変化(例:常温20℃→夏場50℃)を見越して、
部品長の変化量を予測して設計します。
計算例
\( \displaystyle ΔL=α⋅L0⋅ΔT\)
- ΔL:変化する長さ(膨張量)
- α:線膨張係数(単位:1/°C または 1/K)
- L₀:元の長さ(膨張前の長さ)
- ΔT:温度変化(最初の温度と最終温度の差)
この式によって、
温度変化に応じた材料の長さの変化を予測することができます。
\( \displaystyle ΔL=23×10^-6⋅100⋅30=約0.069mm\)
これだけでも0.07mmの誤差。精密設計では無視できません。
材料の膨張差を揃える
複数部品を組み合わせるときは、
線膨張係数が近い材料同士を選ぶことで、歪みや応力を抑えられます。
フローティング構造やスリットで逃がす
膨張を許容するように、片側固定+片側自由にしたり、
スリットやガタを設けて膨張分を逃がす構造にします。
公差設定に余裕を持つ
クリアランスを設ける場合、
最大温度でも干渉しないように寸法公差を設計します。
熱膨張対策は“設計”だけじゃない!
~温度変化のない環境づくりが安定稼働のカギ~
機械設計では「熱膨張」に注意が必要!
機械や装置の部品は、温度が上がるとわずかに膨張し、
温度が下がると収縮します。
この現象を「熱膨張」といいます。
たとえば、金属の部品ではわずかな温度変化でも
0.1mm以上の寸法変化が起きることがあります。
精密な機構になるほど、この変化が原因で
「ズレる・当たる・動かない」などのトラブルにつながります。
設計者は、まず熱膨張を「避けられないもの」として考える
熱膨張は、材料の持つ物理的な性質。
つまり、どんなにうまく設計しても、温度が変われば必ず起きる現象です。
だからこそ多くの設計では、
といった熱膨張を吸収する工夫が必要になります。
しかし、もう一つ重要な視点があります。
対策そのものを“不要”にする考え方
それが「温度変化の少ない環境づくり」
そもそも温度が変わらなければ、熱膨張は起こらない。
これは非常にシンプルですが、とても有効な発想です。
つまり、熱膨張対策の最も根本的な方法は、
部品や装置が使われる環境の温度を一定に保つことです。
温度変化のない環境づくりの方法
恒温室(こうおんしつ)の活用
精密測定や高精度加工が行われる現場では、
20℃前後で安定した温度に保たれた「恒温室」が使われます。
機械や材料の膨張収縮を抑え、安定した作業が可能になります。
🔍 例)
金型部品の仕上げ加工、検査室での寸法測定など
断熱材や遮熱対策を装置に施す
周囲の熱の影響を受けにくくするために、
といった方法で、急激な温度変化を防ぎます。
空調や冷却ファンで温度安定化
屋内工場でも夏と冬では温度が大きく異なるため、
などの環境制御も大切です。
温度変化を軽視するとどうなる?
寸法誤差により組付け不良や軸の固着
精密機器の測定精度がばらつく
違う材質同士で応力がたまり、ひび割れや反り
長期間で見ると、寿命や性能にも悪影響
つまり、熱膨張の影響は小さな誤差の積み重ねで、
大きなトラブルにつながるのです。
設計と環境の“両輪”で対策しよう!
熱膨張を完全になくすことはできませんが、
この両方を組み合わせることがベストです。

特に、高精度が求められる機械や長時間連続運転する装置では、
「環境づくり」の重要性は非常に高くなります。
温度が安定すれば、すべてが安定する
熱膨張は物理現象ですが、それを設計で吸収するか、
発生させないようにするかは設計者の工夫次第。
機械がいつでも同じ動作、同じ精度で動いてほしいなら、
環境の温度を一定に保つことは欠かせません。
それはまさに、見えない部分の「安定性設計」なのです。
まとめ:熱膨張を「無視しない」ことがトラブル回避の第一歩
温度変化による膨張・収縮は、すべての材料に起こる自然な現象です。
特に、可動部品や異種材を組み合わせる装置では、
熱膨張を意識しないと精度・強度・信頼性すべてに悪影響を及ぼします。
熱膨張はトラブルの元にもなりますが、逆に言えば、
「知って設計に活かせば強い味方」になります。
プロの設計者は必ず、「使う温度」を見越して考える。
これが、トラブルのない安定設計への第一歩です。
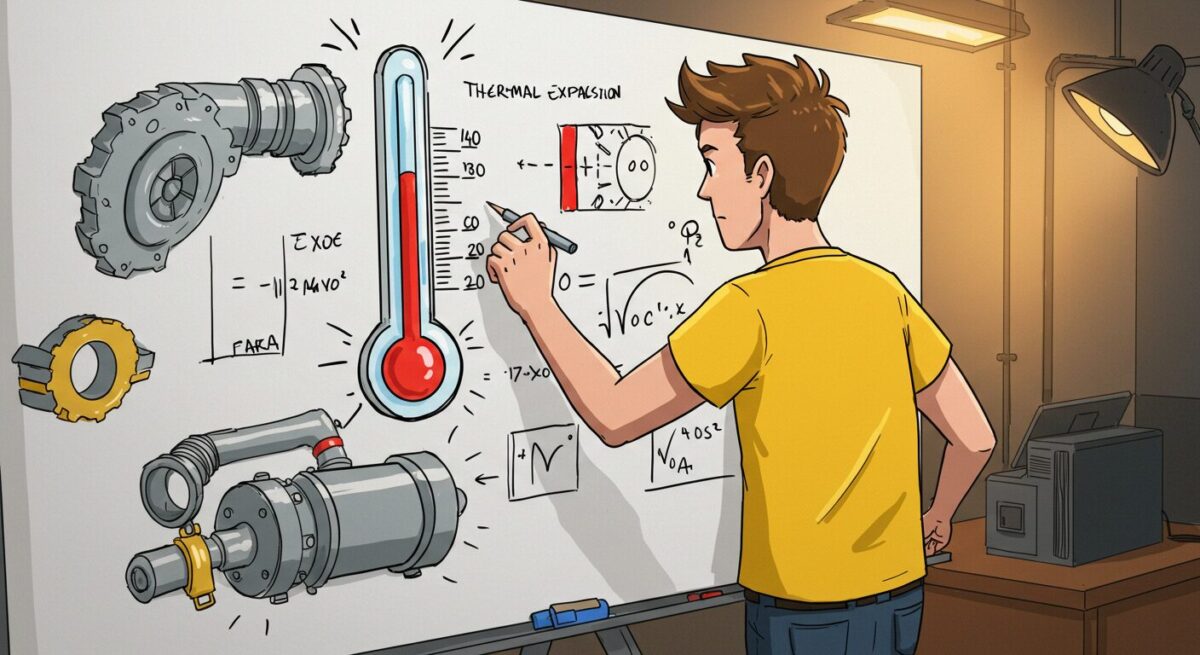























コメント