三価クロメートメッキは、亜鉛メッキの上に施す防錆処理の一種で、
環境規制に対応したクロメート処理として広く使用されています。
従来の六価クロムを含むクロメート処理(有害)に代わり、
環境負荷が低く安全な防錆処理として普及しています。
三価クロメートメッキの特性
| 項目 | 三価クロメートメッキの特徴 | 代替候補 |
|---|---|---|
| 耐食性 | ○ 六価クロメートよりは劣るが、防錆効果あり | 無電解ニッケルメッキ |
| 環境負荷 | ◎ 有害な六価クロムを含まず、RoHS対応 | – |
| 外観 | ○ 銀白色、やや青みがかった仕上がり | ユニクロメッキ(外観は類似) |
| 耐摩耗性 | △ 耐摩耗性は低め | 硬質クロムメッキ |
| コスト | ◎ 低コストで量産向き | 四三酸化鉄皮膜(黒染め) |
三価クロメートメッキのメリット
三価クロメートメッキの注意点
耐食性は六価クロメートより低い
→ 高耐食性が必要なら無電解ニッケルメッキを検討
摩耗しやすい
→ 繰り返し摩擦がかかる部分には硬質クロムメッキなどが適する
三価クロメートメッキの用途例

環境対応が求められる機械部品や量産品に適したメッキ処理です。
三価クロメートは精密部品に不向き? 寸法変化とばらつきの影響
三価クロメートメッキ は環境対応の防錆処理として広く使われていますが、
精密な寸法が求められる部品には注意が必要です。
なぜなら、メッキ処理の過程で 寸法変化やばらつきが発生 するため、
はめあい公差が厳しい部品には不向き だからです。
本項では、なぜ寸法変化が起こるのか、
どのような対策があるのかを初心者向けに解説します!
寸法変化とばらつきの原因
三価クロメートメッキでは、以下の理由で 寸法変化やばらつきが発生 します。
メッキの膜厚による影響
三価クロメートメッキの膜厚は 数μm(ミクロン)レベル ですが、
精密なはめあい公差が求められる部品では 数μmの違いでも影響が大きい です。
メッキの均一性のばらつき
メッキ処理は、部品の形状や処理方法によって
均一に付着しにくい ことがあります。
特に、角部や凹凸のある部品では膜厚が均一にならず、
ばらつきが大きくなる 傾向があります。
メッキ後の処理による変化
メッキ処理後に 水洗いや乾燥の工程 が入るため、
わずかな歪みや寸法変化が生じることもあります。
特に薄肉部品や細かい加工部品では、
この影響が無視できないことがあります。
精密部品ではどうすればいい?
メッキ後の仕上げ加工を検討する
寸法精度が重要な部品では、
メッキ後に仕上げ研磨や追加加工を行う ことで、
精度を確保できます。
ただし、コストが増加するため 事前に公差設計をしっかり行うことが重要 です。
メッキ前に寸法調整をする
メッキの膜厚を考慮して、
あらかじめ寸法を小さめ(または大きめ)に加工しておく 方法もあります。
例えば、設計時に 「メッキ厚さを考慮した公差を設定する」 ことで、
後工程の修正を減らせます。
代替処理を検討する
もし 高精度の寸法が必要 な場合は、
三価クロメートメッキではなく 無電解ニッケルメッキや特殊コーティング など、
膜厚管理がしやすい処理を検討するのも一つの方法です。
三価クロメートメッキは精密部品には注意!
三価クロメートメッキは環境対応で防錆力も高いが、寸法変化が発生する
メッキの膜厚によって、はめあい公差が狂う可能性がある
特に、精密な軸受け部品や摺動部では影響が大きい
メッキ後の仕上げ加工や、事前の寸法調整で対策が可能
公差が厳しい部品には、他の処理を検討するのも有効
三価クロメートメッキは非常に便利な処理ですが、
寸法精度が求められる部品には慎重に適用する必要があります。

設計段階から メッキ後の寸法変化を考慮した対策を行う ことで、
トラブルを未然に防ぐことができます!
三価クロメートメッキとは? ユニクロメッキからの移行が進む理由
近年、金属部品の防錆処理として 「三価クロメートメッキ」 が広く使用されています。
特に従来の 「ユニクロメッキ(六価クロムを含むクロメート処理)」 からの
移行が進んでいるのが特徴です。
なぜこのような動きがあるのか、わかりやすく解説します。
ユニクロメッキとは?
ユニクロメッキ は、鉄や鋼などの部品に 亜鉛メッキ を施した後、
六価クロムを含むクロメート処理 を行うことで、
耐食性(さびにくさ)を向上させた処理です。
仕上がりは銀白色で、ボルトやナット、金具などに広く使われてきました。
しかし、ユニクロメッキに使用されている 六価クロム は 有害な物質 であり、
環境や人体に悪影響を及ぼすことが問題視されていました。
三価クロメートメッキへの移行が進む理由
環境規制(RoHS指令)に対応
ヨーロッパを中心に、有害物質の使用を規制する
RoHS指令(ローズ指令)が制定されました。
この指令では、六価クロムの使用が禁止されており、
これに対応するために 「三価クロメートメッキ」 への移行が進んでいます。
人体への影響が少なく、安全性が高い
六価クロムは発がん性があり、作業者や使用者へのリスクが問題となっていました。
一方、三価クロムは人体への影響が少ないため、安全性の高い処理 とされています。
耐食性も確保
三価クロメートメッキは、従来のユニクロメッキと同等の耐食性を持つため、
ほとんどの用途で代替が可能 です。
コストも比較的安価
三価クロメートメッキは、六価クロムを使用しないにもかかわらず、
従来のユニクロメッキとほぼ同じコスト で処理が可能なため、
移行がスムーズに進んでいます。
三価クロメートメッキの今後
現在、多くの業界で ユニクロメッキから三価クロメートメッキへの切り替え が進んでいます。
特に 自動車、家電、建築業界 では環境対応が求められるため、
今後も三価クロメートメッキの需要は高まるでしょう。
環境規制が厳しくなる中、今後の機械設計において
三価クロメートメッキは必須の選択肢 となるでしょう!
まとめ
三価クロメートメッキは、環境規制(RoHS指令)に適合した防錆処理 であり、
従来の六価クロメートメッキに代わる選択肢として広く採用されています。
主に亜鉛メッキの上に施される処理 で、鉄部品の耐食性を向上させます。
✅ 特徴
✔ 六価クロムを含まず環境にやさしい(RoHS指令適合)
✔ 亜鉛メッキの防錆性を向上 させ、屋内用途に適している
✔ 仕上がりは淡い銀白色や虹色調 で、見た目が良い
✔ 耐食性はユニクロメッキと同等 で、比較的安価
🚫 注意点(選定ポイント)
✔ 屋外や高湿度環境では耐久性が低い(赤錆が発生しやすい)
✔ メッキ膜厚のばらつきに注意が必要(精密な寸法が求められる部品には不向き)
✔ 耐摩耗性は低く、摺動部品には適さない
三価クロメートメッキは、
環境規制対応・コスト面・防錆性能のバランスが取れた処理 ですが、
高耐食性が必要な場合や寸法精度が重要な部品には注意 が必要です。
用途に応じて、無電解ニッケルメッキや硬質クロムメッキなどの代替処理 も検討しましょう!






















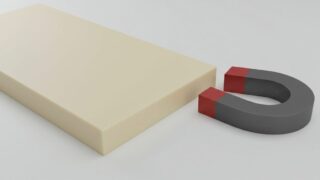


コメント